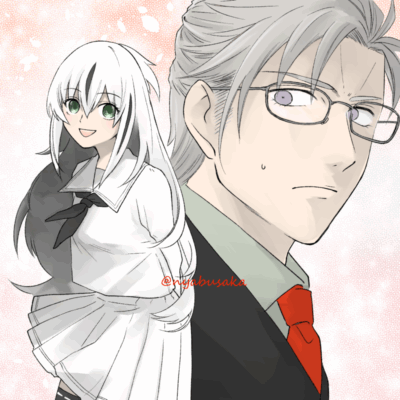「じゃあ土曜日、学校が終わったらそのまま行こうぜ」
「うん、ありがとう」
不意に耳に届いた会話は、稲葉と園村の間で交わされたものだった。二人が立ち話をしていたのは、俺が入って来た教室の扉からそう離れた場所ではなかったが、会話の仔細はわからない。わからないなりにも、どうやら二人で連れ立ってどこかに出かける相談でもしているらしいことは察しがついた。
園村は稲葉に軽く頭を下げて、自分の席へと戻っていく。退院したのはつい二週間ほど前だが、今のところ顔色もよく体調を崩すこともないらしい。
稲葉のほうはその場にしばらく立ったままだったが、その表情はヤツらしからぬものに感じられた。へらへらと締まりのない顔をするでもなく、うれしさを無理に押し込めるような表情でもない。言い表すのが難しいが、責任感と使命感で緊張しているような印象だった。一体話の中身が何なのか、多少気になったのは事実だが、俺は会話の中身を問いただすことはしなかった。問うたところで「南条には関係ねえだろ」と言われるのが関の山だろう。
俺は立ち止まらずに自分の席へ戻る。稲葉もまた同じように椅子に腰を落ち着けているようだった。
§
「てゆーかさぁ~稲葉と園村が話してたの聞いた?」
「モチよ……っつーことは、アヤセも聞いてた?」
「聞いてたっていうかぁ、聞こえちゃったっていうかぁ」
生徒の大半が帰宅済みの放課後の教室では、耳ざとい上杉と綾瀬が稲葉たちの会話を邪推していた。
「いやどう考えてもデートじゃん? 土曜日の放課後に出かけるってもうデートしかないじゃん?」
ほかに何があるのか?と言いたげな綾瀬が他人の机に尻を乗せて、相変わらず行儀の悪い身振り手振りと下世話な興味本位をむき出しにしている。しかし興味津々な態度は綾瀬だけではなかった。
「そりゃあ、話だけ聞けばそうだけどさあ、あの二人よ? マキちゃんがマークとデートとかナイナイ、ナイっしょ~」
薄く笑いを浮かべる上杉は否定する。言葉の上では「あり得ない」と言ってはいるものの、表情からは「あってはならない」という切なる願いのようなものが見て取れた。それは別に園村に対してなんらかの感情があるというわけではなく、単に稲葉に対する対抗心のようなものだろう。
「はあ? デートじゃなかったらなんで二人で出かけんのよ?」
「別にデートじゃなくても出かけることぐらいあるっしょ……」
「アヤセ、モテるからな~デート以外でそういうのわかんなーい。南条もそうでしょー?」
頬杖をついたまま、綾瀬が問いかける。
俺は迎えの車を待つために教室に残っていた。松岡の不手際ではなく、落ち度は今日が5限で終了することを伝え忘れていた俺にある。それを珍しく思ったらしい上杉と綾瀬は、益体のない会話に俺を巻き込まんとしていた。
なぜ俺にそういう話を振るのか理解に苦しむが、思い返せば綾瀬優香という人間の言動は半分くらい意味不明なものなので、考えるだけ無駄というものだろう。適当にあしらってしまうかと口を開きかけたものの、上杉に遮られた。
「いやいやいや、南条コンツェルンの御曹司がそんな、おいそれと、デートとか」
ないないない、と、三度重ねて否定するように片手を振っている。
「そんなことしようものなら週刊誌とかの餌食でしょうよ」
ね?と、前のめりになる上杉に、俺はしばし考えこんで「南条を記事のネタにするような気骨のある記者など、ここ数年は見た記憶もないがな」とだけ答えるにとどめた。
「わー……」
「えー? それどういう意味?」
意味を理解していない綾瀬の傍らで上杉は口元を軽くひきつらせているようだった。上杉秀彦は、当初の印象に反して物事の本質を見ることのできる男だ、俺の言わんとすることは簡単に理解したのだろう。
「やぁっぱ世界が違うっすね~」
「うそ、上杉意味わかってんの?」
この場に限っては洞察力を欠いた綾瀬は、結局上杉に掴みかかる勢いで迫り解説を聞いている。
「だから、下手に南条家の悪い記事なんか書こうものなら潰されるとか消されるとか、なんかそういうアレだよ」
他人に自分の発言をくどくどと説明されているのは何とも据わりの悪いものだった。それはそれとして、消されるというのは物騒極まりない。いくら南条とてそこまではしない。……多分。
「へー、そうなの?」
綾瀬が俺の方に向き直る。わかっているのかいないのか、いやそもそも上杉の説明があまり正鵠を得ていない気もする。だからといって俺自ら解説する気にもなれないので放っておいたが、綾瀬は悪気も嫌味も含まれない顔でこんなことを問いかけた。
「じゃあさ、逆に、南条はデートとかしても別に問題なくない? 女の子と出かけたりしないの?」
上杉は言葉には出さなかったが、興味と好奇が表情に出ている。
「……」
綾瀬にしろ上杉にしろ、なぜそうも人の動向を気にするのだろうか。理解に苦しむ。
「必要があれば出かけるし、ないなら出かけない」
なので、極めて機械的な振り分けを以って回答としたのだが二人の「決して褒められる種類ではない好奇心」は満たされなかったらしい。
「つまんねー」
「まあ南条らしいといえばらしいんじゃないの?」
好き勝手にブーイングを垂れている二人に「無理矢理聞いておいてなんだその反応は」と反論しかけたが、ポケットの中で携帯電話が震えたためその機会は失われた。迎えが来たために鞄を持って教室を出る俺に綾瀬と上杉が緩慢に手を振っている。なんとなく振り返す気にはなれなかったが、何もしないというのも場にそぐわない気がして、軽く片手を上げるだけに留める。
廊下を歩きながら嘆息を禁じ得なかった。馬鹿馬鹿しい時間を過ごしたものだ。
しかしその時の俺は知らなかったのである。この胡乱な会話が暗示的なものだったということを。
§
園村から電話を受けたのは、その日から二週間ほどが経った春休みのことだった。
「圭様、園村様からお電話です」
自室の子機まで回された電話の相手は、予想もしない名前だった。そもそもクラスメイトから電話がかかってくることが少ないのだが、相手が園村麻希だということが珍しさに拍車をかけている。受話器を取る手は躊躇うように緩慢な動作だったが、気のせいだと思いなおす。
「俺だ、何か用か?」
「あっ、南条くん、ごめんね春休みなのに」
電話越しに聞く園村の声は、肉声よりも低く聞こえた。
「いや、構わん。今日は予定もない」
「そうなの? じゃあ少し、話しても大丈夫?」
少し鼻白んでしまう。おそらく本題に入る前に様子見のような雑談が繰り出されるのだろうと直感できた。時間がないわけではないが、俺は益体のない雑談に意味を見出せる人間ではない。なので、園村には悪いが真っ向から切り込ませてもらった。
「ああ。何かあったのか?」
俺の予感が当たったのだろう。出鼻をくじかれ、園村が少し息を呑んだ気配が感じられた。
「何かあったわけじゃないんだけど……」
とは言うが、園村の声は硬い。何かトラブルに巻き込まれたりしたのだろうか。仲の良い同性の友人――姫野や香西、あるいは黛や綾瀬や桐島を差し置いて俺に電話をかけてくる用事には全く心当たりがないし予想もつかない。ただ、もしも園村が「南条」の助力を求めているのなら、できる範囲では応えてやりたいとは思う。友人として、クラスメイトとして。
園村はしばし押し黙っていたが、ようやく口を開いても相変わらず歯切れが悪い。
「あの……怒らないでほしいんだけど、ううん、それは無理かもしれないから……でも、できれば怒らないで聞いてほしいんだけど」
「なんだ」
「怒らない?」
多少、苛立っていたのだと思う。
「内容も聞かずに判断できると思うか?」
「……ですよね」
苦笑交じりの園村が、やや深めに息を吸った気配がした。
「実は南条くんにお願いがあって」
うん、と、促した先の答えは――さすがに予想していなかった。
「山岡さんの、お墓参りをさせてもらいたくて」
§
「実はこの前、稲葉君にもお願いして、お墓参りに行ってきたの」
園村からの電話から二時間ほど後。お互い午後の予定がなかったのを幸いに――善は急げというわけではないが――俺は園村の自宅まで向かった。車をまわす松岡は何か言いたげだったが、山岡の墓参りだと言うと少しバツの悪そうな顔で黙り込む。理由はわからないでもない。大方、俺と同じだろう。
園村は自宅の前に立って待っていた。グレーのワンピースを着て俯いている姿が、春の日差しの中でそこだけ沈んで見えた。
山岡の墓は、御影町から車で半時間ほどの霊園にある。向かう途中の車内で、園村はまた別の墓参りのことを語り始める。
「御影警察署で亡くなった、刑事さんの」
合点がいった。俺は稲葉とその刑事について詳しくは知らないが、どうも顔見知り以上の親しい間柄だったことは間違いないと思う。もしかしたら、補導されるなどして世話になったことも少なくないのかもしれない。あの刑事の、変わり果てた姿を目の当たりにした稲葉の反応からは、そのくらいは想像できた。
それをきっかけにして、思考の糸がつながっていく。
二週間ほど前の、稲葉と園村の会話。あれは園村が墓参りに行きたいと申し出たに違いない。稲葉なら、あの刑事の住まいや墓にも心当たりがあってもおかしくはないから。稲葉も稲葉なりに、園村がそんなことを言い出した理由は察しただろう。
「稲葉は何か、言っていたんじゃないか」
「――うん。稲葉君は、私を励まそうとしてくれたんだと思う」
稲葉がどんな言葉をかけたのか、わざわざ園村に問わずともわかったので俺は何も言わなかった。
車内に会話はない。俺はすれ違う対向車を、園村は歩道の人や木々を漫然と眺めている。その膝の上には、白い花束が抱えられている。
§
山と呼ぶには高さも足りない小高い丘の頂上付近に、山岡は眠っている。駐車場は霊園のすぐ隣にもあるのだが、俺は丘へとつながる県道の入り口前で車を止めさせた。園村には歩きやすい靴で来るように言い含めていたし、それなりに歩くことは了承済みだった。
道路上の標識には霊園までの距離が表示されている。目的地を示す十字架のイラストを見上げながら、園村は疑問を口に出した。
「山岡さんって、クリスチャンだったの?」
「いや、多分違うと思う。ここに墓があるのは……山岡がずっと仕えていた俺の大伯父の墓があるからだ。……山岡には身寄りがなくてな」
無縁仏として役所に「処理」されるのはあまりにもしのびなかったので、俺がそう手配した。
「そう、なんだ……」
会話が途切れてしまい、居心地のよくはない沈黙が続く。
山岡に連れられて大伯父の墓参に赴くときは、大抵この緩やかな坂を上っていった。健康のためです、などと嘯いていたが、本当の目的は別かもしれない。この木々に囲まれた静かな歩道を往くうちに、自然と心が厳かなものに作り替えられていく、その過程が山岡には大事だったのだろう。
そして、俺にとっても。
上り坂は長く、病み上がりの園村を気遣う歩みは緩慢なものだ。途中で休憩を挟むことまで考えれば、無言の道程は居心地が悪い。かといって会話で園村に負担をかけるのも忍びない。
「……大伯父は、御影町に住んでいた」
俺は山岡と大伯父と、それから俺のことを話すことにした。園村も半分くらいは興味があるだろうし、山岡の墓参りをしたいと言った園村にそれを聞いてもらうことは、今日の俺の責務だとも思えた。
大正が終わる年に生まれた大伯父は、俺の祖父の兄にあたる。
南条の家督を継ぐべき本家の長男だったが、何を思ったか大学を卒業してすぐ、始まったばかりの大戦に志願して戦地へ赴き、それきりだったという。当然本家は当主候補が戦死したものだと理解し、終戦の一年後に次男である俺の祖父が妻を迎えて家督を継いだ。そしてその一年後には俺の父が生まれ、とりあえず南条の家も安泰だろう――という矢先に、大伯父が復員してきたのだった。
誰もかれも混乱したに違いない。が、当の本人は呵呵大笑して「そうなってしまったものは仕方がない。お前が継いだのなら、お前が南条の当主だ」と、あっさり納得したという。それで南条の家も、決まってしまったことはもう仕方のないことだし、今更当主交代なんて外聞も悪いことだと、祖父の当主業は続行することとなった。元から変わり者だったらしく、当主という立場には全く何の未練もなかったようだと、当時を知る人は語っていたらしい。
大伯父は東京の本家を離れ、御影町の別邸に移り住んだ。今の自分は使用人を使えるような人間ではないからと本家の申し出を固辞した大伯父が、唯一随伴させたのが山岡だった。
「俺も詳しいことは聞かずじまいだったが、山岡とは戦地からの付き合いらしい」
戦時中のことは、二人とも多くを語りたがらなかった。俺には想像もつかないような艱難辛苦を味わったに違いないし、殊更苦しい思いをさせてまで聞き出そうとは思えなかった。ただ、山岡と同じ船で復員した大伯父は「帰る場所もない」という山岡を半ば無理矢理連れてきたという。それだけは山岡が、穏やかに笑いながら語って聞かせてくれたことだった。それまでのことは別としても、居場所のようなものを得たことは山岡にとって幸福だっただろうことは、容易に推測できた。
ともかくそうして山岡は、御影南条邸で住み込みの執事として働くこととなった。執事としての礼儀作法などは大伯父から叩き込まれたのだと言う。しばらくは大学時代の知己から翻訳の仕事を回してもらいながら生計を立てていた大伯父も、戦後の復興の中で勤め人となった。一旦は財閥解体の憂き目にあった南条も、特需の追い風を得て再びその名を広めている折でもあった。南条商事の役員に名を連ねたころには、御影南条邸にも使用人の姿が増えており、彼らを束ねる山岡の姿もあったという。
「……御影町のお屋敷って、南条君の本家……というか実家?じゃなかったんだ」
園村が意外そうな声で尋ねる。息は上がっていないが、話の中身が気がかりそうな表情を見て、俺は歩みを止めた。
「ああ。俺の生家は東京にある。両親もそこが生活の拠点だな」
「それじゃあ、山岡さんはもともと南条君の執事さんじゃなかったんだ?」
そのとおり。と、いう一言で済ますつもりはなかったが、園村の目にも興味の色が浮かんでいた。
俺は少し先の木陰を指さす。簡易的なものだが、小さなベンチが据えられている。並んで腰かけると、市街地の遠景が見えた。御影町はどのあたりだろうか。
「まあ、それにはいろいろと事情があってだな……」
俺が小学校に入学した年、きな臭い出来事が近辺で頻発した。財閥重役に対する脅迫や、その子女を含む家族の誘拐未遂事件。特定の思想に基づく連続事件かと思いきや、模倣犯のような無差別の事案も発生し逮捕者も複数出たらしい。そのような状況だったので俺の両親もまた息子の身辺を気にしてはいたが、警護を増やすのではなく、より安全だろう隣県の御影町に住まわせることにした……のだと聞く。
今の俺ならその判断が間違っているなどとは思わない。ただ、まだ六歳か七歳の、ほとんど幼稚園児のような時期に親元から引き離され、大伯父という、ろくに会ったこともなければ存在すら知らなかった老人と同じ家で暮らせと言われれば泣きもするし癇癪も起こす。それでも、どんなに泣いて喚いても、両親に会いたいという俺の望みは叶えられず、結果として父母に対する大いなる不信感だけがしっかりと刻まれていった。
大伯父が優しかったのは幸いだった。それに、俺をよくかわいがってくれた、亡くなった祖父に似ていたので、俺が御影南条邸での暮らしに慣れるまで時間はかからなかった。
そして俺が御影町に滞在している間、世話をしてくれたのが他ならぬ山岡だった。そのときすでに還暦を迎えていた山岡だったが、実家の使用人の誰よりも俺のことを理解していたように感じられた。実家の方は使用人の入れ替わりも多く、長く勤めている住み込みの使用人は家宰であって、俺の教育係やいわゆるシッターではなかった。当時の俺は専属の従僕(valet)が付くにはまだ幼かったので当然だ。それが御影町に移ってからというもの、山岡は起床から就寝まで甲斐甲斐しく俺のそばに付き従った。なにせ子供だったので、俺にとって山岡は執事や従僕と言うよりも、親代わりのようなものだった。大伯父ももちろん優しかったし、食事を共にすることもあったが、子供にはよくわからない所用で留守にすることも多かったので、やはり圧倒的に、山岡と過ごす時間の方が長かった。
御影の南条邸で過ごしたのは半年ほどだったように思う。春が近づいたころ、実家のほうもずいぶんと落ち付いたので両親は息子を呼び戻そうとした。しかし「やまおかもいっしょにかえる」と言いだすのは、両親とて予想外だったに違いない。当の山岡本人も、そして雇い主の大伯父も。
結論から言うと、大伯父は俺のわがままを快諾してくれた。大伯父にとっても山岡は重要な使用人だっただろうに、なぜそうまでしてくれたのか、歳を重ねるにつれて理解が難しくなっていった。俺が両親から受け取れなかった即物的な愛情を、山岡に求めていたことなどわかっていただろうから、同情的な気持ちがあったのかもしれない。中学の頃にはそう結論付けていたが、あの思慮深い老人は大局的なところから物事を見ていたから、もっと別の理由があるのかもしれない――と、今は考えている。俺がそれを知りうる日は来るのだろうか。
結果として俺は山岡を信頼し、山岡は俺の信頼に応え続けた。半面、両親とは反目し合ったままだった。反目というより、不信感から父母よりも山岡を慕う息子を扱いかねていたのかもしれない。関係を修復しようという意志が全く感じられなかったわけではないが、いずれにせよ、仕事で不在にしていることのほうが多い両親との溝は年々深まるばかりだった。
おそらくは山岡がいてくれたから、俺は両親との不仲をそこまで深刻に考えずに済んだのだと思う。山岡が亡くなって初めて、俺は両親との十年来のことをじっくりと思い返すようになった。もしも山岡が東京に来なかったら、俺と両親は今よりも不仲だっただろうか。それとも、どこかで関係修復に成功していただろうか。
考えても詮無いことだ。
「……今気づいたが、俺と園村は少し似ているな」
「え?」
俺の方を振り返った園村の顔に木漏れ日が落ちていた。表情は驚きに満ちている。
多忙な親の愛情を疑ってしまい、関係が悪化したところが似ている。そう言うと、園村が小さく何度か頷いた。
「そう言われると、そうだね。……まさか南条君と共通点があるなんて、想像しなかったなあ」
感慨深そうな園村に小さく笑ってしまう。気持ちはわからなくはない。
園村は続けた。
「けど、私達だけじゃないのかも。そういう親子って、世界のどこにでもいるのかもしれないね」
珍しいものでもない、ありふれた関係だ。園村はそう結論づけているらしい。
「ああ……そう、かもしれんな」
そうかもしれない、という思いは、俺の心を少し軽くした。親に顧みられることのない俺という子供は、長い年月をかけて染みついた偏執は、ただの幻だったのかと、そう思わせるものだった。
「大人になるにつれて、親の気持ちがわかるようになるのかな」
春霞の空を見上げながら、園村は笑う。
「あ、そうしたら、城戸君は大人ってことになるのかな?」
それはうなずける話だった。
「少なくとも稲葉よりは大人だろうな」
「あはは……」
園村と同じ種類の苦笑が口元に浮かぶ。俺はその稲葉よりも、幼いのかもしれない、と感じて。
しかし両親も似たようなものかもしれない。向き合おうとしなかったのは、互いを遠ざけようとしたのは、俺だけではなかったから。
「……俺がエルミンに入学しようと思ったのは、親が帰ってこない家を出たかったから、だと思う」
ほかにも理由があったかもしれないが、忘れてしまったのはそれがくだらないからだろう。
聖エルミン学園については中学の同級生から聞いた。所在地が御影町という事実が、半分以上は決め手だった。御影町の邸の主、大伯父はすでに他界していた。山岡とともに月命日の墓参のたびに、俺たちはあの屋敷にも立ち寄った。主を亡くしてもまだ数人の使用人たちがそこで働いていた。長く住み込みで働いていた者たちは、ここ以外で働こうとは思えないと言い、庭の手入れや相続財産の整理を続けていた。
もしも俺が聖エルミン学園に入学出来たら御影の南条邸から通いたい。そうすれば彼らも向こう三年は仕事を続けられるのではないか? という、なんとも浅はかな算段だった。
腹は決まったが、その年の年末年始も、両親は日本にすら戻らなかった。俺は両親の滞在先まで国際電話をかけて、受験のことを切り出した。しんしんと雪の降る早朝のことだった。山岡にこれでもかと言うほど厚着させられて、受話器を持つ手に汗がにじんでいたことをよく覚えている。
うまく話せたのかどうか、今でも確かではない。父は少ない相槌を挟みながら俺の話を聞いていた。当時はそれを、あまり関心がないように感じたのだと思う。話が終わりに近づくにつれ、俺は自分の望みが叶えられないことを受け入れようとし始めていた。
しかし――
「だったら圭、お前は御影町の邸を、あの家の当主として切り盛りしなさい。山岡は連れて行ってもいいが、本家の使用人は誰一人として連れて行ってはならん。あちらの使用人はまだ何人か残っているだろうから、彼らを使ってみせなさい。
聖エルミン学園への入学は好きにしたらいい」
好きにしたらいい、という言葉の衝撃で、俺はなんと答えたらよいのかわからず、父が最後に「わかったか?」と念押ししたのに「はい」と答えるしかできなかった。山岡は指先一つ動かさず、部屋の隅に立っていた。聞いた話を復唱するように伝えると、山岡はまるで最初から分かっていたように目尻を下げた。
「さようでございますか。旦那様のお許しが出てようございました。御影の南条邸のことは山岡が差配してまいります。ぼっちゃまはまず、聖エルミン学園の入学願書をご準備なさいませ」
山岡は一礼すると、厚い絨毯を静かに踏みしめて部屋の外へと退出した。俺は何も言わずにそれを見送る。別に、父と山岡が通じていたとは思わない。山岡は山岡なりに、父のことを把握していたのだろうと、今になれば推測もつく。息子の要望を無下にするほど頑迷でもなく、南条の当主として、次代を育て上げる責務と意志があることくらい、山岡はお見通しだったに違いない。
もしかしたら大伯父に仕えていたころに似たようなことがあったのだろうか、とも考えたが、大伯父は生涯伴侶を持たず、子供もいなかった。(だから、俺のことを「ゆくりない孫」と呼んでかわいがってくれたのだと思う。)
「じゃあ南条君、あのお屋敷の「ご主人様」なんだ……⁉」
「ご主人とは呼ばれないが、まあ邸の主ではある」
結果論ではあるが、山岡の葬儀やらその後の手続きやらを俺が率先して指揮できたのは、邸の主という立場があってこそだったので、押し付けられた役目だとしてもそれだけはよかったのだと思う。
ちなみに呼び方といえば、以前からの使用人たちは俺を「旦那様」と呼んでいる。役柄が人を作るという話ではないが、そう呼ばれることによって責任感が伴ったのは事実だ。俺をいつまでも「ぼっちゃま」と呼んだ山岡の前で甘えが出たのも、つまりはその裏返しなのかもしれない。
「ぼっちゃまなんて呼んでいたのは山岡だけだったな、後にも先にも」
実家にいたころは「圭様」と呼ばれていたし、父の元から派遣されている松岡もそうだ。言うと、園村は眩しそうに目を細めた。
「そっかあ、なんだか特別な感じがしていいね」
特別。
その響きは、いろいろな意味を伴って俺の胸中に落ち着いた。
「そうだな。山岡は俺の親ではなかったが、父や母では果たせない役割を果たしてくれたのだと信じている。……それに、山岡では果たせない役割も、父や母にはあるのだろう。今はそう思えるようになった」
不仲が解消したわけではないが、思うところが少しずつ変わりつつある、それは事実だった。いつか山岡の墓前にそれを報告できる日が訪れるのだろうか。
街の遠景が雲に翳る。話し込んでいるうちに、ずいぶん時間が経ったらしい。
「そろそろ行くか。あまりのんびりしていると日が暮れてしまうな」
俺は立ち上がり、園村を促した。霊園までの道は、ゆるく曲がりながら続いている。
葬儀の日、真新しい山岡の墓は霊園の中で目立っていたような気がしたが、今訪れてみればその印象は薄れているように思えた。
霊園は広く、翳った白い墓石がどこまでも敷き詰められている。雪の朝のようだと思った。音はすべて、白い光景に吸い尽くされているようだった。
大伯父の墓の隣に、山岡の名を刻んだ墓石がある。園村はそっと身を屈めて白い小さな花束をささげた。
「エルミンはせっかく礼拝の時間もあるんだから、お祈りの言葉くらい、覚えておけばよかったな」
惜しむように園村が目を伏せる。形式的なものなど、どれだけあったところで意味はないだろう。俺はそう言いかけた口を閉じた。数千年の時を語り継がれた言葉は、幾億幾万の人の思いをゆるした言葉は、実を伴わないものとは思えなかった。
裾が汚れるのもいとわず、園村は膝をついて両手を組んだ。礼拝の時間に見られる祈り。いや、これはまるで、贖罪のための懺悔だった。
園村は目を閉じ、無言のままだった。
その姿を見下ろす俺の胸中に、苦々しい思いが満ちていく。苛立ちと言ってもいい。園村に対してだけではない。半分くらいは俺自身に対するものだ。
「園村」
たまりかねて、声をかけてしまう。
「お前を気遣うつもりもないし、むしろこれは、お前を侮辱し不愉快にさせるかもしれん。だがそれでも言わせてもらう」
園村は膝をついたまま俺を見上げた。まっすぐな目で、俺に向かって頷いてみせる。
「これに一体、何の意味がある」
自分でも予想しなかったほどに、掠れた声だった。園村は表情を変えない。ただ、一瞬だけ両目が苦しそうに細められそうになった、ように見えた。その仕草に勢いを削がれそうになりながら、俺は続ける。続けなければならなかった。吐いた唾は呑めぬのだから。
「山岡も、その刑事も、二人が死んだのはお前のせいじゃない。あの事件は、お前がある意味ではきっかけではあったかもしれない。だがそれでも、お前に責任はない。俺はそう思う」
しかし本当に「園村はあの事件の被害者でしかない」とだけ考えているなら、こんな言葉は出なかったのではないか。俺自身が無意識にそう考えていなければ、それを否定する言葉だって思い浮かびもしないはずだ。俺は友人を励まそうとしているのか、糾弾しようとしているのか、自分でも判じることができなかった。いっそ園村が「どうしてそんなことを言うのか」と詰ってくれた方が気は楽だった。だというのに――
なのに、お前のその態度はなんだ。どうして「自分が悪かった」とでも言いたげな態度をとる。
「慰めようと思って言っているわけじゃない。お前には、いや、人の身には背負いきれるものではないものを、無理に背負って何になる?」
口の中に熱く苦いものが広がっていくような気がした。俺が真実責めているのは誰なのだろう。いや、誰も責められはしないし、責任を負うこともできないのではないか。
そうだ、背負えるものか、背負えるものならば俺が、せめて俺が――
「そうだね」
立ち上がり、膝を払う園村は表情を変えない。冷淡なのではない、多分表情を変えようとしたら、堪えているものが溢れてしまうから、懸命にこらえているだけなのだ。俺と、同じように。
「もしかしたらそうじゃないかなって思ってたけど、今の南条君の顔を見て、そうだと思った。南条くんも、私と同じだね。きっと考えてたんでしょう? あの日病院に山岡さんが来なかったら、自分が病院に行かなければ、もしかしたら――って」
園村の言葉は俺を抉った。
あの日俺が病院に行かなければ、ペルソナ様なんてしなければ、山岡を先に帰らせていれば、俺だけでもかかりつけの別の病院に行っていれば――
山岡は今もこの世界で、あたたかい日差しの中で、俺に笑いかけたのではないか。
「否定はしない」
園村に向けていた視線を、足元に落とす。気勢はとうに削がれていた。
「だから俺は、お前にこうまで強く言っていいのか、わからん……。責めを負うべきはお前ではなく、俺の方ではないのか。山岡の主人だったくせに、俺の落ち度で山岡を死なせてしまったのではないか。不意にそんな考えが、浮かんでしまうのを否定できん」
普段は考えまいとしていることでもあったから、俺はこのときはじめて、自責の念を直視したのかもしれない。あるいは、あれから時間が経ったからこそ悪念が俺を蝕み始めたのだろうか。
「わたしもわからない。わたし自身が、あの事件に対してどう向き合ったらいいのかわからない。でもね、南条君、わたしが山岡さんのお墓参りに行きたいと思ったのは、そんな背負いきれない責任感のせいなんかじゃないよ。そう、思ってるよ……」
園村の言葉は祈りのようだった。
「南条君が大切に思っていた山岡さんのことを知りたかったから。どんな人だったのか、私は覚えておきたかったから」
誰かに許しを乞うでもなく、自分がそう在りたいと願う切なる心の表れだった。まなざしは強く前を向いている。責任を感じようとするでもなく、そこから逃れようとするでもない、ただありのままに受け止めた事実を深く思索したいという意志がそこにあった。
「――すまなかった」
圧倒されたのかもしれない。
「俺も背負いきれない責任を勝手に感じて、押しつぶされそうになっていた」
思わず額を覆ってしまう俺に、園村は首を横に振る。
「気持ち、わかるよ。……楽だもんね、自分は悪くないって言うより、自分が悪かったんだって思うほうが、ずっと楽だもんね……」
先ほどとは打って変わった心細そうな声色に同意する。
自責の念に苛まれるのは簡単だ。それは自分に責任などないと逃れるより、ずっと卑怯なことだと言われるかもしれない。思考停止した愚か者のすることだと咎められることかもしれない。しかし自分は悪くないと自己弁護するのも、本来負うべき責任からの逃避でしかないのでは?
俺と園村はおそらく、そういう葛藤に苛まれていたのだろう。もし俺が当事者でもない他人だったなら、こう言ったはずだ。「馬鹿馬鹿しい、答えのない自問自答など大いなる時間の浪費だ」と。尊大に胸を張って、相手の苦しみには配慮などせずに。
「でも、一人じゃなくてよかった」
ぽつりと、そんな言葉が聞こえて、俺はひっそりと同意した。こんな弱音を口に出したとき、「考えすぎだ」「自分を責めるな」と否定するだけでなく、この入り乱れた感情に共感できる友がいてくれることは幸いだった。おそらくは刑事の墓参りをした園村に、稲葉は励ますような言葉をかけたのだろう。それはそれで尊いことで、稲葉の厚意は的外れでもないし無下にできるものでもない。
ただ――山岡にしか果たせぬ役割、父母にしか果たせぬ役割、そういうものがあるのと同じように、俺たち二人が互いにしか担えない役割というのもあるのだと自然に理解できた。
風が吹き抜ける。遠くで梢が揺らぐ音がする。少し肌寒いのは日暮れが近づいているせいだろう。
そろそろ戻るか。言うと、園村は頷き、もう一度墓前に手を合わせた。
「下まで歩くことになるが、体調はどうだ。無理なら、松岡に車をここまで回してもらうが」
霊園の門をくぐりながら問うが、園村の顔色は悪くはないように思える。
「ううん、平気。それにこの道、景色もいいから歩くのは大変じゃないよ」
なかなか来ない場所でもあるので新鮮だったらしい。
「上ってくるとき、なんだか天国への階段を上ってるみたいだな、って思ってた」
その言葉は、深く響いた。山岡と二人で歩きながら感じていたあの、厳かなものに近づくような畏敬の念をよく言い表しているように感じられた。だとしたら道を下るのは楽園追放といったところか。口には出さず、胸の内に留める。
だまったまま坂を下っていると、園村の口が何事かを紡ぎ始めた。
おさない記憶 しろいあやまち
水と星とが ながれてそよぎ
光と灰とが さかしまにふる
それは楽園の扉
あなたの涙と真実を奪い
あなたに夢と永遠を与える
それは楽園の扉
ひらかれるときを待つ
あなたのための終のゆりかご
文章というより、詩の一節のようだったが、俺には覚えのないものだった。
隣を歩きつつ耳を傾けていた俺は、それが一区切りのように止んだところで問いかける。
「なんだ、それは?」
「大好きな本。何度も読んで、そこだけ覚えちゃったの」
はにかむように笑う園村
「楽園の扉、って本」
タイトルには聞き覚えがあった。姫野と貸し借りしていた本か、と確認すると、園村は頷く。どんな話なのかと尋ねてみれば、ストーリーなどほとんどない、言葉と絵がつづられた絵本のような児童書のような、とにかくそういうものらしい。ならば美術部の園村のことだから、大方絵を眺めるほうが多かったのでは。そう勘ぐってみるが、文章を諳んじているくらいなのでやはり何度も何度も繰り返し読んだ、気に入りの本というところか。
「もしも楽園が天国だとしたら、神の国だとしたら、どうして扉があるんだろう」
不意に昏い声で園村が立ち止まる。
扉。楽園の扉。
扉には開閉の機能があり、それは内と外を隔てるためだ。隔てる理由はこの場合明確で、内に入る資格――のようなもの――を持たないものを排除するためだ。
だとしたら、楽園の扉というものは、言葉に反して無慈悲な装置かもしれない。園村は、そう言っているようだ。
「天国へ行ける人は、扉なんて見えないのかもしれない。もしかしたら天国の扉は、そこに行けない人のためだけにあるのかもしれない」
理屈としては、それは納得できるものだと思えた。否定するだけの論拠を出せないのがもどかしく、天国へ行けないと思っているのかと問いただす度胸のない自分が歯がゆかった。
「私は、叩き続けなきゃいけないのかな、天国の扉を」
だとしたら、俺もそうだろう。いや、俺は扉の前に立ったとき、果たしてそれを叩けるだろうか。その中に迎えられたとして、胸を張って会うことができるだろうか。
砂を踏む緩慢な足音が一つ泊まる。
「あ……ねえ、南条君は覚えてる?」
「何をだ?」
振り返った園村の顔には、予想したほどの気鬱はなかった。
「入学してすぐの礼拝の時間にきいた、聖書の話」
「いや……」
礼拝は毎週の恒例なので聖書の話も頻繁に聞いているはずだが、頻繁だからこそ正直話の中身はほとんど覚えていない。
「どういう話だ?」
聞けば思いだすというわけでもないのだが、とにかく尋ねてみる。
「天国は、神の国は、特定の場所に、目に見える形であるわけじゃない。神の国は、人の心の中に確かにあるものだ、って話」
やはり、記憶にはなかった。そのときの俺はこれを聞いても別に何とも感じなかったのだろう。今とは違って。
「だとしたら、もしも天国の扉が閉じられていても、それはいつか、私が私のために開くことができるのかもしれない。今はどうしたらいいのかわからないけれど、私が私を……なんて言ったらいいのかな……みとめたり、ゆるしたり、そういうことができたら、私の中の楽園の扉はきっと開く気がする」
言い聞かせるような言葉を口にしながら、園村の表情はだんだんと晴れやかなものに変わっていった――気がした。それは園村の言葉によって、俺もまた同じように、ある種の希望を見たからかもしれない。
「……なんか、恥ずかしいこと言ったよね、私……」
当の本人は両手で顔を覆って後悔しているようだが。
「いや、そうは思わなかった。恥ずべきことでもないだろう」
そう言ったにもかかわらず、園村はなお顔を赤くしている。むしろ俺の言葉のせいでいっそう気まずそうな顔になったようだが。
ともかく。
「神の国が人の内にあるというのは、そう荒唐無稽な話でもないと思う」
理解に苦しむ所作は無視して、俺はそう続けた。園村の話を聞きながら、俺は「どうして、俺が山岡の姿をしたものを、俺のペルソナとして呼び出せたのだろうか」という疑問への答えを得た気がしていたからだ。もしも神の国が俺の意識の内にあるのならば、そこに山岡がいても何の不思議はない。人の内なる神の国に在って、人を律し人を見守るもの、それは俺にとっては、亡きあの姿に他ならないのだから。
そういえば再び見えた山岡の姿はまるで御使いのようだった。奇しくも園村の説を補強するようで、笑みがこぼれる。
「扉はそう遠からず、開くんじゃないか」
「……ありがとう」
俺は俺の祈りのためにそう言ったに過ぎないが、律儀な園村は謝辞を述べている。礼を言われるほどではないと固辞するものでもない気がして、俺は何も言わずに坂を下り始めた。
ふと目を向ければ春の陽が山の端に落ちていくところだった。稜線が赤く染まり、街は淡い紫の色に沈んでいく。いつかこの光景を、山岡と見たことを思い出す。そして今日もまた、あるいはこの先もずっと、俺は山岡とこの美しい世界を眺めるのだろう。いつか、楽園の扉に迎えられるまで。