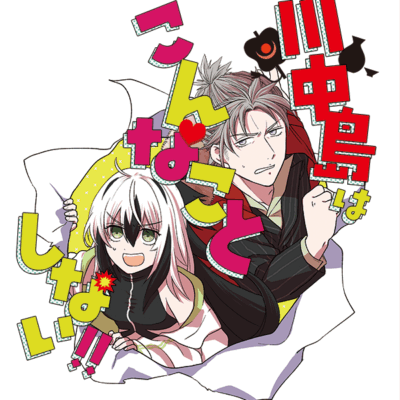かつては肩をならべて
「はあ、そうすると先生方、まるで天皇陛下のようですなあ」
しみじみと感慨深い、と言いたげな感心がその言葉の中にはあった。天皇のようだ、と、言われた方の俺は、まったくなんのことなのかわからずに「はい?」と裏返った声を返してしまう。相談者のじいさんは「ああ、失礼しました」と、本当にそう思っているのかわからない顔で笑っている。
「亀山先生、村上先生、どちらも天皇の諡と同じですから」
「――ああ、そういうことですか」
亀山というのは俺のことで、村上は去年迎えた新入りのことだ。確かに亀山天皇、村上天皇、日本史の教科書で見た記憶がある。同じタイミングで村上も理解したらしく「ああ~!なるほど~!」と、学生気分の抜けない明るい声を上げたので、じいさんは満足そうに笑っていた。
法律相談のために弁護士事務所を訪れる人間にしては、じいさんは朗らかだった。相談内容がトラブルがらみというわけではなく、今後の財産管理と遺言作成に関するものだからだろうか。
平坂区の雑居ビルに事務所を構えて三年になるが、大抵の相談は今のような牧歌的なものだ。当然そんな相談事はメインの収入源にはならないので、保険会社から回ってくる仕事でなんとか食っていける状態が続いている。青葉区の大手事務所や港南区の小綺麗な事務所に比べると古臭い上に、カメヤ横丁の片隅なんて立地もデメリットばかりのようだが、俺はこの場所が比較的気に入っていた。
雑談を挟みながらの相談が終了し依頼人が帰ると、村上弁護士が思い出したように笑う。
「亀山先生とセットだとロイヤルになれるんですね~」
「何がロイヤルだよ、たまたまだろ」
そんなにおかしいだろうか、と、苦笑していると、湯呑を下げに来た事務員が割って入ってくる。
「ちょっと、先生方だけじゃないですよ、私も!」
私も、と言う彼女の苗字を村上が笑い交じりに読み上げた。
「白川さん! ほんとだ!」
してやったり、とばかりに口の端を上げている白川さんは得意気だが、正直それは、惜しいのでは? 天皇の方は確か、白河じゃなかったか。「カワ違いでしょ」と指摘すると、
「そんなの誤差の範囲ですよ、大体ほんまもんが揃ってたらちょっと恐れ多いと思いません?」
だから丁度いいんですぅ、と、白川さんは結論付けて給湯室へと洗い物に入っていった。村上はロイヤルネームが三人揃った(揃ってはいないのだが)のがツボに入ったのかまだ笑っている。
「お前何がおかしいんだよ」
「えっへへ、あは、ごめんなさい」
ようやく落ち着いたかと思うと、また噴き出す。
「今度は何だよ」
「いや、今の会話、しらいしでやってたら絶対おばちゃん入って来たよねって思って。『アタシのご先祖ねぇ、ほんとは時の帝のご落胤だったのよぉ~』とか言いそうじゃないですか?」
「……」
わからんでもないのが困る。
カメヤ横丁の顔役、あるいは名物と言っても過言ではないのが、ラーメンしらいしの店主、通称「しらいしのおばちゃん」だ。自称「元女スパイ」「ロマノフ王朝の末裔」、それから「ラーメン屋は世を忍ぶ仮の姿で、実は某国の特務調査員」なんてのもあった。当然冗談の類に決まっているのだが、語り口が妙にそれっぽいので得体の知れない真実味がある。飲んだ後、〆の一杯を楽しみながら聞く与太としてはかなり上等なもんだろう。
ちなみに俺が事務所を開いてすぐのころ、挨拶がてら訪問した際の一言が「カメヤマさん? ああ、だからカメヤ横丁選んだの」というものだった。疑問文ですらなかったので、おばちゃんの中では俺が駄洒落で事務所開設場所を選んだことになっているに違いないし、常連の耳には事実として伝わっているのかもしれない。もはやどうでもいいのだが。
ともかく、しらいしのおばちゃんは、そういう人物なのだ。この場にいたならきっと話に乗ってくる。一番乗り気になると思う。
「言いそうだな」
「でしょー?」
村上が誇らしげなのは理解できないが。
それで話は終わったかと思ったのに、わけのわからん村上はしつこい。
「でもすごくないですか? こうなったらもう一人くらいロイヤル弁護士入れましょうよ!」
「なにがロイヤルだよ、大体人増やすほど仕事ねえぞ」
「え~じゃあ入れる入れないは別にして、亀山先生のお知り合いとかにいません? ロイヤルな人。えーと、醍醐とか? 天武とかはないですよねえ……人の苗字でありそうな……う~ん」
村上が声に出してうんうん唸っているので、俺までつられて考えてしまう。醍醐はありそうだけど後醍醐はさすがにないよな、そもそも俺は天皇の名前自体そんなに詳しくない。それは村上も同じだったようで、インターネットでなにやら検索している。仕事もせずにこれだったらさすがに咎めるが、村上は仕事の出来については文句の付けようがないので、しばらくは好きにさせる。
「あ、あった。えー……と……あ、三条とかどうです? 花山、カザンじゃなくてハナヤマさんならいそうですよね。あとは~……朱雀? 亀山先生、朱雀って苗字あると思います?」
「知らん」
「えー? ほかにないかなぁ……」
俺が無視して書面の作成に戻っても、村上はくだらない「調査」を続けるつもりらしい。腕時計をちらと確認すると、時刻は三時の五分前だった。あと五分は大目に見てやろう。どうも相手が若い女子だと強く出られないので、調子が狂いそうだった。
「村上先生、清和さんとか、どうです?」
まさかの援軍、白川さん。三人分の湯呑を盆に載せて給湯室から出てきたと思ったら、あろうことか村上に入れ知恵している。
「……」
無言で湯呑を受け取るのは俺のささやかな抵抗だった。そうこうするうちに二人はヒートアップして、次から次に苗字を投げかける。宇多、堀河、二条、一条、六条、鳥羽、高倉……こうして並べられると、案外天皇の名だった苗字というのは多いことに気づかされるが、特に学びを得たとは思わなかった。話半分に聞いていた俺は油断していたのかもしれない。
「亀山先生! 伏見!」
「いない」
「えー? 花園はどうです?」
「いない」
「じゃあ……嵯峨!」
その名前を聞いた一瞬、胃の腑が浮いたような錯覚を覚えた。
「――いや、いない」
なんとか答えた俺を、村上が見ている。不自然さに気づかれたのかとひるんだが、そういうわけではなかったらしい。
「なかなかいないですね~……亀山先生、検事時代の人でもいいんですけど」
「……お前、この事務所をどうしたいんだよ」
「え~? 亀山・村上法律事務所にもう一人天皇の名前が並んだら単純におもしろくないですか? わかる人にはわかるインパクト大! ですよ?」
「……バカヤロウ」
イロモノ事務所じゃねえんだぞ、とだけ釘を刺して、俺は再び書面と向き合う。村上もいい加減飽きたのだろう。パソコンの前から移動すると、案件ファイルの棚へと向かっていった。文章は思い浮かばず、すでに文字になった情報も意識の上を滑っていく。
先ほどの村上の、若さゆえのまっすぐな目が俺に過去を思い出させる。嘘はついていない。嵯峨なんて弁護士の知り合いは、俺にはいない。
あいつは、最期まで検察官だった。ヤツ自身の信じる正義をまっとうし、検察官として死んだと聞いた。
俺が知っているのは、ただそれだけだ。
(了)
桜の園に降る
無医村と呼ばれる過疎地域への赴任を終え、東京の母校に戻った私を待っていたのは信じがたい現実だった。
「――徳永先生、ですか? 助教授……?」
研修医時代から世話になっていた助教授の名前が医局のどこにも見当たらないので、秘書に尋ねたその時点で少し嫌な予感はした。徳永、という名前自体聞き覚えがなさそうな顔だったからだ。いくらなんでも、二十歳そこそこの新人だとしても、助教授の肩書を持つ人の名前に覚えがないというのはあり得ない。しかし私は、そのあり得ない可能性を願った。徳永先生がいないよりは、私にあてがわれた秘書の資質に問題があるというほうがまだマシだった。
しかしその数十分後、秘書が人事担当に問い合わせた結果を耳にして私は愕然とした。
「徳永助教授は2年前に退官されています。それと……医師会に問い合わせたのですが、届出がなされていません」
どうやら私の秘書は有能らしい。言ってもいないのに医師会への問い合わせまでしてくれたのは、彼女なりに徳永先生の行方を調べようとしてくれたのだろう。だが、届出がない……つまり徳永先生は、今現在、医師として働いていないのかもしれない。退官しているにしても、その後どこかで開業しているのではないか、そんな希望すら、あっけなく打ち砕かれてしまった。
何も言えずに立ち尽くすばかりの私に、さらなる追い打ちがかけられる。
「あの……それと……徳永先生が退官された事情ですが――」
§
十日後、有給休暇を取った私は新幹線で珠閒瑠市へと向かった。在来線でも事足りるほどの距離だったが、逸る気持ちがそうさせたのだろう。到着した新夢崎駅から在来線へ乗り換え、私は目的地を目指した。正円の形をした珠閒瑠市を分断するように流れる川は、七夕川と言うらしい。鉄橋を渡る最中、大きな標識が目に入った。東蓮華台駅からは、市バスに乗り換えて最終目的地を目指す。別にタクシーを使ってもよかったが、駅前のロータリーで煙草をふかしている白手袋の運転手たちは意図的に無視した。新幹線を使っておきながら、まどろっこしい交通手段を選んでしまうのは……やはり、躊躇しているからだろうか。
繁華街らしい夢崎区とは違って、中央区の蓮華台という地域は落ち着いた街並みだった。バスターミナルと隣接している商業ビルもあるが、蓮華台の大半は住宅街だった。おそらくかつては珠閒瑠城の城下町だったのだろう。
私が目指しているのも、その珠閒瑠城があった場所だった。今は本丸公園と名を変え、地域住民の憩いの場になっている。
徳永先生の所在について調査を依頼した探偵から受けた報告は私を混乱させた。
「ホームレス、って言うんですかね。今は公園で根無し草みたいな暮らしをしているようですよ」
時折日銭を稼ぐために日雇いの現場に顔を出してはいるらしいが、大半はこの公園でぼんやりと過ごしているらしい。つまりは定職にもつかず、住居すらないのか。
愕然とした。かつては最高学府の医局に在籍し、ゆくゆくは外科部長となることを約束されたような人が、なぜ――
探偵から渡された写真の徳永先生の顔には、覇気が感じられなかった。穏やかな表情などとはとても言えない、諦念が色濃く感じられる暗い顔だった。
信じられない、確かめなければならない、そう思ってここまでやってきたのに、本丸公園の入り口で、私はしばし立ち止まっていた。傍らを子供たちが駆け抜けていく気配も、ベビーカーを押した女性たちから不審の目を向けられているのも感じ取っていた。
私は果たして本当に、ここに足を踏み入れるべきなのだろうか。かつて尊敬した人の姿を目の当たりにしてショックを受けずにいる自信はない。何も見ず確かめず、知らぬふりをして生きていくほうがいいのではないか、電車の中でもバスの中でも考えたことだった。それでも、探偵の言ったことが間違いである可能性を、万に一つもないだろう希望を、諦めることができなかった。何も確かめずには、私は私の日常へ戻ることも、これからの医師生活を続けることもできないと思った。
足を踏み入れた公園の中では、散り始めた桜の木々が風に静かに揺れていた。
春の午後、日差しは穏やかにすべてを照らしている。遊具で遊ぶ子供たち、それを見守る親の姿、仕事の途中なのかベンチで一服している男性、学校をサボっているらしい制服姿の女子学生。
(徳永先生――)
ありふれた光景の中で彼の姿は異様だった。いや、ホームレスという存在は残念ながら今の日本ではありふれたものかもしれない。異様だと感じてしまったのは、数年前まで大学病院で辣腕を振るっていたあの人がそうなっていることを理解したくない私のささやかな抵抗なのだろう。
擦り切れて薄汚れた衣服、整えられていない不衛生な口髭、人目を避ける意図なのか目深にかぶられたサウナハットのような帽子。そこに面影など一つもない。柔和そうな印象を与えていた丸い眼鏡だけが、あのころの徳永先生のままだった。
『二年前、医療過誤事件の責任を問われて退官されました』
学内の派閥争いで特定の勢力に与しなかった徳永先生は、誰からも庇われなかったらしい――秘書の彼女が語った言葉を思い出す。徳永先生は一人きりで、誰からも見向きされていない。今も、二年前も。
目を逸らしてしまいたかったが、できなかった。その場に縫い付けられたように、手も足も動かなかった。金縛りにあったような私の身体を動かしたのは、一人の子供だった。
「あっ!」
幼稚園児くらいの子が、徳永先生の腰掛けるベンチの目の前で転倒した。私はずっと、そのベンチに腰かけている徳永先生を見ていたので転ぶ瞬間もはっきり見ていた。距離があるので断言はできないが、地面についた手が変にねじれていたような気がする。骨折の可能性があるかもしれない、思わず駆け出そうとして、一瞬動きを止めてしまった。
もし、もしも――徳永先生がまだ医者であってくれるのなら――
私と同じようにあの子の手を確かめるのではないか。
かすかな希望だった。願い、あるいは執着と言ってもいいかもしれない。目の前で泣いているこどもを放って平気な顔ができるような人であってほしくなかった。
しかし徳永先生は、黙って立ち上がると何もせず、背中を丸めてのろのろとどこかへ立ち去ってしまった。その後姿には、誇りをもって職責に当たっていた在りし日の輝きはなかった。
目の前で大きな扉が閉ざされたような、そんな幻聴を感じる。
先生、あなたは、医者としての自分まで捨てたのですか。
たまらなかった。私は走り、その肩を掴んで問い質したかった。それをしなかったのは、目の前の怪我人を優先したのは、自分が医者だという自負があるからだ。
泣いている子供の手を確かめながら、私は徳永先生を恨んだ。恨みながら、まだ希望を捨てきれずにいるのも事実だった。
先生、あなたがベンチから立ち上がるまで、ためらうような間があったように見えました。苦しそうな顔をしたようにも見えました。本当は手を差し伸べたかったんじゃないですか。医師であることを諦めていないんじゃありませんか。今のご自分が客観的にどう見えているかを考えて、あえて声をかけなかったんじゃないですか。もしかして僕がここにいることもわかっていて、任せようと思って立ち去ったんじゃないですか。そうですよね、先生、答えてください。お願いです、先生、先生――
振り返った先に彼の姿はない。ただ舞い落ちる花弁と子供の泣き声が、嵐のように何もかもを乱していた。
(了)
何もなかったようには
私の一日は、息子に花を供えることで始まり、その花を家に持ち帰ることで終わる。毎日あまたの人が行きかう夢崎区の大きな交差点の端で、私は毎朝毎晩、花を供えては手を合わせていた。
三歳だった息子が車にはねられて死亡したのは昨年の秋だった。事故当初は世間も私たちに同情的な目を向けてくれていた。犠牲者が三歳の子供だったので、二週間ほどは献花台が設置され、花だけでなくお菓子やジュースもよく供えられていた。
人の優しさに触れたようで、不幸の中でも嬉しさを感じていたのはその時期だけだったかもしれない。四十九日が過ぎると、交差点近くの商店街から献花台の撤去を告げられた。それは当然のことだと思った。厚意で献花台を作ってくれたことはありがたく、掃除やお供え物の処分を任せてしまっていたことは本心から申し訳ないと思っていた。それでも、今後も自分だけは花束を供えたいのだと申し出たところ、彼らは少しめんどうそうな顔をした。毎日夕方には回収するからと食い下がって、なんとか承諾が得られた。その日、帰宅してから、変な話だと思った。交差点は商店街の敷地内ではない。単に彼らは、商店街の近くが、枯れた花で汚されるのが嫌なのだろう。あるいは、人が死んだ証をいつまでも置かれたくはないのか。今となってはもう誰も、私達には目もくれない。
仕事に向かう前に夢崎区の交差点に花束を置き、終業後は帰宅途中にまた寄って、朝供えた花を持ち帰る。そんな生活の合間に弁護士との民事訴訟の打ち合わせを行い、刑事裁判傍聴のため裁判所へと足を運ぶ。息子を失い日常を奪われ、なにもかもを剥ぎ取られた私の人生は、そのようにして何とか回っていた。
§
珠閒瑠地方裁判所は年期が入った佇まいをしている。そういえばいつか訪れたときには建て替えだか移転だかについての公聴会が開催されていたことを思い出した。案外、なにもかもに興味を失った自分のような人間も、どうでもいいことを覚えているものだ。そう、入口には金属探知のゲートが設置されていて、古めかしい石造りの外観とのギャップがおかしくて口元が緩んだのも覚えている。しかし物珍しさに興味を引かれたのも最初の頃だけだった。ここへ何度も足を運ぶようになった今――裁判というものの当事者になった今となっては、ここも灰色の世界の一部に過ぎない。
今日、息子をはね殺した男への判決が言い渡される。それがどのような結果であっても、私の苦しみは一旦の区切りを迎えるのだろう。願わくば重い罰を受けて欲しい、例えば……その先は口に出すのがはばかられたが、それが私の願いだった。
民事訴訟の代理人を依頼した弁護士に聞くと、交通事故によって人を死に至らしめた場合、それも過失によるもので、かつ初犯の場合は罰金刑に留まる場合や執行猶予が付くこともあるらしい。
「ああ、もちろん、加害者に重大な過失がある場合は実刑判決が出る場合もあります」
とってつけたようなフォローだった。私は愕然として耳を疑った。
三歳の子供を死なせておいて、事実上罪に問われず、これまで通りの社会生活に戻れるなんて、不公平だと思った。弁護士は取り繕うように、「ご納得のいく判決だとよいのですが……」と、居心地の悪そうな表情を浮かべていた。
納得のいく判決とはなんだろうか。弁護士の話を信じるなら、どれだけ重くても刑は禁固か懲役に留まる。それで罪が償えるのだろうか。目には目を、歯には歯を、命には、命を。そうではないのか? どうして加害者は生きていられるのか? なぜ私の願うようには罰せられないのか?
わからない。なぜあの黒衣の男達には、無関係でありながら罪を裁く権限が与えられ、肉親を害された私にはそれが認められないのだろうか。馬鹿なことを考えている自覚はあるし、それは私の望む罰の重さについても同じだった。加害者が重い罪に問われることはないだろうと感づいているからこそ、それが許せなかったのだと思う。どうだろうか、結局わからない。息子を亡くして半年が経ったようだが、時間の経過すらおぼつかない私が何かを正しく認識できているとは到底思えなかった。
「主文、被告人を禁固二年に処する。この裁判確定の日から三年間、刑の執行を猶予する」
その結論を聞いた瞬間、私はこの先をどう生きたらいいのかわからなかった。背中しか見えない加害者が何を思ってうつむいたのかもわからなかった。安堵だろうか、それとも執行猶予つきの判決に喜んでいるのだろうか。あるいは犯した罪の重さに対して軽すぎる罰に、自責の念を生じているのだろうか。
そうであってほしくはない、殊勝な態度などやめてほしい、と、思ってしまった。
法律が彼を事実上許してしまった今、私まであの男を許すわけにはいかなかった。許すわけにはいかないのだ、私も。まだ憎まなければならない、誰かを恨み、呪い、そうしなければ発狂してしまうという確信があった。
視界が赤くなっていく。怒りに震えながら、それはただの錯覚か妄想だと理解する冷めた自分も感じていた。私は多分冷静だった。ここで叫んでも暴れても何の甲斐もないことはわかっていた。理解したのだ。所詮、司法などは頼るに値しない機構でしかないのだと。
§
その日も私は交差点へと足を運んだ。私が置いた花束の他に、もう一つ控えめな、小さな花束が置かれていた。
夕暮れに沈みかける繁華街に人口の灯がともっていく。人の流れはより激しくなり、私の背後では信号待ちの通行人が青に変わるのを待っている。
ざわめきの中から、私の耳がこんな会話を拾った。
「そういえば先週、平坂区で殺人事件あったじゃん」
高校生くらいの女子の声だった。
「そんなんあった? てか、それがどうかしたの?」
「あれってJOKERが犯人って噂だよ」
「それアタシも聞いた。殺されたのひき逃げ事件の犯人らしいよ! 被害者がJOKERに頼んだんじゃないの?ってバイト先の先輩が友達から聞いたんだって」
「マジ? ヤバくない?」
信号が青に変わり、電子音のメロディが緩慢に流れ出す。歩き出した人々の足音や声が流れていき、私の耳には意味のない喧噪だけが押し寄せる。別の女子高校生たちのグループが、何がおかしいのか笑いながら歩き去っていく。その甲高い笑い声がいつまでも耳に残った。
足元に残された花束は、加害者が置いていったもののように思えた。謝罪は形ばかりのものだと象徴しているようだった(私の願望に過ぎないだろうか?)。おそらくは罪も罰もそうだろう。反省してしおらしくしているのは最初だけ。権威のある誰かに許されれば、それきり罪悪感などは消えてしまったかのように振舞う。罪を量る方も罰を決める方も、条文と事実をパズルのように当てはめているだけだ。誰も私の悲しみを顧みない。誰も失われた命を悼まない。所詮自分ではない誰かに降りかかった対岸の火事に心から同情するのはお人よしでも善人でもなく、ただの愚か者にすぎないのだろう。
(そうか、殺してくれるんだ)
先ほど聞こえた会話が、頭の中でリフレインしている。
JOKERに頼んだ。
JOKERは殺してくれた。
(ああ、そのヒトは、代わりに罰してくれるのだ)
それに気づいた瞬間、安堵のあまりに涙が出そうだった。罪を正しく罰してくれる存在があることの、なんと幸いなことか。
花束だったものをかき集めて拾い、両手で握りつぶして声を上げる。歓喜、高揚、戦慄、絶望、あらゆる感情がないまぜになった叫びが、明るすぎる夜空に吸い込まれていった。
後日、検察は控訴を断念したと聞かされた。しかし私にはもう、どうでもいいことだった。
§
半月後、加害者の男は遺体で発見された。発見のニュースから身元が発表されるまで二日を要したと言うから、遺体の状態は推して図るべし、だろう。私は警察の聴取を受けたが、どう見ても形式的なものだった。ニュースや新聞でも、現場の状況から一連の猟奇殺人事件と同一犯だろうという見方が主流のようだった。
終わった。何もかもが終わった。晴れ晴れとした気持ちになるわけでもなく、何かを達成した感慨もない。未来を奪われた息子に代わって復讐をなしたという意識もあまりなかった。ただ、罪は正しく裁かれたのだという思いが、私をひたすら安堵させるだけだった。
「聞いた? JOKER呪いの噂。あれってJOKER呪いをやった人がJOKERになって、人殺ししてるんだって」
「そうなの? 俺が聞いた噂だと、JOKER呪いをした人もJOKERに殺されるって……」
最近、JOKER狩りという言葉を耳にするようになった。JOKER呪いをした人がJOKERになるとか、自分もJOKERに殺されるとか、そういう話ばかりなので、実際JOKER呪いをした人は今頃震えて眠れないのだろう、なんて笑い話まで聞こえてくる。
その話を聞いた私はと言えば――いっそ感動するほどの喜びに打ち震えていた。
これでJOKERは正しいことが証明された。彼は罪人を裁き、正しい罰を与える存在だ。
あの日私は車道に飛び出そうとする息子の手を放してしまった。もっと強く握っていたなら息子は死ななかっただろう。先日の裁判では遺族である私への配慮があったのか、私の過失についてはついぞ言及されなかった。事故現場は夢崎区だったのに、目撃者は何人もいたのに、証言が出なかったのか、出ても黙殺されたのか。だがこれでようやく私の罪も裁かれる。罪悪感に苦しまずに済む。息子を殺したのは私だ。息子をはねた男が死ななければならないなら、その原因を作った私も死ななければおかしい。オオカミのような犬の遠吠えが聴こえる。ようやく、ようやく罪が裁かれる。私は待ち焦がれていた。子供のような目で、月が満ちるのを待っている。
(了)
夢見るころを過ぎたら
父親が失職したのは俺が高三のときだった。理由は聞かされていないが、あの頃の報道を見ていれば大方予想はついた。まだ小学生だった弟ですら「父さんは悪いことをしたの?」と不安な顔をするくらいだったのだから。
母はいわゆる専業主婦だったが、父の退職の直後からパートタイマーとして雇ってくれるところを探して歩き回った。父も表向きは気丈な顔をして、再就職先で警備員として昼も夜もなく働き始めた。必死に働いたのは弟が小さかったのもあるが、一番大きな理由は俺の進学問題だったのだと思う。かつて調理師の専門学校に進みたいと言った俺に、両親は快く賛同してくれた。専門学校の学費は高額だったが、父の稼ぎでもなんとかなるだろうと笑っていた。それも遠い記憶、ほろ苦い思い出でしかない。十八歳にもなれば、自分の願望がもはや夢物語でしかないことなどすぐに理解できた。
俺は大学進学を決めた。最初は進学ではなく就職すべきだと考えたが、高卒向けの地元企業の募集も公務員試験の日程もすでに終わった後だった。どうしたらいいのだろうか、と、考えあぐねて相談に行った先の担任は、俺の家庭の事情なんてとうに理解しているだろうに、深くは尋ねることをせず単なる希望進路の変更としてあれこれ世話をしてくれた。
「成績も悪くないどころかむしろいい方だからね、いや、正直に言うと学年主任の先生なんかは、君が大学進学しないことを惜しんでいたくらいだよ。私としても進学を勧めるかな。君くらい成績がいいなら、高卒で就職するより大学を出たほうがいろんな道が開けるだろうから」
道が開ける、という婉曲な言葉だったが、多分「給料のいい仕事につけるから」という意味なのだと思う。両親にさらに四年間の負担を強いるのは心苦しかったが、四年後に俺がたっぷり仕送りできるようになればいい。なるしかない。
だから担任の言う通り、成績がいい方だったのは不幸中の幸いだったのだと思う。自宅から通える距離の国公立大の中で、一番偏差値が高い大学への入学も夢ではないと言われたのはうれしかった。
「私大でも、ここの学校は成績優秀者の学費を全額免除してくれる。こっちは独自の無利子奨学金制度があるから検討してみるといい。あと学費を払わなくていいのは――」
その先は、声には出されなかった。学費免除の大学がどこなのかは俺でも知っているし、それを言わないのは担任の気遣いに違いなかった。主に女子から「くたびれたネクタイのさえない中年」なんて言われているが、俺はこの人の優しさを一生忘れないだろう。
冬の訪れとほぼ同時に猛勉強の日々が始まった。平日は早朝から登校し、施錠されるギリギリまで居残った。休みの日もほとんど自室にこもっていた。両親は土日も働いていることが多かったので、あまり顔を合わせることがなかった。不在の両親に代わって弟に食事を作ることは多かったが、その作業自体は苦痛ではなかった。ただこの先の人生で、このように働いていくことがないのかと思うと、洞に向かって歩いているような徒労感を覚えるだけだった。
結論として、俺はめでたく第一志望の大学に入学し、卒業し、東京の大企業に就職した。学生時代もバイト代を家に入れていたが、これからはもっとたくさん仕送りができる。特に弟はこれから進学などで金がかかる。金はいくらあってもいいだろう。
就職はゴールではなかった。俺にはまだ、やらなければならないことがあった。
俺は身を粉にして働いた。二十四時間戦えますか、そんな言葉を昔テレビで聞いた。戦える、戦えるさ。やりがいもある。結果は給与として明確に数値化される。けれど充実しているとは言えない。何が原因なのかわからない――いや、本当は知っている。知っているが、それはもう手放したはずの夢だ。そう言い聞かせながら深夜のオフィスで眠気覚ましの煙草をふかす。この先、俺はこうして何十年も生きていくのだろうか?
§
「俺、防衛医大に合格したよ」
東京に遊びに来た弟を馴染みの居酒屋に連れて行くと、そんなことを聞かされた。
久しく会っていないのでずいぶん背が伸びたなとは思っていたが、もう受験生だったのかと驚いてしまう。いや、そうではなく、俺が箸を取り落としそうになったのは、進学先の名前のせいだ。
弟は昔から医者になりたいと言っていたし、成績も俺とは比べ物にならないほどよかった。そうはいっても国公立の医学部は狭き門だし、私大の医学部の学費なんて一般家庭に出せる金額ではない。防衛医科大学校はその点学費無料の上に手当までつくが、当然入試の難易度は高い。そんなところに合格したのかという驚きには、父が元自衛官という理由も含まれている。
俺は高三のころ、無意識に自衛官や、それにつながるものを遠ざけようとしていた。父が不正を働いたという疑惑によって退職を余儀なくされたことがその理由だった。俺も防衛大への進学は考えなかったし、担任もそれを明言するのを避けてくれた。だが、弟にはそんな嫌悪感はないらしい。
「兄さん、今まで俺たちのために我慢してくれてありがとう。でも、もうそんな必要はないし、俺たちだって兄さんが苦しんでいる姿は見たくない。今からだって、遅くはないんじゃない?」
弟が差し出したのは、地元の銀行の預金通帳だった。俺が社会人になってから始めた仕送りがそっくりそのまま入っていると言う。
俺はもしかしたら、父を恨んでいたのかもしれない。夢を諦めざるを得なくなった原因は父親だと思いつつも、親を恨むなんて許されないことなのだと、自分を抑圧していたのだろうか。だから父の職業に連なるものを忌避したのかもしれない。
言葉に詰まった俺から目を逸らし、弟は頬杖でつぶやく。
「父さんも母さんもそう思ってるよ。忙しすぎて帰ってきてくれなくて寂しがってる」
うん、そうか、ごめんな。そう答える俺の声は震えていた。磨かれたテーブルの木目が、かすかに滲んでいる。
それから数年後、父が関与したとされる事件の調査が実施されることとなった。話を聞いた当初は、今更何をされたところで、何かが変わるわけでもないと感じていた。俺の学生時代は戻らないし、父が復職できるわけでもない(そもそもそういう気もなさそうだったし)。
けれど、捜査によって父の無実が判明し、マスコミによって全国的にも報じられた後、考えは変わった。涙を浮かべるほどによろこび、安堵している両親の姿を見て思い知った。過去は戻らないとしても、費やされたものは無為に過ぎないとしても、明らかにすべきことをそのままにしてはならないのだと。
心残りがあるのなら、それを捨て置いたまま生きられはしないのだと。
俺はまだ間に合うだろうか――そんな思いが浮かんだ時点で、心は決まっていたのだと思う。
§
家族全員に背中を押された俺は、俺が弟のために送った金を調理師専門学校の学費に充てさせてもらった。入学した直後は二十代半ばで十代に交じることに抵抗があったが、すぐにそれもなくなった。辞めた仕事とは比べ物にならない充足感で、二年間はあっという間だった。
卒業後は東京勤めをしていたころの伝手を頼って、都内の日本料理の店で修行をした。有名ホテルの厨房でも学んだあと、俺は故郷の珠閒瑠市に戻ると港南区のシーサイドモール近くにテナントを借り、自分の店を開いた。はじめの頃は細々と営業をしていたのだが、地元紙の取材を受けた後から徐々に客足が増えてきた。「シリーズ・夢追う人」なんてタイトルでの取材は恥ずかしくて仕方なかったが、繁盛につながったので今となってはありがたいばかりだ。
ある雨の日だった。その日の昼営業が終わる間際の十四時直前、アルバイトに出すまかないを作り始めたくらいの時刻に、一人の若い男性客がのれんをくぐって入って来た。いつもならありがたいことに十三時すぎにはすべてのメニューが売り切れているが、この日は雨で客足が鈍かったので店先にはまだ「営業中」の看板が出ている。なので、「まだ大丈夫ですか?」と心配そうな顔をする彼を、俺は笑顔で迎え入れた。
「雨、酷かったでしょう。よかったら使ってください」
肩のあたりが濡れていたのでおしぼりとは別にタオルを差し出すと、彼は折り目正しい謝辞を述べる。真面目な性格のようだしスーツ姿ではあるが、如何せんその色合いが個性的な上に金属フレームの眼鏡のレンズにも色が入っている。カタギなのかそうでないのか、勘ぐってしまいそうになった。
「すみません、助かりました」
男性がタオルを返すために腕を伸ばすと、不意に煙草の香りが鼻先を掠めた。喫煙者特有の、体に染みついたものだった。俺も会社を辞めるまではヘビースモーカーだったので、少し重苦しいなつかしさがこみあげた。今も時折口元が寂しく感じることはあるが、料理人として味覚や嗅覚に悪影響があってはいけないので禁煙を続けられている。そんなことは彼の知ったことではないだろうが。
カウンター席に座った彼に鯖味噌定食を出したタイミングで十四時になった。俺は外の看板を「準備中」にひっくり返す。雨脚は少し穏やかになっていた。
男性客は定食を綺麗に平らげてくれた。皿の隅にまとめられた小骨に、几帳面さが見てとれる。
「ごちそうさまでした」
そのままカウンター越しに会計を済ませ、彼は財布をポケットに仕舞いつつ立ち上がる。そうしてドアの方に向かうのかと思っていたが、その足は動かない。
どうしたのだろうか、何か料理に不都合があっただろうか。俺は不安に息をのんだ。口を開いたのは、客の男性のほうだった。
「あの、」
「はい」
何か言いたげなのは見ればわかるのだが、その後の一言がいつまでも出てこない。
「……何か?」
問いかけていいものか悩んだが、二人して黙りこくっていても仕方がない。
「――いえ、先日の新聞記事を拝読しまして……」
それはおそらく彼の言いたかったことではない気がしたが、問い詰めるわけにもいかないので話を合わせるしかない。
「そうなんですか、ありがとうございます」
軽く頭を下げると、相手も同じようにした。律儀な人だな、と、少しおかしくなる。
「社会人になってから専門学校に進まれたそうですね。ご苦労もされたことでしょう」
おや、と、思った。本意ではないだろうと感じていたのに、その言葉は本心からの気遣いのようなものが込められているように思えたのだ。彼が何を言いたいのか、あるいは、聞きたいのか。それは知る由もないのだが、一つだけ否定すべきことがある。
「いえ、これが夢でしたから。大変じゃなかったというと嘘になりますが」
事実として、苦痛に感じたことは一度もない。そういうと、男性客は僅かに目を細めた。
「きっとあなたにとって天職だったんでしょうね」
薄く色の入ったレンズ越しに見た彼の目は、ここではない遠くを見ているように感じられた。何故だろうか、俺はその目を見て、東京で働いていたころの自分を思い出した。
彼は思い出を振り切るように、軽く首を振る。
「――定食美味しかったです。また来ます」
「ありがとうございます。お待ちしております」
最後にもう一度軽く会釈をして、男性は店を出ていった。
皿を下げながら、ふと気が付いた。『苦労をしただろう』という言葉は、もしかしたら父のことを言っていたのかもしれない、と。あの記事には俺が調理師学校に進んだきっかけとして、父の名誉回復のことも書かれていた。もちろん話の本筋ではないので二行程度のものだったのだが――いや、その程度の記述は誰だって読み飛ばすはずだ。今まで誰一人として、そのことに言及する人はいなかったのだから。
「まあ、考えすぎだろう」
ひとりごちて、テーブルを拭き上げる。俺の頭はすでに今後のことを考えてはじめていた。夜は二組の予約が入っているが、この天気ではそれ以外の客足は望めないかもしれない。
雨はまだやまず、残り香はとうに消え失せている。
(了)
さらば愛しき面影よ
青葉区の大通沿いにあるコンビニが、フリーターの俺の勤め先だ。青葉区は珠閒瑠市の官公庁が集まっているが、テレビ局やら出版社も多い。コンビニの客層もそんな感じで、堅苦しいスーツ姿も見るし、フリーターの俺よりラフな格好も見かけることが多い。あとは芸能人やらタレントやらもしょっちゅう見かける。こないだなんて黒須純子が来た。大きなサングラスをかけてたけど、オーラは隠しきれていなくてバレバレだった。黒須純子は新発売のコンビニスイーツを三つ買って、そそくさと退店した。その姿があまりのインパクトだったので、その日バイト仲間との話題は黒須純子の買い物のことばかりだった。
「あれってスマスマスマルで特集したやつだったよね」
「黒須純子、気に入ったのかな……」
「でもなんで三個?」
「家族の分じゃない? 旦那と息子がいるって言うし」
「へぇ……なんかイメージ違う、家族思いなんだね」
こんなふうに立地柄有名人を見かけることも多いが、勤務中に見聞きしたことを言いふらしたりするな、というのは働き始めてすぐに言い含められている。つい誰かに話したくなる出来事もなくはないが、俺自身が芸能人やら有名人に興味津々というわけでもないので、禁忌を破ることはなかった。
それに、気になる人は別にいる。
毎日のようにやってくるあの人を意識し始めたのは、高校を卒業してから二回目の夏を迎えたころのことだった。
女性にしては長身なので、まずそれだけで目を引く。加えてスタイルもよければ顔もいい。タレントかモデルだろうかと思えるほどだが、そういうのに詳しいバイト仲間に聞いても「フツーの人だと思うよ?」という返事だった。一般人ながらモデル並みのスタイルと女優並みの美貌、それだけならば近寄りがたい美人でしかなかったが、彼女はいつだって明るく溌剌とした、親しみやすい雰囲気があった。支払いの後に商品を受け取りながら、「ありがとうございます」と笑ってくれる。
男なら誰だって悪い気はしないと思う。いや、フリーター仲間の女性店員も「あの人すごく感じがいいですよねぇ」なんて言うから、性別を問わず好かれているに違いない。
彼女は本当に、いつだって笑顔だった。日付が変わろうかという深夜に栄養ドリンクを買いに来るときも、疲れをにじませながら笑顔を欠かさなかった。多忙なせいだろう、昼食のタイミングを逃したらしい時刻にやってきて、ろくな弁当が残っていないときも落胆しながら笑っていた。
女性としても、魅力的だと思った。
あるとき彼女が首から社員証を下げたまま来店したことがある。俺は悪いと思いつつも、それを盗み見てしまった。あいにく裏返っていたので氏名はわからなかったが、キスメット出版の文字だけはしっかりと目に入った。
そうか、出版社に勤めているのか。編集者、なのだろうか。
遅い時間まで残らなければならないほど忙しいのも納得できる気がした。俺はいわゆる会社勤めをしたことはないけれど、どれだけ忙しくても疲れていても笑顔を欠かさない彼女は人並み外れているのだと思う。もともとの性格が明るいというのもあるだろうし、なにより周りに対する気遣いの人なのではないだろうか。ウチの店長なんて売り上げが少し悪いとすぐに不機嫌になって、俺はもうそれには慣れたけれど、新人の女の子なんかビビってしまっている。
もしも彼女が店長だったら、いや店長じゃなくても同じ職場で働いていたら、雰囲気が悪くなることなんてないだろう。キスメット出版の社員が羨ましかった。俺も同じ職場に入れたら、なんて妄想はむなしいだけだ。箸にも棒にも掛からないような高校をなんとか卒業できた程度の俺には、出版社なんてキラキラした場所で働くことは叶わない夢でしかない。
まして俺と彼女では、男女としても、つり合いが取れるわけもない。
だから店員と客として、時々関わることができるだけでもありがたいというものだろう。もしも俺がアルバイトの店員風情でなければ、それこそ立場だけでも店長であれば、疲れている彼女にコーヒーのオマケを差し入れることくらいできたかもしれない。下心あってのことではない、と思う。俺はただ、何かを返したかったのだと思う。いつも笑顔を向けてくれる彼女に、感謝を伝えたかったのではないだろうか。
§
ここ数週間ほど、彼女は姿を見せない。
これまでも一週間ほど見なかったことはときどきあった。きっと仕事が本格的に立て込んでいるとか、あるいは風邪か何かで休暇を取っていたのだろう。しばらくするとけろりとした顔でいつものように来店してくれた。
しかしこれほど長く彼女を見ないのは初めてだった。おまけに、街全体がおかしな事態になっていた。
おかしな事態、なんて、小学生みたいな言葉でしか言い表せないのが悔しいが、JOKER呪いなんてものが流行り、ハリボテの飛行船が空を飛び、近所のバーでは武器が密売されているなんて聞くこの状況を、他にどう言い表せるというのだろうか。
更に気がかりなことには、死人が出るような物騒な事件も連続している。俺は彼女のことが心配だった。巻き込まれてはいないだろうかと毎日ニュースを確認しては胸をなでおろしてばかりだった。
しかし状況は悪化し、気づいたときにはすでに、他人の心配なんてしている場合ではなくなっていた。どういう理屈なのかまったく理解できないが、珠閒瑠市は鳴海区を残して浮上してしまったのだ。崩落する地面に巻き込まれた人も少なくないと聞くので、俺が今こうして生きていられるのは、本当に運がよかったのだろう。
§
街は、形ばかりは元の姿を取り戻した。それは全体をおおまかに見れば、というだけであって、個人のレベルで言えば散々なものだった。店長は行方不明、新人バイトは両親が大怪我を負い、俺は家族が無事だったものの、家が全壊した。とりあえずは市が仮設住宅を用意してくれるらしいが、当の市役所も被害甚大でいつになるかわかったものではない。友人の家に厄介になりながら、俺は彼女のことを気にかけていた。どういうわけかニュースはあの一連の災害(と言っていいだろう、これはもう)を報じなかったし、珠閒瑠市全体も通信網がズタズタになってネット経由で情報を得ることもできなかった。気がかりを気がかりのままにせざるをえない状況はもどかしく、沈んだ気持ちがさらに沈むようだった。
それでも日常は続く。フランチャイズの本部から派遣されてきた社員が面倒そうに切り盛りする中で、俺はアルバイトとしての日々に戻っていく。しかし不思議なもので、かつての日常だったものの中にいると、安心するようなところがあった。インフラが徐々に回復していくと、俺だけではなく街の人たちも雰囲気も、数か月前に戻ったような気がした。それは錯覚か、思い込みだったのだろう。
三日ほど経った朝、彼女が来店した。朝の店外掃除をしていた俺によっては不意打ちだった。
「おはようございます」
そう、彼女はよく挨拶をしてくれた。明るくて、こちらまで晴れやかな気持ちになれる声だった。けれど今となっては、それも過去の記憶にしかならないらしい。
決して暗いわけではない。人によっては、落ち着いた声音だと評するだろう。俺にはそうは聞こえない。彼女の中から何か、きっと彼女がずっと大切にしていた何かが、そぎ落とされた――俺にはそう聞こえた。彼女の笑顔には、自分自身の一部をえぐられるほどの悲劇を受け止めながら、それでも前を向こうとする痛々しさすら感じられた。
あの大惨事の後から、こんな顔をする人が増えたように思う。誰もかれも同じだった。街も同じだ。表面上は元通りなのに、皆同じように何かを喪失し、代わりに悲しみと痛みを与えられている。それが避けられないものだと受け止めながら、それでも隠し切れずに溢れてしまう。
俺も同じだった。悲しく笑う彼女の表情が、声が、俺の中から恋心と呼べるものを消失させた。
俺は溌剌と明るい彼女が好きだった。けれどあの頃の彼女はもうどこにもいない。きっと痛ましく姿を変えた街と同じように、かつての姿はどこかへ消え去ったのだ。
街が復興しても、それがかつての街とは全く異なるように、彼女が昔のように笑う日がきても、もはやあのときの笑顔とは違うのだろう。
「おはようございます、いらっしゃいませ」
驚くほどに事務的な声が、俺の口からこぼれ出ていた。もうこの胸は高鳴ることもなく、消息を気に病むこともなくなるのだろう。空々しい来店チャイムを聴きながら、俺は失望していた。失恋のむなしさすら感じられないことが、何よりも悲しかった。
(了)
かなしい街
珠閒瑠市には、港南区と鳴海区の二つの港湾地区がある。かつての港南区は工業地帯のような様相を見せていたが、最近では大きな商業施設や科学館が出来たこともあって、市の内外を問わず人が集まる華やかな地区に変貌した。対して鳴海区はいまだ開発途中のため殺風景で閑散としている。珠閒瑠市はここ鳴海区を港南区に次ぐ観光地区にしたい思惑で、まずは外資系の大型ホテルを誘致したが、話題になったのは一時に過ぎず、地下鉄の延伸工事もまだ途中ということもあって、人の出入りは他の区に比べるとはるかに少なかった。
今になって思えば、それも不幸中の幸いだったのかもしれない。
現在の鳴海区は全域が見るも無残に崩壊している。跡形もなく、という言葉はこの光景のためにあるのだろうと思えるほどだった。
この場にあるものは、一見しただけでは、いや、よくよく見てもそれらがなんなのかわからない。低く、あるいは高く堆積したものを凝視した俺がようやく最初に名前のついた物として認識できたのは、自動車のタイヤだった。それからどこかの会社の看板の破片、ひしゃげた家具、濡れて乾いた紙の束、破れて泥まみれになった布……それ以外はすべて、圧倒的な力に押し流され破壊された残骸としか言い表せなかった。
すべては珠閒瑠市の一部が浮上するという、怪現象がもたらした惨劇の爪痕だ。
鳴海区以外の珠閒瑠市は、真円形の境界部を崩落させながら浮上した。その結果、それまでそこにあった土地そのものがなくなるので、海水が珠閒瑠市跡に流れ込む。その何日か後に元のように降下してきた珠閒瑠市によって、溜まっていた海水は再び、堆積した様々なモノとともに海へ押し流される……というのが、ここで起こった悲劇の要点だ。頭では理屈を組み立てることはできるが、現実として受け止められるかというと、その限りではない。
俺は地獄と言うものを見たことがないが、それはきっと光も届かぬ暗い場所で、おぞましい見た目の化け物が跋扈し、苦痛を訴える亡者たちの呻きがこだましているのだと想像していた。
しかしここは、曇っているが明るく、動くものはなく、聞こえるのは海鳴りの音ばかり。想像上の地獄とは正反対と言ってもいい光景だが、ここが地獄でないとは、断言できない。
鳴海区に住んでいるわけでもなければ、訪れた経験すらほとんどない俺でも、この光景はショックだった。言葉がなかった。復興作業開始の初日には市の職員や、奇跡的に難を逃れていた住民が足を運んでいたが、絶句したような沈黙の後、そこかしこからすすり泣きが聞こえてきた。それが徐々に激しさを増していくと、俺もつられたように泣きたくなったが一瞬でその気は消えた。消えたと言うか、消した。気のせいだろう、と言い聞かせた。思い入れなんてないのだから。俺には彼らのように涙を流すだけの道理がないのだから、と。
「ぼさっとすんな新入り。始めるぞ」
会社の大先輩である測量士の春川さんが俺を小突く。この人と一緒に仕事をするのは初めてではないが、あまり口数の多い人ではないので人となりをよく知っているわけではない。それに俺だってべらべらしゃべるタイプでもないので、仕事中は雑談なし、必要最低限の事務的な会話で一日が終わるのがほとんどだった。
今日も黙って、機材を抱えて歩く春川さんの後を追いかける。確かにぼさっとしている暇はない。もう二週間ほどひたすら測量をしているが、まったく終わる気配がないのだ。この仕事は市からの発注だし、国と県からも補助が出るという噂もあるから、社長は期間が長びくほど売り上げが確保できるとほくそえむかもしれない。が、現場を知っている社員たちは以前から受注している仕事があるのでできればそちらに人員を割きたい。しかし荒廃した鳴海区の復興という大義名分を無視するわけにはいかず、測量をさっさと終わらせるために、俺たちは毎日黙々と機材を配置しては測量するだけだった。
冬は寒いし、海辺は風が強い。その二つが組み合わさった結果は、当たり前だが「凍えるほど寒い」の一言に尽きる。測量士補になって一年。こんなところで毎日仕事をしても泣き言一つ零さない自分を褒めて欲しい……などという、無分別な考えはこの場では思い浮かびもしなかった。
人の生活が完膚なきまでに破壊された場所には、まだ暴力の気配が残っているように感じられて、神妙な態度を余儀なくされた。気にしないように努めていなければ引きずり込まれるような恐ろしさがあったから、俺は必死だった。地獄を見まいと懸命だった。対照的に春川さんは落ち着いていた。初日からさして動じることもなく、淡々と作業を進めているように俺には見えた。
うらやましいほどの平静だったので、一週間ほど前にとうとう訪ねてしまった。「あんま堪えてなさそうっすね」と。春川さんは一瞬手を止めて俺を一瞥し、「震災で見たからな」と返した。
「呼ばれたんだよ、応援でな」
震災――二年前に関西地方を襲った地震のことだった。地震発生から数日後、復興作業の前段階として全国からのべ二万人の測量士が集められたらしい。春川さんがその中に選ばれたのもわかる気がした。測量士歴三十五年の大ベテランだ。おおいに活躍したことだろう――と、口に出すのは不謹慎だと思ってやめた。春川さんは俺を気に留めるでもなく、海風に肩をすくめながら呟くように語る。
「震災でボロボロになった街を見た時はまあ、堪えたよ。ただな……人間は慣れてしまうもんだ」
俺はその場にいなかったのに、その言葉の意味をなんとなく理解できた。荒廃した鳴海区を訪れた初日をピークに、俺の中の感情が徐々に摩耗しているような、鈍化しているような感覚は確かにあるからだ。いや、鈍化「させている」と言ったほうが適切だろう。
港湾地区にあった会社の関係者だろうか、何かを探しにくる人々の姿を見たとき、確かに最初は心が痛んだ。悲しんでいる人たちを目の当たりにして、その手伝いをできないことを申し訳なく感じた。民間建設会社の重機、警察官、災害派遣されてきた自衛隊が瓦礫の山をかきわけているのを見る度、苦しんでいる人を手伝い、直接助けられるのが羨ましくすら思えた。自分が彼らからどんな視線を向けられているのかを気にしてしまうこともあった。俺たちのしていることが役に立たないとは思わないが、役に立つのはずっとずっと先のことだろう。考えると苦しくなるだけだった。だから考えないように、感じないように自分に言い聞かせる。俺は俺のできることをするだけだ、それがベストなんだと思いこむことにした。それから俺は、あまり周りを見なくなり、何かを感じることも少なくなっていった。
§
年の瀬が近づいても作業は終わらなかった。春川さんの言う通りなら震災復興には大量の測量士が送り込まれたようだが、この現場はそうではないらしい。役所の方で応援を手配しているという話も、信じていいものか疑わしいところだ。
来る日も来る日も同じ作業に、少し飽きはじめている薄情な自分を否定できずにさらに気分が落ち込む。春川さんは相変わらず淡々としている。もしかしたらこの人は俺以上に鈍化しているのではないだろうか、と、考えると、仲間意識のようなものでほっとしてしまう。嫌な兆候だな、と、思うだけの正気はまだあった。
その日も分厚い雲が空を覆っていた。昼食は、港南区にある教会が差し入れてくれたパンとスープだった。炊き出しのようなそれは、人を探している市民とか、瓦礫の撤去作業などにいそしんでいる「俺たち以外」向けだと思ったので遠慮したのだが、シスターの柔和な笑みに押し切られて受け取ってしまった。気が引けて口をつけられない俺の横で、春川さんはあたたかいスープを旨そうに啜っている。啜りながら、こんなことを言う。
「神様ってのは、早朝に働いた人間も、昼間に働いた人間も、長く働いた人間も短時間労働の人間も、みーんな等しく救ってくださるんだとよ」
「……なんですか、それ?」
春川さんは何も答えなかった。俺はあらゆるものに観念して、丸い大きなパンをちぎってほおばる。噛み応えのある硬さだったが、スープは悪くなかった。いや、こんな寒い中で他人のために身銭を切って施してくれているのだ。俺はパンもスープも残さずに平らげた。思ったよりも空腹は満たされたが、精神的な充足感からは程遠い。
午後の作業を初めて一時間ほど経ったころ。
「見つかったぞー!」
そう遠くないところから、叫び声が聞こえた。何事かと思って顔を上げると、声のしたほうに人がわっと集まっていく。見つかった、と、聞こえたが、何が見つかったのだろうか――というのは愚問だ。とてつもない悲しみの予感に、喉の奥が苦しくなる。俺は緊張で顔が強張っていくのを自覚した。
春川さんと俺は、しばし作業の手を止めてそちらを見ていた。ほどなくして消防隊二人の姿が現れる。彼らが抱えた担架の上には、ブルーシートに包まれた何かが乗っていた。
それを目にした瞬間の、棒か何かで胸を衝かれたような衝撃。
(ああ――)
予想できていても、感情を上手く処理できなかった。心臓がバクバクとうるさく、勢いよく送り出された血液が頭に上っている気がする。バランスがとれない、四肢の感覚がない、呼吸できているか定かではないし、きちんと立てているのかわからない。かろうじて動かせた目で隣を見ると、
「……」
春川さんが両手を合わせて、静かに瞑目していた。
はじかれたように俺もそれに倣う。担架が目の前を運ばれていく気配がした。薄く目を開けると、近くにいた警官たちは敬礼で、建設会社の連中は重機から降りて両手を合わせているのが見えた。
「ありがとうございます、暮れまでに息子を連れて帰ることができました。みなさんのおかげです」
担架の後ろをついていく初老の夫婦は、そう言いながらあちこちに頭を下げていた。奥さんのほうは声を上げて泣きながら、それでも夫に支えられて懸命に両足を動かしているように見えた。
海から吹く風は、恐ろしいほどに冷たい。俺の想像の地獄は炎が地面を舐めていたが、この地獄は、凍り付くほどに寒かった。
気づいたときには二人の姿がにじんでいった。涙のせいだった。なんで俺が泣いているのだろう。あの夫婦も息子も見知らぬ他人だ。もちろん人が亡くなったのは悼むべきことだ。でもこんなに、子供みたいにボロボロ泣くなんてどうかしてる――。
そうだ、どうかしている、この街が、街に降りかかった何もかもが。
「なんでですか」
「あ?」
俺は春川さんを振り返らなかったが、合掌を解いて怪訝な顔をしているらしいことは察しがついた。
「あの息子さんが、ご夫婦が、何したって言うんですか。こんな、こんな悲しい酷い死に方しなきゃいけない理由ってなんなんですか。なんで息子が死んだのにお礼を言ってんですか」
自分でもわけがわからなかったし、何を言っているのか意味不明だった。駄々をこねている子供のようだと頭のどこかでわかっていても、俺にはどうすることもできない。理性と感情がバラバラになって、制御不能になっているみたいだった。
「この街だってそうですよ、だって意味わからないじゃないですか、街がUFOみたいに飛ぶなんて、飛んでった街にいたほうはマシですよ、無事に降りてきたし、自分たちは選ばれたんだって、よろこんでたかもしれないじゃないすか」
かもしれない、ではなかった。俺たち――街とともに浮上した市民の中には選民思想めいたものを口に出すやつもいた。口には出さなくても、内心では優越感と安堵で満たされていた人も少なくはないだろう。俺が打ちのめされている理由の大半は、自分がそういう醜い考えを持っていたことに対する後ろめたさと罪悪感のせいに違いない。俺たちに責任はないかもしれないが、他者に降りかかった悲劇を無視したことは罪でなくて何なのか? 実際に見ていなくても、街が浮上した後に残された鳴海区や近隣地域に何が起こるかなんて簡単に想像できたはずなのに。
俺のしていることは自分勝手な償い、あるいは償いと思い込んでいる自己満足なのだろうか。しかし償おうとしたところで、償える罪などあるのだろうか。そこには弁済可能な損害はあっても、失われた命や時間は二度と帰らない。だとしたら俺はこの罪悪感を一生ぬぐえないまま、生きていかなければならないのだろうか。理不尽な悲劇とやらは、こんなものまでもたらすというのか。
「なんなんですかそれ、こっちはめちゃくちゃだ、人だって死んでる、どうして、なんで」
みっともない、情けない、これが成人した男の言ってることだとは思えないし、俺だって信じたくはなかった。風は冷たく気温は低いのに、涙も鼻水も俺の体温のままに垂れ流されている。合わせたままだった両手で顔を覆ってうずくまってしまいたかったが、できなかった。当事者であるはずの夫婦がそれでも歩いている様を見たのだ、俺が崩れ落ちるわけにはいかなかった。
もし、もしも、この惨劇が誰かのせいなら、例えば悪いやつが何かのスイッチを押して街が飛んでいったのだとしたら、俺にもそいつのことを殴らせてほしい。一発殴るくらいじゃ気は収まらないが、そうでもしないと気持ちの持って行き場がないのだ。
でもそんな誰かはいない。この惨劇には都合よく感情を引き受けてくれる極悪人なんているわけがない。仮にいたとして、俺の罪悪感までをそいつに背負わせるわけにはいかないだろう。俺たちはこの有様を受け入れなければならない。被害も、悲しみも、罪悪感も、すべて。
「わかってる、わかってんですよ、でも……」
理不尽さなんて知っていたつもりだったのに、いざ目の前に突きつけられると拒んでしまう自分しかいない。歯を食いしばりながら春川さんの言葉を思い出す。神様は誰もを等しく救ってくれるかもしれないが、同じように誰に対しても平等に惨たらしい仕打ちができるのだろう。
春川さんは何も言わず、担架を回収して夫婦を乗せた車が走り去るのをじっと見ている。口からは何の言葉も出てこなかったが、悼む気持ちと悔しさと、無力感が眉間の皺に感じられた。
それでもこの人の顔は、疲れ切って諦めた人間の顔ではなかった。罪悪感などはとうに振り切ったような、強さを感じる表情だった。
希望を、持っているのだろうか――わからないが、今の俺は何でもいいから光を示してほしかった。あの震災の場で、今の俺と同じように理不尽さに打ちひしがれたはずのこの人が、まだ歩みを止めてはいない理由があるとしたら、それを教えて欲しかった。
「馬鹿野郎、泣いてどうなるってんだよ。やるしかねえだろ、自分にできることをよ」
そう言った人は、じっと前を見ている。前しか見ていない。もしも希望と呼べるものがあるとしたら、それは自分の前にしかないのだと強く信じて声を上げている。
俺は何も言い返せなかった。そんなふうに強くあることはできない。少なくとも今、すぐには。
俺たちの街は壊れてしまった。街も人も、壊れてしまった。失われた命と生活と思い出はもう二度と戻ることはないし、俺はあの頃のような能天気な自分にはもはや戻れない。
けれどこの街を、この地獄のままにはしていられないと思ったのは事実だった。
俺たちは瓦礫を撤去し、土地の安全を確かめ、もう一度この街を、鳴海区を、俺たちの街にしなければならないのだ。復興した街には慰霊碑ができて、それを見る度に何度も胸をかきむしられるような苦しさを味わうのだろう。
それを元通りと言うことが正しいのか、あるべき姿なのか、俺にはわからない。何をすれば俺の罪悪感が薄れ使命感が満たされるのかわからない。わからないまま前だけを見つめて、歩まなければならない。苦痛に満ちた道程だとしても、生きている俺にはそうすることしかできない。いつかこれを希望と呼べる日が来るのだろうか。歳をとった俺は、そう振り返り得るだけの強さを得ることができるのだろうか。
「仕事戻るぞ」
相変わらず口数の少ない春川さんに促される。その姿は冷たいようで、しかし確かな救いでもあった。少なくともこの人はまだ歩いているのだから。
俺はもう一度だけ、あの家族が去っていったほうに頭を下げた。
鼻をすすれば寒さでかじかむ手の中に雪が舞い落ちる。春はまだ遠いが、雲の隙間からは薄く光が漏れていた。
(了)