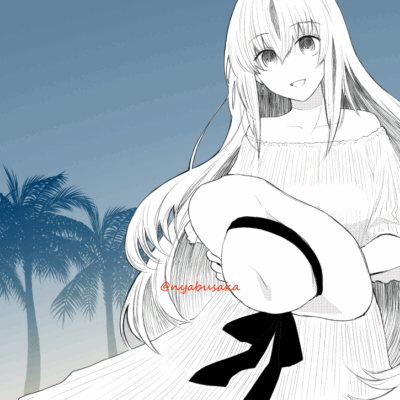学校が氷漬けになったり、よく知らない会社のよくわからない機械が暴走して街が変になった。というのが、後に「セベクスキャンダル」とか「御影町プラズマ隔離事件」と呼ばれる一連の出来事に対する綾瀬優香の認識だった。そのよくわからない事態が解決して街が元通りになったとき、綾瀬は大多数の人間と同じように当然喜んだ。これでもう心配することはなくなったし、明日からは穏やかな日常が送れるだろう。そう、手放しで喜んでいた。事件が解決して、すぐの頃は。
さすがに最初の一週間は、後始末のようなゴタゴタで落ち着かなかった。警察とか、市や県の職員らしき作業着の大人たちが街中のいたるところで難しい顔をしているのを綾瀬も見た。
特にセベクの建物の近くは大変な有様だったらしい。
「すごかったぜ昨日なんてさ、セベクビルの前で近所の人たちが大声上げてたんだよ」
「デモ隊のようになっているらしいな。まあ、得体の知れない企業だという印象が広まったんだろう。セベクは御影町からの撤退を余儀なくされるだろうな」
事件の真っ最中にあのビルの中に突入したクラスメイトたちにとっては気がかりだったようだが、そのメンバーではなかった綾瀬にとっては今までもこれからも特に関わりのない対象なので、さして気に留めることもなかった。ただ、事件の当事者としてセベクのことを気にかけているクラスメイトの心境については、少し関心があった。
クラスメイトの数人が最初にセベクビルに突入した最中に綾瀬が何をしていたかと言うと、こちらはこちらで友人ら何人かとともに氷漬けの校内を走り回っていた。目的は、突如として現れた塔に登って鏡のかけらを集めること……というと、なにやらロールプレイングゲームのような牧歌的な趣すらあるが、当の本人たちにとってはそんな生易しい状況ではなかった。見慣れた学び舎が変わり果てた姿になったのは、学校についてさしたる思い入れのない綾瀬であっても胸が痛んだ。悲しいと言うよりは「なんてことしてくれたんだ」という、日常を破壊されたことへの怒りの方が大きかったかもしれない。
事件が終わった今、セベクビルを見に行ったクラスメイトがもとからそこ(ビル)に思い入れを持っていたとは考えにくいが、彼らも駆けずり回った場所については何かしら感じるものもあるのだろう、と、綾瀬は想像している。
元通りになった校舎を、ついすみずみまで見回るように眺めながら綾瀬はそんなことを考えていた。
「思いだしただけで芯から凍っちゃうよ」
愚痴っぽい一言を吐き出し、カーディガンのポケットの中で使い捨てカイロを握りしめる。笑われそうで誰にも言っていないが、実はあの事件の後からカイロが手放せない。だいぶ後になって「ある意味トラウマだったのかもしれないね」と、指摘してくれたのは、この数年後にカウンセラーとなった友人の言だ。
当たっているかもしれない、と、後の綾瀬も思う。事件の直後は解放された安堵とある種の高揚のせいで、自分たちにストレスがかかっていたことに気づけなかった。だから事件から数日、数週間が経つうちに、気がかりだったことがじわじわと綾瀬の胸の内に広がっていったように思えたのだろう。本当は事件の直後から、あるいは最中から、ずっと考えていたかもしれないのに。
綾瀬は放課後の校舎を一人で歩いている。事件の前の彼女は、授業が終わるや否やに昇降口に向かい、友人たちと遊びに出かけたものだった。たまに補習を受ける以外で放課後の校舎に残ることなどほとんどなかった。それが今、見回りのようにしてあてどもなく歩き回っている、その理由は綾瀬にもよくわからない。
誰かを探しているような気がしたし、その誰かには二度と会えないことを知っていながらそんな気分になっていることも理解していた。
冬の日没は早く、校舎の中は半分が赤い夕陽に浸り、もう半分が暗い影に沈むようだった。半分燃えて、半分が燃え尽きている、そういうふうに見えなくもない。それも後から考えれば、無意識に氷から一番遠いものを思い浮かべようとしていたのかもしれない。
氷の城、三つの塔。そこにいた少女たち。綾瀬はそれらについて考えることをしなかった。考えることを、しようとしなかった。
しかし考えないようにしているということは、意識してしまっていることに他ならない。そう気づいたのは、御影町にこの冬初めての雪が降った日だった。
§
大石静は校長室の扉を開けると、手に抱えていたコートをハンガーにかけた。車を降りてから校舎に入るまでに少し雪に降られたため、コートの表面には雪が溶けた水滴がまばらに残っている。それを手のひらで軽く叩き落としながら、彼女は長い溜息を吐いた。
校長の仕事というのは大半が対外的なものだが、学内のことを何もしないというわけではない。むしろ気にかけているからこそ、県と市の教育委員会にカウンセラーの派遣を連日掛け合っている。しかし前例主義の役人仕事と揶揄されるだけあって、彼らの態度は変わらず、本日も結果は芳しくなかった。
聖エルミン学園の生徒たちの様子が目に見えておかしいわけではない。ただ、それは心理学の専門家ではない大石から見て、という話だ。もしかしたらカウンセラーは大石や他の教師たちも見落としているような異変に気付くかもしれないし、あるいは教師たちの中にもカウンセリングを必要とするものがいるかもしれない。校長という立場である以上、この学校に所属するすべての人たちに気を配っていなければならない。
「あんなことがあったのだから、皆少なからず何かあるんじゃないかしら」
傷ついていたり、悩みを抱えていたり――そう、自分のように。
一連の事件が終了した今、大石はこれまでの比ではないプレッシャーを感じていた。毎日外出しているのも、ある意味ではそれからの逃避のように思えて気が滅入っているところだった。
だから、校長室の扉の向こう――鱗模様の型板ガラス越しに生徒らしき人影を認めたとき、彼女は反射的に扉を開けてしまった。
「わっ⁉」
その人物は、さすがにノックするより先に扉が開くとは思っていなかったのだろう。驚いた声が放課後の人気のない廊下にしばし残響した。
「綾瀬さん?」
意外な顔に、大石も綾瀬と同じように目を丸くしてしまう。そもそも校長室にやってくる生徒というのはほとんどいない。まして大石は綾瀬優香という生徒を、好き好んでここに来るような生徒だとは認識していなかったので驚いた。
三秒ほど何も言わずに二人は向き合っていたが、廊下に満ちていた冷たい空気が次の行動を起こさせる。
「寒いでしょう、中にお入りなさいな」
ガラス越しの綾瀬は、扉の前で逡巡していたように見えたので校長室か校長のどちらかに用事があるのだろう。大石の推測どおり、綾瀬は校長室の中に足を踏み入れた。
「おじゃましまーす……」
後ろ手に扉を閉めながら入室した綾瀬は、キョロキョロと室内を見回している。所在ないのか、好奇心ゆえか。そんな彼女を興味深く見ている自分も似たようなものかもしれない、と、大石は少し気まずい。
「このところずっと雪だけど、今日は一段と寒いわねえ」
誤魔化すようなことを言いつつ、電気ポットのスイッチを入れる。職員室にはコンロやらレンジのある給湯室が隣接されているが、校長室はこの電気ポットしかない。それでもこんな寒い日には、わざわざ給湯室まで足を運ばなくていいだけありがたい。
綾瀬はあいまいにうなずくだけで返事はない。立ったままの彼女に応接用のソファを勧めると、綾瀬はややためらいながらも腰を下ろした。大した用事ではないなら立ったままでいいと言うだろうから、すんなり座ったということは、彼女の用事は何か深刻なことかもしれない。大石は少し目を細め、それでも表情は厳しくならぬよう心掛けた。
「綾瀬さん、お茶でいいかしら?」
「え?」
むき出しの膝をこすっていた両手が止まる。大石は茶缶と急須を手に取っていた。
「校長先生が? いいの……?」
自分にお茶を淹れてくれるのか?と、表情が問い質している。
「一人分も二人分も変わらないことよ。それとも……綾瀬さんが淹れてくれる?」
後半は半分冗談のつもりだったが、大石の意図に反して綾瀬はすっくと立ちあがった。
「いいよ。アヤセ、実は得意だし」
曰く、小さいころに母親を真似て以来、なんとなく家族内での綾瀬優香の日課になっているらしい。
「面倒は面倒だから夕ご飯のときしかしないけど」
朝は兄貴たちと時間合わないしね、と、綾瀬は大石から渡された茶缶を開けながら語った。
見た目で人を判断するものではないと人に言い聞かせている大石ではあったが、綾瀬の言葉はさすがに予想外のものに感じてしまった。しかし入学前、自分も同席した入試の面接時のことを思い出すと、それほど意外というものでもないと思いなおす。
今でこそ髪を金髪にして化粧を欠かさず制服は着崩している綾瀬だが、中学の頃は真面目な生徒に思えた。髪色はやや明るかったが地毛であるという言葉を疑うほどのものでもなく、入試の成績も内申点も申し分はない。それがどうして今のこの姿になったのかは大石には知る由もないが、所謂非行に走ったわけではないらしい。高校デビューという言葉を聞くようになって久しいが、綾瀬もその類ではないかと思えば、矯正に躍起になることもない……というのが大石のスタンスだった。もっとも、何かと厳しい教頭は綾瀬を要注意の問題児と認識しているらしいし、担任の高見をはじめ各教科の担当教師は彼女の成績に頭を抱えているようだが。
「先生、できたら綾瀬がテーブルに持ってくから、座ってて」
綾瀬の手つきは言う通りに慣れたものだった。
沸いた湯を湯呑に注いで適温になるまで冷まし、茶葉はしっかりと蒸らし、二つの湯呑に交互に注ぐ。丁寧さと辛抱強さが所作の隅々にあった。そういうものは、見ているだけで気持ちが晴れやかになるものだ。
「……うん、美味しい」
きちんと淹れられた茶は確かに美味しかった。雪の中を帰って来た後なので、程よい熱さが殊更に身に染みる。
「よかった~」
綾瀬も自分の茶を口に含み、満足そうにうなずいている。
結果として綾瀬の緊張は解れたようで、大石は目を細めた。
「お茶請けでもあればもっとよかったけど、ごめんなさいね」
大石が言うと、綾瀬は笑って首を振る。
「アヤセもカバン持って来ればよかった。チョコとか入ってたのに……あ、でもお茶には合わないか」
「そうかしら、案外合うかもしれませんよ?」
それから二人は好きな菓子について益体のない会話をしばし楽しんだ。話題は御影町の中にある老舗和菓子店のこともあれば、少し離れた珠閒瑠市や都内の新規店にまで及ぶ。気づけば湯呑は空になっていたので、二杯目は大石が淹れることにした。上等な茶葉なので、二杯目でも十分に濃い緑色だった。
綾瀬は自分の湯呑を持って立ち上がると、大石のいるワゴン横ではなく、大きなガラス扉の書架の前に歩んだ。
「卒アル……」
そこには、綾瀬の言葉の通り、創立以来の卒業アルバムが収められている。
「なにか、気になるかしら?」
傍らまで近寄った大石は、やや硬い表情をした綾瀬から湯呑を受け取った。わずかに残った温度は、茶のそれというより、綾瀬の体温が移ったように思えた。
「あ、いや……」
そういうわけじゃ……と、綾瀬の言葉は否定しきれずに途切れる。大石は少し迷ったが、差し当たっては何も言わず、綾瀬の湯呑に二杯目を注ぐことにした。
「見てはいけないものでもないから、気になるなら開けても構いませんよ」
綾瀬の背中にそう声をかけながら。
扉のガラス部分に指先だけで触れている綾瀬の顔は、冷たい氷に反射しているようにも見えた。あの日凍り付いた学び舎のことを思い出して、身震いしそうになる。
「校長先生……聖子ちゃんカット流行ったのって、いつごろ?」
「え?」
大石は面食らった。聖子ちゃんカット?と、復唱しそうになるが、もちろん未知の言葉というわけではない。それが『かつて一世を風靡したアイドルを真似た髪型』だということは知識として有している。
しかしなぜその単語が今、綾瀬優香の口から出てくるのか、それはわからなかった。
わからなかったが、聞かれたことには答えてしまうのが教師としての性分でもある。
「ええと、そうね……私もあまり詳しくはないんだけど、十年……もっと前かしら、でも二十年も前ではないと思うわ」
それがどうしたのかと聞くより先に綾瀬の手が動いた。
「ありがと! じゃあ、このへんかなっ!」
重い扉を開くと、綾瀬の手は迷うことなく数冊の卒業アルバムを棚から引き抜いた。大石が言葉にした、今から十年ないし二十年前の範囲に該当する年代の卒業アルバムだった。
「綾瀬さん……?」
何が彼女を駆り立てているのか、大石には到底わからなかった。聖子ちゃんカットをした生徒の写真が見たいのだろうか? 何のために?
大石の疑問には答えず、綾瀬は卒業アルバムをテーブルまで運び、ソファに腰を据えて上から――新しい方から順に捲り始めた。昭和の頃のアルバムを見る彼女は真剣な顔をしている。それは興味本位などでは決してない。まるで警察が捜査のために古い資料にあたっているような顔だった。
大石は、綾瀬を邪魔すまいとした。二杯目の湯呑は静かに、綾瀬の手元から少し離れたところに置くに留める。
綾瀬が注視しているのはクラスごとに卒業生それぞれの顔写真が載ったページだった。一人一人の顔を指先でなぞるように確認しては次のページ、次のアルバムに移っていく。大石もなんとなくその作業を観察していたが、最初の四冊には該当する髪型をした生徒はおらず、五冊目でようやくちらほらと見かけるようになった。それでも綾瀬の作業は止まらない。となれば、『その髪型をした女生徒』を探しているのではなく、『その髪型をした特定の誰か』を探しているのではないか。大石にもようやく綾瀬の目的が見えてきたが、目的の動機は相変わらずわからずじまいだ。
綾瀬の手が止まったのは数えて七冊目だった。仮に綾瀬の手が止まらなかったとしても、大石も「あっ」と声を上げたに違いない。
その年に卒業した三年三組の集合写真の右上には、楕円形の写真がはめ込まれている。集合写真撮影の当日不在だった者への対処として知られているものだ。不在の理由は様々だ。急病で欠席していた場合や、ごくまれには、その時点で亡くなっていた場合。
その場所を人差し指でなぞりながら、綾瀬はぽつりと、
「ほんとに……死んじゃってんだ……」
そう言うと、静かに項垂れて背中を丸めた。どうやらその人物は集合写真の撮影時点で故人だったようだ。そして、綾瀬優香はそれを予想していたらしい。
大石はそっと、綾瀬の手元を覗き込む。写真の少女は大きな目が愛らしい。見覚えなどはもちろんなかった。なにせ今から十六年前の卒業アルバムなので、聖エルミン学園に赴任すらしていない大石が知るはずもない。
「そうだよね、言ってたもんね、百合子、生きてるうちに友達になりたかったって」
だから、綾瀬が彼女のことを知っている様子なのがわからない。わからないが、それを問えるような状況ではなかった。
「でももしかしたら、って思ったのに……なんで死んじゃってんだよ……ばかぁ……」
綾瀬の声は震えていた。顔を覆ってしまった綾瀬に、大石はかける言葉もなかった。
§
「校長先生、ごめんね……せっかく淹れてもらったのに……」
大石がもう一度淹れなおした茶を口元に運ぶ綾瀬は気まずそうに頭を下げた。
「いいのよ」
今の綾瀬に冷えた茶を飲ませることは是認しがたいことだった。冷たさは悲しみを増幅させ、対照的に温かさは悲しみを少なからず癒すものだ。
もう一度温い湯で淹れられた茶を啜りながら、綾瀬はその少女のことをぽつりぽつりと語り始めた。氷漬けになった学校の、塔の一つにいた山本百合子という名の少女。高校生だった当時を己の人生の絶頂期であると妄信し、その後は落ちるだけだと悲観して現実から目を背けた少女。おそらくは綾瀬優香とそう変わらない年齢の、あまりにも無垢で愚かな少女。彼女の名前を、綾瀬は何度も口にした。
「わかんなかった。なんで百合子がそんなに簡単に死んじゃったのか、ずっと」
聖エルミン学園の制服を着ていた彼女のことを、綾瀬はずっと気にかけていたのだと言う。それで、これまでの卒業アルバムが保管されている校長室まで足を運んだらしい。しかし確認できたのは「確かに山本百合子という生徒が在籍していた」という事実だけで、彼女の人となりなどはまったくつかめなかった。当時を知る教職員もすでに退職しているが、仮に話が聞けたところで山本百合子の悲観的な内心までは聞けないだろう。
知る手段を失った綾瀬は、けれど諦めはしなかった。彼女なりに思うところや推察できることがあるらしい。
「でも、そうしようと思ってたわけじゃないのかもしれない。なんていうのかな、魔が差したとか? 一瞬そう思っちゃったのを咄嗟にやっちゃったっていうか……上手く言えないけど……」
身振りを交える綾瀬に大石は力強くうなずく。
「ええ、わかりますよ」
説明に難儀している綾瀬の言わんとするところは大石にも伝わった。その場だけの衝動的な行動で取り返しのつかない事態になる……思春期には起こりがちなことだ。山本百合子がどのようにして命を絶ったのかはこの場の誰にもわからないことだが、そうなる前に彼女が誰にもすがれなかったことだけは、おそらく間違いないのだろう。
「……百合子が言ってたの、今でも覚えてる。生きてるうちにアヤセと友達になりたかったって」
大石は息を呑んだ。なんと残酷な一言だろうか、それはまるで――
「もしもアヤセが百合子と友達になれてたら、百合子は死ななかったのかな」
呪いのような言葉ではないか。
あなたには何の責任もないし、それは不要な罪悪感だ、綾瀬がそうまで背負い込む謂れはない。そう言って、彼女の心を軽くしなければならないと、大石はその意気込みで口を開きかけたが、
「――って言ったって無理なもんは無理だよね!」
綾瀬はあっけらかんとした口調でソファの背もたれに勢いよく体を預ける。声音も表情も態度も、強がっているようには見えなかった。むしろ呆れていると言っても過言ではない。唖然としている大石をよそに、綾瀬は湯呑を口に運びながら「あっ」と声を上げる。
「あれ? っていうかもしかして、アヤセ、百合子が死んじゃった年に生まれた?」
卒業アルバムからは山本百合子の正確な没年はわからないが、十六年以上前に亡くなっていることは間違いないだろう。綾瀬は指折り数えていたのを止めて、顔をしかめている。
「えー、気が合いそうとか言われたけど、まさかアヤセ、百合子の生まれ変わりとか?」
突拍子もない言葉に、大石は言葉もない。思考がくるくると目まぐるしく展開していくさまは、ついていくのがやっとどころの話ではなかった。
「アヤセ、百合子の分まで生きるとか、そういうのヤダよ」
そう言って唇を尖らせる綾瀬の顔は本当に、心の底から嫌がっているような表情だった。
大石は、胸を打たれたような思いだった。もし綾瀬が今の言葉を言わなかったら大石は、亡くなった人を思い、その人の分まで幸福になろう――そんな言葉で慰めようとしたかもしれない。けれどその言葉が本当に残された側のためになるのだろうか? いや、百合子が零したささやかな願いを呪いだと断じるならば、『その人の分まで』と言う言葉もまた、呪いなのではないか。
大石は言葉にしなかったが、綾瀬は言われる前にそれを拒んだ。きっと彼女は、自分と百合子はまったくの他人だという事実をこの上なく肯定的に考えている。
大石は両手で湯呑を包み、静かに語った。
「そうね……百合子さんが投げ出してしまったものは、たとえ綾瀬さんが望んだとしても、受け止めることはできないと思うわ」
人は自身の人生しか生きることはできない。『誰かの分まで』という考えを受け入れがたいと感じている綾瀬は、それに自覚的なのだろう。けれど綾瀬は百合子を拒絶しているわけではない。
「綾瀬さんは、彼女のことを考えてくれた、彼女の悲しみを理解しようとした」
そういう相手に最後に巡り合えたことが、山本百合子にとって救いになったかもしれないし、そうではないかもしれない。それは本人しかわからないことだし、真実救いになったかどうかは、綾瀬には関わりのないことだ。
だって、『相手が救われなければ、行動も気持ちも意味がなくなる』なんて、あまりにも悲しいことだから。
「たとえ百合子さんには二度と言葉が届かなくても、綾瀬さんの心にその気持ちがあるということが、何よりも大事で、素晴らしいことだと思うわ」
言っていることはきれいごとで理想論にすぎないのは理解している。口にしながら言葉とは裏腹なことを考えているのも、大石はわかっている。
これは所詮、むなしい想像に過ぎないのかもしれないが、もしも綾瀬と百合子が同じ時を生きていたのなら、悲劇は起こらなかったかもしれない。大石は、学舎の中で笑いあう二人を思わず幻視したような気がした。大人として、教育者として、一人の人間として、その美しい光景をこの目で見てみたかった。この愚かしい願望が叶わないことが何よりも惜しいと思えた。
綾瀬は大石の言葉に耳を傾けているようだった。神妙な顔は、大人の詭弁を見抜いているようにも感じられる。その目から逃れたいとは思わなかった。こんな目ができるほどに綾瀬が成長したと思えば、喜びこそすれ厭うわけはない。
綾瀬はふっと表情を緩め、「ありがと、校長先生」と、目を伏せた。
「でも考えちゃうよね、ほんとにアヤセと百合子が友達だったら、って。百合子が全部投げ出す前だったら、アヤセにもなんかできたかもしれないのに。死にたいなんて言ったら、アヤセが遊びに誘うのに。カラオケ行ってプリ撮って、そんでかっこいー男友達呼んで美味しいものいっぱいおごってもらって、それから……」
綾瀬は湯呑を呷って空にする。
「とにかく、死にたいなんて言う暇なくすくらい一緒にいて、世の中楽しいことがいっぱいなんだぞって怒ったのに」
ゆっくりと瞬きをしたあとの綾瀬の睫毛が輝いていた。
「バカだよ、百合子」
泣き笑いのように顔を歪めて、もうどこにもいない少女を詰る。
「アヤセ、おばーちゃんになっても金髪やるのに、百合子だって聖子ちゃんカットのおばーちゃんになればよかったんだよ」
それで二人で買い物行ったりしたかった。綾瀬はさみしそうに笑う。
綾瀬は確かに傷ついている。孤独な苦しみを抱えていた少女に共感し、その悲しみを分かち合っているのかもしれない。大石は痛ましささえ感じそうだったが、果たして綾瀬は、大人の想像するよりもずっと、強く前向きだった。
「でもね先生……百合子、最後に『ありがとう』って言って消えたの。だから……アヤセたちがあの塔で百合子に会えたのは、そんなに悪いことじゃなかったのかな? それに、アヤセと百合子の歳が離れてなきゃああやって会えなかったわけだから、これって結果オーライ?」
「――」
大石には言葉がなかった。
ああ、なんと頼もしいことだろうか。彼女は友を想い、一人思案し、自分なりの結論を見出したのだ。生徒たちが学業やスポーツで好成績を収める場面ももちろんよろこばしいが、精神的な成長の瞬間に立ち会うよろこびは何にも勝る。
「だからね先生、アヤセ、百合子に会えてよかったって、今、思えたよ」
憑き物が落ちたような、明るい表情だった。この先、綾瀬は時折百合子のことを思い出しては心を痛めるのかもしれない。しかし痛みを伴うほどに想える誰かが心にあるというのは、幸いなことに違いない。
綾瀬は湯呑を空にすると、「ごちそうさまでした」と頭を下げ、ソファから立ち上がった。
「なんか校長先生に話聞いてもらって、頭がすっきりしたかも」
校長室の扉の前で「ありがとう」と言う綾瀬に、大石は「私も」と微笑み返す。
「このところ少し気分がふさぎ込んでいたけれど、綾瀬さんとお話できて気分転換になりました」
担任でもなければ教科担当でもない大石は、生徒と接することが極めて少ない。あのとき扉の向こうに佇む人影を招き入れたのは、大石の本能が生徒との関わりを求めていたのだろうか。そうかもしれない。事実として、綾瀬との時間は充実したものだったのだから。
「ほんと? じゃあまた来てもいい?」
綾瀬は自分の訪問が拒まれてはいなかったと知って、少しうれしそうな顔をした。
「ええ、もちろん」
留守にすることが多いが、もし時間が合えばいつでも。聞いた綾瀬は歯を見せて笑う。
「わかった! 今度はアヤセおすすめのお菓子、持ってくるからね!」
「ふふ、楽しみにしていますね」
綾瀬は片手を振りながら、晴れやかな顔で扉を閉めた。夕刻の廊下はさらに冷たさが増したようで、「さむい~~!」と叫ぶような声と、小走りになる足音が聞こえた。それも徐々に遠ざかり、校長室にはゆるやかな沈黙が訪れる。
大石は卒業アルバムを書架へと戻す。仕舞いながら、この一冊一冊に掲載されているあまたの生徒たちのことを想う。そして彼女の意識は、この先この学び舎を巣立っていく生徒たちへと移った。
どうか皆、優しく健やかでありますように。
望むことはそれだけだ。秀でていなくても、時に間違っても、思いやりのこころを忘れずにいてほしい。そして他者に優しさを向けることは、自分が苛まれていては不可能なことだ。だからまずは誰よりも、自分を大切にしてほしい。人を愛するのと同じように、自分自身も愛してほしい――大石は書架の扉を閉じると、無意識に両手を組んでいた。
祈りは儚く消えた少女のために、そして彼女を思って泣いた優しい少女のために。