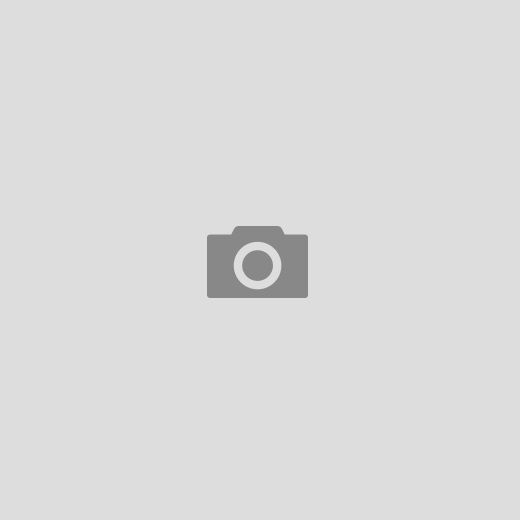⚠幻覚と捏造とシュバルツ兄弟に対する巨大感情(カプではありません)。モブが出たり過去捏造してたり好き放題です。
1
帝国の冬は長い。
体の芯まで凍えるような冷たい風がようやくやんでも、厚い雲が春の訪れを未だ阻んでいる。
バン・フライハイトとフィーネが帝国領内のとあるコロニーにやってきたのは、そんな晩冬の日だった。
「バン! 貴様、軍をやめただと!?」
コロニーに滞在しはじめて三日目、どこから聞きつけたのか定かではない上にあまり聞きたくもないのだが、猛烈な剣幕でやってきたトーマにはさすがの彼らも目を丸くするしかなかった。
「あらトーマさん、お久しぶりです。どうぞ?」
とはいえフィーネのほうは生来のマイペースさゆえか修羅場をかいくぐってきた経験ゆえか、すぐさま表情を緩めて向かいの椅子をトーマに勧める。コロニーの長の家に、厚意を頂戴して寝泊りをしているのだが、当の家主はいきなり乗り込んできた帝国軍人に肝を冷やすばかりだった。
「えっ、あ、はい……いや、そうではなくて! バン!」
気を抜かれたようにフィーネの勧めにしたがって一旦腰を下ろしたはいいものの、トーマは即座に立ち上がってバンを指差す。指差されたバン本人よりも、部屋の片隅で立ち尽くしたままの村長のほうが緊張しきっていた。
「なんだよ」
「貴様なぜ軍をやめたのだ!?」
いや、そんなことはお前には関係ないだろう。と、言いかけてバンは口を閉じる。 火に油を注ぎかねないからだ。もっとも、油をそそがれずとも勢いのままにトーマはまくし立てるのだが。
「お前ほどのゾイド乗りがその力を遊ばせておくなどもったいない! いや別に! これは貴様を褒めているわけではないぞ! 断じてな!」
「どっちだよ」
相変わらずのらりくらりとしたバンに、トーマはさらに何事かを言おうとするのだが苦笑するフィーネに手を振られてさえぎられる。
「まあ……とりあえず座ったら? はい、コーヒーでも飲んで」
そうまでされてようやくトーマは椅子の上に落ち着いた。
「すみません……あ、フィーネさん、塩は結構です」
マイペースを崩さないフィーネにコーヒーを勧められ、トーマは謝辞を述べつつも一言は忘れなかった。
「そう?」
残念そうな響きをにじませつつも、フィーネは白い調味料入れを手元に引っ込める。 トーマが断らなければ、彼女は自分の思うままの「適量」をトーマのカップに入れていたことだろう。
塩入りを逃れ得たコーヒーをトーマが一口すすると、バンは頬杖をついたまま話し始めた。
「デスザウラーも倒した、レイヴンたちももう妙なことはしない。 ルドルフやルイーズ大統領なら、国同士の戦争になるようなこともありえない。だったらもう、軍人だってそんなにいらないだろ? 俺がいなくたってハーマンやオコーネル、それに、共和国と帝国の軍人がいれば十分だ」
「それはそうだが……」
理屈はわかるのだが釈然としない。バンのせいにするつもりもないが、かと言ってこのもやっとした心境の原因を自分の中に求めても答えなど見つからない。
コーヒーの液面に、沈んだ顔の自分が写っている。
「それに、別に俺は、最初から軍人になるつもりなんてなかったからな」
「何?」
顔を上げると、自分とは対照的に朗らかに笑うバンの顔があった。その隣で、フィーネも笑っている。
「クルーガーのおっさんにだまされた」
「バンったら……」
「一人前のゾイド乗りにしてやるって言うんだよ、それで、ついていったら共和国軍に入れられた」
つまり、本当に軍人になるつもりなど毛頭なく、言葉通りゾイド乗りとして成長したいだとか、そういう目的でバンは共和国軍に所属していたわけだ。
フィーネは、それは彼らしい考えだと言って笑うだろう。それが彼らにとって当たり前だから。
しかしトーマはそうではない。考え込みそうになるが、バンの明るい声にさえぎられる。
「まあでも、結果としてはいい経験だったのかな」
『いい経験だった。』
すでに過去の話になってしまったような口ぶりに、もう一度ショックを感じてしまう。
「やっぱ堅苦しいのは苦手なんだよ。それに、俺はもっといろんなものを見てみたい。いろんな場所を旅してみたい」
そんなことは軍人をやりながらでもいいじゃないか。口にしかけて飲みこんだ言葉は、しかしバンには見透かされていたのかもしれない。
「お前にとっては『そんなこと』なのかもしれないけど、これが俺のやりたいことなんだよ」
もはやそれに対して言い返すことすら思いつかない。反論の余地などこれっぽっちも、残っていなかった。
「お前にもあるだろ、やりたいこと」
そう問われたトーマには、答えが思いつかなかった。
2
トーマ・リヒャルト・シュバルツがそんな話をしているとき、帝都を挟んで逆方向に存在するとある帝国軍基地では、彼の兄――カール・リヒテン・シュバルツが二人の男女と話しあっていた。
基地としては小規模な上、老朽化が進み近いうちに基地ごと移転する話すら持ち上がっている。そんな取るに足らない基地に、先月将官に進級したシュバルツが滞在しているのは異例中の異例だった。
「――では、二人ともよろしく頼む」
厳めしい階級に似つかわしくないさわやかな笑みを浮かべ、シュバルツはバインダーを閉じながら男女の顔を交互に見渡した。
「なーんか相変わらず軍人みたいなことさせられるわねえ。まあ、払うもの払ってくれるんだったらいいんだけどさ?」
ムンベイは言葉の上でこそ納得していないような口ぶりだが、頼まれたことについては別段異存はない。報酬はきちんともらえるし、依頼主はガイロス帝国、窓口はなじみ深いシュバルツとなれば不安要素は一つもない。口元が緩みそうになるのだが、隣に座っている男はどうにも納得していないらしい。
「アンタねえ、いつまでぶーたれてんのよ。ガーディアンフォースだったんだからいいじゃないのよ」
「俺はそんなもんになった覚えはねぇ」
彼女に話を振られたアーバインは、本心から嫌そうな顔をしている。が、気に入らない仕事は引き受けない彼が大人しく椅子に腰を下ろしているのだから、なんだかんだでシュバルツが抱えている難儀な案件を手伝うつもりはあるのだろうし、そもそも彼だって義侠心のようなものは持ち合わせているのだ。
「誤解しないでほしいのだが、私は君たちを軍人扱いするつもりはない。あくまで今回は帝国からの要請だ」
書類上の依頼主は皇帝陛下本人だ。あの曇りない二つの目を思い出し、アーバインは腕を組んだまま呻ってしまう。
ムンベイはめんどくさそうな顔をしながらアーバインを小突いた。
「そうよ、アタシはともかくアーバイン、アンタはもともと傭兵みたいなもんだし、違うことと言えば今回の依頼主が帝国ってだけでしょうよ」
「傭兵じゃねえ賞金稼ぎだ」
「いいじゃないのどっちでも。報酬はもらえるんだし」
「……お前にゃプライドってもんはねえのか」
女ってのはこれだから。と、顔に浮かんでいるのをムンベイは歯牙にもかけなかった。
「帝国軍が腕を買ってくれるのよ? 運び屋冥利につきるってもんよ!」
この場合は窓口であるシュバルツの知り合いだからという理由なのであって、腕を買われた云々は一番の理由ではないのでは……と、アーバインは口には出さずに溜息だけを吐いた。何を言っても無駄だ。ムンベイが依頼を受けるとなれば自分もひっぱられるに違いない。
「しょうがねえな……」
「なーにもったいぶってんだか。 ルドルフの頼み、最初から断る気なんかなかったくせに、いちいちまどろっこしいったらありゃしないわよ」
「なんだと?」
シュバルツがさえぎるようにこほん、と咳払いをする。
「仲がいいのは結構だ。その調子で現地でもよろしく頼む」
仲がよくなんてないわい。
と、反論しようとするが、シュバルツが立ち上がって窓の近くへ歩いていくので二人はタイミングを逃してしまった。
窓の外はさすがに軍事基地の周辺とあって、目に見える範囲には集落の類はない。冬の冷たい荒野の、薄汚れたような茶色がただ広がっている。もの悲しい光景だ。
「先だっての騒乱でわが軍も共和国軍も・・・・・いや、軍人だけではない。多くの命が失われた。いまだ混乱の続く地域もあるが、人員不足の軍だけではどうにも手が回らない。退役した元軍人、予備役だった者、士官学校の候補生、そこまで手を回してもまだまだ足りない」
そもそもシュバルツがここにいるのも、本来の基地の長が別の任務に就かざるを得ないほど人手が足りないためだった。
「それで俺たちにお鉢が回ってきたってことか」
シュバルツは、窓の外を見つめたままうなずく。
「…………あんたらの事情なんか知ったこっちゃねえんだけどな」
とってつけた言い訳のようなことばをムンベイはひそかに笑った。
「しっかし、こんなときに火事場泥棒みたいなことする連中がいるなんて世も末ってことだね、戦争も騒乱も終わったってのにさあ」
呆れたように言いながら、ムンベイが脚を組み替える。と、アーバインが冷笑した。
「そいつらも食ってくためには必要なんだろうさ」
「だからって、何の罪もない村を襲撃するなんて許されることじゃないよ」
「その通りだ。このところガイガロス郊外に出没する盗賊団が次に狙うのはここだろう」
シュバルツが指差した地図上の場所は、この基地からもかなり離れた、小さな村だった。
「奴らが使っているゾイドの数はそう多くはない。 武装を改造したダークホーンが一体、小型ゾイド……おそらくヘルキャットとみられる機体が何体か。合計で四体から六体らしい」
「らしい、って何よ」
「すまない、こちらも情報が入り乱れて正確なことはわからんのだ」
「アンタが謝ることでもねえだろ。まあ、その程度ならなんとかなるだろうが……」
頭の中で算段をしているのか、アーバインが顎のあたりに手を持って行く。
それを見て、ああ、と、声を上げたのはシュバルツだった。
「言い忘れていたがトーマ・シュバルツ大尉も同じく任務にあたってもらう」
シュバルツ曰く、軍が何もしないように見られるのは体面が悪いらしい。それもそうだろうとムンベイたちは頷いた。要するに二人のお目付け役というわけだ。
「そうなの? へえ……しかも大尉ねえ……」
「形式だけの昇進だ。私と同じさ」
「その大尉殿は現地にいるのか?」
揶揄するようなアーバインの口ぶりに、兄であるシュバルツはこめかみのあたりを指で押さえながら眉を寄せた。
「……別の任務の報告を兼ねてこの基地での打ち合わせに参加するように言っておいたのだが、どうにもどこぞかで油を売っているらしいな」
壁の時計を気にするシュバルツは特に苛立っているようには見えないが、内心ではどうなのだろう。ほとんど感情的にならないタイプだろうな、とムンベイはシュバルツを評しているし、その評価は外れてはいないと思っている。
おそらく内心では時間通りに現れないトーマに腹を立てているだろうし、それ以上に心配もしているのではないだろうか。
なんと言っても兄弟なのだから。
推測したところで、詮無いことではあるのだが。
「失礼します」
その時、控えめなノックと共に女性仕官が部屋に入ってくる。
基地内で一番重厚であろうドアを静かに閉め、彼女はその場に直立した。
「どうした」
「トーマ・シュバルツ大尉から連絡がありました。これから基地へ帰投されるそうです。二時間ほどで到着予定と思われます」
「なるべく早く――いや……大尉には直接現地に向かうように言ってくれ」
「了解しました」
終始抑揚のない声で用件を済ませると、美しい敬礼をして彼女は立ち去った。軍人かくあるべし、という気概が全身からオーラのように発されている気がする。
どちらかというといい加減もとい、緩やかな気風の共和国軍になじみの深いアーバインとムンベイは、居心地悪いような身の引き締まるような、妙な気分になってしまう。
その二人の方を見て、シュバルツはわずかに眉を下げた。
「申し訳ないが、時間がそうあるとは思えんので、大尉とは現地で打ち合わせをしてもらえないだろうか」
「ないだろうかも何も、そうするしかねえんだろ?」
アーバインが立ち上がると、ムンベイもそれに倣う。
「じゃ、ちゃちゃっと片付けてこようかね」
気軽なムンベイの言葉にアーバインがげんなりとした顔になる。
「何が『ちゃちゃっと片付ける』だよ……お前はグスタフでシェルター引っ張ってくだけだろうが」
「アンタがささっと片付けてくれればあんな重くてでかいもん使わなくて済むんだけどねえ?」
万が一のために住民の避難用の頑丈なシェルターをグスタフで曳いていく。それがムンベイの役目であり、アーバインと、そしてトーマは盗賊団を叩くのが任務だった。
「その通りだな……難しいとは思うができれば襲撃前に叩いてもらいたい。住民の命はシェルターに避難してもらえば守れるが、家や畑はそうはいかない」
「簡単に言うぜ」
アーバインは笑う。とはいえ、一番じれったい思いをしているのはシュバルツ自身だろう。
将官の肩書が付き、一時的に基地の責任者となってしまった以上個人レベルでの行動は当然できない。とはいえルドルフの即位後は文民統制が徹底してなされ、将官のシュバルツですら勝手に兵を動かすこともできない。トーマについては、彼は一応まだ、裁量権の高いガーディアンフォース預かりなので今回出動が可能だった。それだけだ
「そんじゃ、行きますかね……弟に伝言あったら言っとくけど……どうする?」
寸の間、シュバルツはためらい、苦笑する。
「いや、結構だ」
「そりゃそうか。そろって軍人になるくらいだもん、仲いいわよね」
苦笑するムンベイに、珍しくシュバルツは、その目に戸惑うような色を浮かべた。
「……私は反対したんだがな」
「え?」
何やら拙いことを聞いたかもしれない。
ムンベイがそう思って謝ろうとすると、室内に小さなアラームが響いた。通信機のディスプレイが時刻表示と共に点滅しているのを見て、シュバルツはアラームを止める。
「すまない、定期連絡の時間だ。では、よろしく頼む」
半ば追い出されるようだったと思えないでもない……と、ムンベイはグスタフの操縦席で考え込む。そんなに妙なことを聞いたとは思えないし、あの兄弟の仲が悪いというのも考えにくい。とすれば、
「ねえ」
「なんだよ」
アーバインのライトニングサイクスに通信回線を開く。ぶっきらぼうな返事は不機嫌なわけでも疲れているわけでもなく、この男の通常通りの反応だ。
「なんで反対したのかね?」
シュバルツはそのあたりの事情が今も引っかかっているのではないかとムンベイは推測してみる。しかしそもそも何故兄は弟の志願に反対したのだろう。シュバルツ家と言えば代々軍人を輩出してきた帝国きっての名家云々というのは当のトーマから耳にタコができるほど聞かされている。軍人にならないことを咎められるのならまだ理解できるが、その逆というのはどういうことなのだろう。
アーバインは眠そうに大あくびをした。
「知らねえよ。向いてねえとでも思ったんじゃねえか?」
「向いてないのかしら……アンタはそう思うの?」
ノイズ交じりに笑い声が漏れ聞こえる。
「考えてることがすぐ顔に出るやつは軍人どころか賞金稼ぎにも向いてねえよ」
「ああ、そりゃそうだ。バンにはつっかかっていくし、今日は基地に戻らないし……悪い人間じゃないと思うんだけどねえ」
例の騒乱時は行動を共にしていたのだが、どうもトーマは直情的で熱くなりやすく、それがミスにつながることも少なくないように見える。根が素直でまっすぐと言えば聞こえはいいだろうが、確かに軍人に向いているかと聞かれると、自信を持って「向いている」とは言いづらい。
「向いてないのかしらねえ……」
「さあな……兄貴のほうはその辺よくわかってんだろうな」
そりゃあ、同じ家に生まれて同じ家で育った兄弟なのだから、と、言おうとしたムンベイは思わず笑い声をこぼしてしまった。
「んふふ」
「……なんだよ気色悪い」
呆れ交じりの返答にムンベイは眉を吊り上げた。
「失礼ねえ。……ただ、あの二人にもこーんなに小さい頃があったのよねえ、って思ったらなんか笑えてきて」
こーんな、と言いつつ自分の腹のあたりの高さで手のひらをひらひらさせるが、音声通信のみのアーバインには伝わるはずもない。もっとも、仮に映像で見ていたとしてもアーバインは何の興味も示さなかったに違いない。
「余裕だなムンベイ。足ひっぱんじゃねえぞ」
これ以上くだらない話に付き合うつもりはない、と言わんばかりに、アーバインは通信を切ってしまった。
「こっちの台詞だっての!」
悪態をついてもすでに相手には届きはしない。 ムンベイはオレンジ色のキャノピー越しに広がる冷たい荒野の先を見遣った。目的地は、まだ見えない。
3
兄であるカール・リヒテン・シュバルツが、ガイロス帝国士官学校への入学を決めたとき、弟のトーマはまだ七歳だった。
小さなトーマが寮生活のために荷造りをする兄の後ろをちょろちょろとついて回ったり、手伝いにもならぬ手出しをするさまは微笑ましくもあったが、一方でその顔に寂しさと悲しさが浮かんでいるのも事実だった。優しい兄が長期間家を空けることを理解はしていても心情的に納得はしていないらしいトーマは、結局兄の出立の前日にちょっとした騒動を起こしてしまった。
「ぼっちゃまー!」
「トーマぼっちゃまー!」
使用人たちはほぼ総出で邸の中と庭を捜索している。トーマは外よりも部屋の中で遊ぶ方が好きな子供なので、邸の外には出ていないだろう。という意見が全員の間で一致している。とはいえ帝国屈指の家柄であるシュバルツ家の敷地は内も外も広大なだけあって、ちょっとやそっとでは小さな子供一人見つけられないのが事実だった。
短い夏も終わりにさしかかる頃だけあって、日暮れの庭は肌寒い。 父は執務からまだ帰らず、母は邸内の捜索に加わっている。 十五歳のカールは庭を歩き回りながら、弟のふわふわとしたくせ毛を探していた。
「トーマ! どこに行ったんだ!」
こんな面倒をかけるような弟ではなかった。 出来が悪いとか、親から愛されていないわけでもない。とはいえことあるごとに兄のカールと比べてどうだのと評されているのは知っている。
同じ親から生まれたとはいえ別の人間なのだ、比較されて何か言われるのはカールだって嫌なのだが、比較された上に、いくらオブラートに包んでいるとはいえ「兄よりも出来がよくない」と言われるトーマはなおのこと不愉快だろう。まだ子供だから
わからないと思っているのかもしれないが、そういう悪意に対して最も敏感なのは他ならぬ子供自身だ。
「トーマ、いるなら出てくるんだ。 怒らないから、ほら、夕食の時間だよ」
迷路のように入り組んだ、腰ほどの高さの生垣の間を練り歩きつつ弟に呼びかける。母が目をかけているバラの花壇、カールが昨年植えた百合の鉢、そして唐突にビデンスが植わっているあたりを通り過ぎようとしたとき、足元に小さな影を見つけた。
「お前、ここにいたのか」
トーマは小さな体をさらに小さくして、膝を抱えて座り込んでいた。黄色いビデンスの花に紛れ、泣き顔が夕日に照らされている。ここはカールが百合を植えるとき、誤って種の入った袋をトーマがばら撒いてしまったせいで、ビデンスの花が植わってしまった。兄の真似事をしようと勝手に倉庫から持ち出したらしいが、転んで袋の中身をまき散らして、挙句ひざをすりむいたトーマを咎める者は誰もいなかった。
ビデンスの芽が出てくると、母は笑いながら、「それならここはこのまま、トーマの花壇にしてしまいましょう」とその周りをレンガで囲った。その作業をカールも手伝ったのはまだ記憶に新しい。
トーマが腰かけているのは、そのレンガの枠の上だった。
「にいさん、」
「心配したぞ」
しゃくりあげるトーマの前にしゃがみこみ、カールは微笑みながら小さな頭を撫でた。くせのない直毛の自分とは違って、トーマの髪は巻き毛のようにふわふわとしている。赤ん坊のころは皆から「天使のようだ」とかわいがられていたものだった。
もちろん成長した今、かわいがられていないわけではない。トーマを探そうと躍起になっているこの屋敷の人間は、一人残らず純粋にトーマの身を案じて行動しているのだから。
「ほら、家に入ろう。みんな心配してる」
できるだけ穏やかに話しかけたつもりだったのだが、トーマは叱られるとでも思っているのだろうか、ぎゅうと目をつむって首を横に振り、拒否の意思表示をしている。
「誰も怒りはしないさ、ほら」
手を差し伸べてもトーマはそれを取らない。それどころか、兄の手から逃れたいかのように身をさらに編ませて後ろにのけぞろうとしている。
「何してるんだ、花壇の中に転がり落ちるぞ」
カールはいい加減、空腹でもあったし苛立ってもいた。それなのに一向に動こうとすらしない頑なな弟を、いっそ抱えて連れて行こうかと無理矢理両肩を掴んだところ、トーマは再び泣き出してしまった。
「なんで泣くんだ……」
とっさに手を放してしまったが、これでは埒があかない。 途方に暮れたカールはべそをかいた弟の顔をハンカチでぬぐう。涙と鼻水にまみれた顔が綺麗になると、トーマは少し落ち着いたのかしゃくりあげるのをやめた。
「なあトーマ、泣いても喚いても、僕は明日から士官学校に行かなきゃいけないんだ」
トーマは小さくうなずく。
「しばらく帰ってこないけど、父さまや母さまもいる。 寂しくはないだろう?」
再び、トーマはうなずく。やはり頭ではちゃんとわかっているのだ。カールは弟の肩を掴み、にこやかに言い聞かせようとした。
「だから僕がいない間、父さまがお仕事の間は、男のお前が家を守るんだ、いいね?」
すると再びトーマは泣き出す。
「だ、だからなんで泣くんだ?」
思わず動揺してしまい、カールはその場に座り込んでしまった。あぐらをかいた兄を、トーマは涙をいっぱいためた目で見上げる。
「みんな、ぼくにそういうんです。 にいさんがいなくなるから、そのあいだはちゃんとにいさんのかわりに、いえをまもれって。でも、ぼくにはできません」
「どうして?」
「だってぼくはにいさんみたいに、なんでもできない」
カールは何も言えなかった。
劣等感に押しつぶされそうな弟に、何を言えばいいのかわからなかった。
「ぼくは、にいさんとおなじにするのはむりです」
文武にすぐれ周囲からの期待も大きく、いずれは名門シュバルツ家の跡を継ぐことが約束されているとは言っても、カールはまだ十五歳の少年なのだ。弟に正しいことを説き、導く役目は彼には重すぎた。
それでも、泣き止まない弟を放っておくことはできない。
カールはトーマの小さな手を握る。
「……トーマ、できないできないと言ってる間は本当にできないし、だからできないんだ。自分だってできるって思えば、なんでもできる。あたりまえだ。おまえはこの僕の弟なんだから。僕みたいになれる。なれるさ」
「ほんとうに?」
「ああ、本当だ。僕が嘘をついたことなんてあったか?」
トーマが即座に首を横に振る。と、邸のほうから二人を呼ぶ声が響いた。
「ほら、みんなが探しにきてる」
屋敷の中をくまなく探しきったのだろう。使用人たちの声がだんだんと近づいてくる。
トーマは不安そうに兄を見上げた。
「おこられない?」
カールは弟の目じりに残った涙を拭いてやり、くしゃくしゃと頭を撫でる。
「怒られないさ。僕がちゃんと言ってやるから」
苦笑したカールは、弟と手をつないで歩き出す。
「にいさん」
「うん」
ぎゅうと手のひらを握りしめられる。見下ろしたトーマの顔は、泣き笑いのようだった。
「にいさん……がっこうにいってもがんばってください」
「うん、ありがとう」
士官学校を出て本格的に配属されたとなれば、家に戻れるのも今まで以上に稀になるだろう。トーマは、寂しがるに違いない。
なるべく、家には帰るようにしよう。 帰るときには、弟の好きなものを買って行こう。
「そうだ、トーマ、一つ頼みがあるんだ」
ふと思いついて、カールは視線を下げる。 きょとんとした顔の弟は頼みと聞くと少しだけ表情を明るくした。
「なに?」
「この前お前が作った――」
4
ナデルバルトという名の村は、深い森を抱く山のふもとに位置する小さな村だった。主な産業と呼べるほどのものはない。
山を切り開いた耕作地は狭く、例年厳しい寒さのため余剰分が出るほどの収穫も見込めない。
しかし、貴金属の加工に関しては昔から一定の評価を得ているらしく、日々の農作業の合間をぬって制作されたものは高値で取引されることもあった。とはいえ最近ではその技術を買われた者は帝都をはじめとする都会の工房に引き抜かれ、村に残った人々が日常何をしているのかというと、やはり細々とした農作業ばかりだった。
「遅い!」
ナデルバルトに到着したアーバインとムンベイを出迎えたのはトーマだった。
「いい気なものだな、いつ盗賊どもが襲ってくるかわからんというのに」
それもねちねちとしたお小言付きなものだから、二人とも呆れて物も言えない。
「アンタこそ基地の打ち合わせに顔も出さなかったくせによく言うよ!」
「自分の寄り道は棚に上げて他人に説教たあ、大尉殿はずいぶんといいご身分みてえだなあ?」
「そ、それはだな……」
ムンベイの指摘とアーバインの皮肉にトーマはぐっと言葉に詰まってしまう。
あの時点でトーマがいた場所のほうが、ムンベイたちがいた基地よりもナデルバルトに近い。おまけにムンベイのグスタフは低速な上に重いシェルターを曳いていたのだから遅く到着しても何の不思議もない。なので、アーバインとムンベイからすればトーマのお小言など言いがかりのようなものだ。
「り、臨機応変に行動することも軍人としては重要なことだ!」
「よく言うよ……」
げんなりとした顔を隠すことなくムンベイは肩をすくめた。
さすがに口には出さない、というか出せないが、軍人に向いているかいないかと聞かれれば、こうやって自分だけに都合のいいことを当たり前のように言うトーマは軍人には向いていないと言ってもいいのかもしれない。
「貴様たちが遅いからこの俺がこの通り、必要事項をまとめておいた」
都合が悪くなったと見たトーマは話を変えようとする。 ぺらりと差し出された紙切れには、何やら数字が書かれていた。
「必要事項?」
いまいち要領を得ないムンベイに、トーマはなおも苛立った顔を向けた。
「住民の数だ! シェルターに避難させるなら数が必要だろう!」
「ああ、なるほど。そりゃ……」
それはそうなのだが、その情報はシェルターを用意する前に必要なのであって、すでにシェルターが運び込まれた現時点で提示されてもどうしようもない。
「そりゃ、どうもね」
なんとなく断りづらくて、ムンベイはその紙切れをありがたく頂戴した。
・大人百六十七人
・子供 五十八人
・作業用ゾイド 三体
「けっこう子供が多いのねえ、ここ」
ムンベイが思わずそう言うのと同時に、アーバインは積み上げた枯草の陰からこちらを見ている子供たちに気が付いた。
「………ん?」
「あっ」
眼帯を付けた強面の男と目が合って、数人の少年少女たちはさっと身を隠す。
「なに? どしたの?」
「いや、そこにガキが」
そこ、と指差す方を見ると、確かに小さな靴を履いた足が見え隠れしている。
ムンベイは笑いながら声を張り上げた。
「出といで! このゴリラみたいな兄ちゃんは見た目ほど怖くないからさ!」
「誰がゴリラだ、誰が」
「アンタよアンタ。 そういう顔するから子供が寄り付かないのよ」
言うとおり、子供たちは姿を見せない。 ムンベイは苦笑しながら枯草の山に近づいていった。
ひょいと顔を出して覗き込むと、まだ十にも満たないくらいの子供が四人、怯えた顔をしていた。
「どうしたの?」
できるだけ柔らかい笑顔を作ってやると、四人の中で一番年上を見られる少年が口を開いた。
「あ、あのう、あの黒いゾイド、おねえちゃんたちの?」
黒いゾイド。 アーバインのライトニングサイクスだろう。
「あれ? あれはね、あのゴリラ兄ちゃんの」
この期に及んでなおゴリラと言うか。指差されたアーバインはもはや言い返す気も起きずに腰に手を当てて立っているだけだった。
一方の少年たちはというと、見知らぬ大人とはいえまだ話しかけやすそうなムンベイではなく、どう見ても関わりづらいアーバインが持ち主だと知って落胆と狼狽を隠しきれなかった。
「ゾイド、好きなの?」
尋ねてみると、四人そろって大きくうなずく。
ははん、とムンベイは目を細めた。
アーバインのライトニングサイクスは最新鋭機で、そこらに出回ってもいない。何しろあの研究所からいわばぶん捕ってきたようなものだからそれも当然だ。
見たこともないゾイドを見たいと思うのは子供も大人も同じだろう。 村に入る途中にも好奇心むき出しの視線をいくつか頂戴していた。 アーバインはさぞ居心地悪かったろう。
ムンベイはにこりと笑う。
「頼んでみてごらんよ? おねえちゃんがいっしょについてってあげるからさ?」
小さい頃の自分を思い出すようで放っておけなかったのだ。ゾイド乗りなんてやってる人間で、 ゾイドが嫌いなやつはいない。 アーバインだってそうだ。だから子供たちに見せてやらないわけはない。
「本当?」
「ほんとにみせてくれるの?」
「大丈夫だって!」
小さな手を引いて、ムンベイは子供たちを促した。居心地の悪いアーバインは、頼まれるのが嫌だったのか、それとも照れ臭かったのか、頼みこまれるより先に子供たちをライトニングサイクスのほうへと促した。
「微笑ましい光景だわねぇ」
満足そうに笑いながらアーバイン達を見送るムンベイと一緒に、トーマもぼんやりと同じ方を見ていた。
「でもこのあたりじゃディバイソンも珍しいんじゃないの? 見せてって言われなかった?」
共和国製ゾイドであるディバイソンを帝国領で見かけることはあまりないのではないか。同じ共和国製とは言っても輸送用ゆえいたるところでお目にかかるグスタフはこの際レアリティの問題外だ。
「……ああいう高速ゾイドが、子供は好きなんだろう」
察するに、トーマのディバイソンは不人気……とは言わずとも、ああして囲まれることはなかったらしい。
高火力で重装甲のディバイソンにも愛好家はいるとは思うが、子供にはまだわからないのだろうか。きっと足の速い男子が女子に人気なのと似たようなものだろう。それも少し違うか。ともかくムンベイはそう納得することにした。
「アンタも子供のころはあんな感じだった?」
「は? 何を突然……」
トーマは予想しなかった質問に目を丸くした後、怪訝そうに細めている。感情も豊かなら表情も豊かなことだ。
「いや、ゾイド好きが高じて軍人にでもなったのかな? って思って」
「はあ……馬鹿馬鹿しい」
嫌味なほどに長い溜息の後、トーマは胸を張った。
「我がシュバルツ家は代々栄誉ある軍人を輩出してきた。父も兄も生まれながらに軍人となることを定められていたようなものだ。ならば俺も軍人になるのが当然というものだろう! ゾイドの好き嫌いなど関係ない!」
一息に言い切ると、満足したようにトーマは口元を緩めた。
心なしか頬まで血色がよくなっている気がする。
ムンベイはそのエリート意識とも呼ぶべきかもしれない彼の自負に、呆れ半分に頷いていた。
「はあ、そりゃご立派なことで……あれ?」
ムンベイは首を傾げた。何か違和感があるのだ。
「でもアンタ確か、ヴァシコヤード・アカデミーに通ってたんじゃないの? それも飛び級で」
フィーネから聞いたことだ。ヴァシコヤードと言えば帝国の頭脳との評判も名高い名門中の名門校だ。生半可な実力で入学できるわけもないそのアカデミーに飛び級で入学したというのだからトーマは本来その方面が得意分野のはずなのだ。
「そうだよ、大体そのビークだって自分で開発したんでしょ? 別にそれが悪いって言うわけじゃないけど、なんでわざわざ自分が最前線に出てくるのさ?」
研究者なのだからわざわざ戦場に赴く必要もあるまいとムンベイは考えていた。もちろん、正式に卒業した後に軍属になったとあればそれは不自然ではない。が、仮にそうだったとしてもトーマの場合、兵器開発のような部署に配属されそうなものだ。なぜまたガーディアンフォースなんて、危ないところに……。
「関係ないだろう、そんなこと」
都合が悪いのか、トーマは苦虫をかみつぶしたような顔で地面を睨んだ。何があるわけでもない。むしろ、何もない。
ムンベイは追及をやめなかった。
「でも、変よ。だってアンタ、今は休学扱いになってるんでしょ?」
「なんでそれを、」
「フィーネ」
この名前を出すと大人しくなるのは少し前から変わらない。涙ぐましいようで複雑な気持ちになるが、ムンベイは食って掛かろうとしたトーマをけん制した。
「フィーネが言ってたんだよ。休学ってことはまた戻るの?」
「お前には関係ない。……俺はビークの調節をしてくる」
気まずそうに吐き捨てると、トーマはディバイソンの方へ大股で歩き去った。
「変なこと聞いちゃったかね?」
半ば確信しつつムンベイはため息を吐いた。アーバインは相変わらず子供たちに囲まれている。僕も乗せてほしい、馬鹿言ってんじゃねえ。そんな応酬が冷たい風に乗って運ばれてくる。
それを聞くともなく聞いていたムンベイは、背後から声をかけられた。
「あの、もしかして、軍から派遣された賞金稼ぎの方でしょうか?」
「そうだけど?」
振り返ると、ムンベイよりも二歳ほど年下に見える少女が立っていた。ざっくりとしたストールを羽織り息を切らせている彼女は、赤く染めた頬のまま安心したように笑う。
「よかった……あ、私、エルマと申します。村長の妹です」
「ああ! そうなの、あたしはムンベイってんだ。よろしく――妹?」
見た限り、エルマはせいぜい二十歳前後。娘ではなく妹。 ということは、村長もずいぶん年若いに違いない。
「すみません、兄は足が悪くて、その、みなさんをお迎えに上がれず……」
ムンベイの驚愕を勘違いしたのだろう、エルマは瞼を伏せて詫びた。 慌ててムンベイも両手を振る。
「ああ、そうじゃないのよ! ずいぶん若い村長さんなのねって思って」
ムンベイの故郷もそうだったし、二年前の旅の道中に立ち寄った街やコロニーも、大半は老人世代が代表を務めていたものだ。
エルマの表情に陰りが見える。
「あ、はい……昨年父がなくなりまして」
「あ、そ、そうなの……それは、」
ご愁傷様……。ムンベイは消え入りそうな声で辛うじてそれだけ述べると、居心地の悪さに頬を掻いた。
父を亡くし、おそらく家長である兄も足が悪いとなれば苦労も多いことだろう。そこにこの、盗賊団の騒ぎである。同情するつもりはなかったが、さすがに気の毒だと感じてしまった。
エルマは気丈にも明るく振る舞って見せる。
「私たちが避難できるシェルターを運んできてくださったと聞きました。よろしければ、兄に詳しいお話をお聞かせ願えませんか?」
ド田舎の村娘にしては、というと失礼だが、エルマはなかなか育ちのいい娘に思えた。
「そりゃもちろん。案内してくれる?」
「はい!」
ムンベイはライトニングサイクスの方へ声を張り上げた。
「アーバイーン! あたしは村長さんのところに行くからー!」
「は⁉ てめ、ちょっ……」
相変わらず子供たちに捕まっているアーバインはすぐには行動できない。それを放ったまま、ムンベイはエルマと共に歩き始めた。
「……いいんですか?」
「いいのいいの。ああ見えて子供好きなんだから」
適当な言い訳と共に手をひらひらとさせながら、ムンベイは村の一番奥まった家を目指す。そこが、エルマと兄、テオの住む家だ。
道中、ムンベイはエルマから色々なことを聞いた。母親はエルマたちが小さい頃に亡くなったこと。父親が亡くなったのは、先の一連の騒動が原因だったこと。兄は手先が器用なので、足が悪くても彫金細工でなんとか生計を立てられるということ。
その兄は、かつてヴァシコヤード・アカデミーに在籍していたこと。
5
村の子供たちにさんざ懐かれたアーバインは、ムンベイがエルマの家に招かれて三十分ほど経った後にようやく姿を見せた。
「ひでえ目にあったぜ」
言うほどうんざりしているように見えないのは、なんだかんだで彼も子供と接することが嫌いでも苦手でもないからだろう。
そうでなければバンやフィーネ、そして彼らよりもさらに幼かったルドルフと旅をするなんて到底できなかったに違いない。と、ムンベイは確信している。
「ごめんなさい、あの子たち、ゾイドが好きで……。あんなに珍しいゾイドを見て、きっとはしゃいでしまったんだと思います」
「あ、いや、別にいいんだが」
申し訳なさそうに眉を下げるエルマに、アーバインはたじろぐ。この男、どちらかというと子供よりも女のほうが苦手なのかもしれない。
エルマは三人分の茶を淹れ終わると、夕食の支度をすると言って応接室を出て行った。
兄妹二人だけで暮らしているとはいえ、さすがに村長の家は広く、過ごしやすい造りになっている。
ムンベイはエルマのお茶を一口飲むと、対面に座るテオの顔を見つめた。
「それで、トーマはいないけど、いいの?」
明日以降のことについてムンベイとアーバインは、村長であるテオ・ローベルの話を聞くことになっている。が、ここにトーマはいない。大方ディバイソンのコックピットに籠って何かしているか、あるいは何もしていないのだろう。
テオ・ローベルは妹のエルマに似た、優男風の外見をしている。線は細いが意思の強そうな目は、村長の任を背負っているからだろうか。
その目を細めてテオは苦笑した。
「あいつとは先に少し話しました。アカデミーにいたころとはずいぶん変わって……」
「なんだ、アンタ、あいつのこと知ってたのか」
「ええ、僕もアカデミーに在籍していたんです。 脚がこの通りになってしまったのと、村長をやらないといけないので休学していますが」
そう言って笑うテオの右足は、膝の関節を含めてそれから下が全部、金属の義足になっていた。
アーバインは無言でそのつま先を見ている。 どうしてそんなことになったのか、聞いていいものか逡巡しているようだった。
テオは、慣れているのだろう。聞かれる前に口を開く。
「旧プロイツェン派のテロで、ヴァシコヤード・アカデミーの研究室が狙われました。僕は片足で済みましたが、友人が何人か……」
「……そりゃ、」
災難だったな、と、軽く言えるものなのかよくわからない。
テオの口ぶりから、彼の友人の数人はそのテロで命を落としたのだろう。生き延びることができたのなら、それは確かに「片足で済んだ」のかもしれない。が、それは本人だから言えることであって、アーバインやムンベイからすれば、片足の喪失はあまりに大きな被害としか言えない。
沈黙に支配された場を、テオは笑顔で破ろうとした。
「トーマは、もっと運がよかった。あいつはその日、たまたま建物の外にいたんです。たしか兄上が迎えに来るのを確かめに行ったんじゃなかったかな……」
「へえ……」
そんなことはつゆ知らず、ムンベイもアーバインも目を丸くして驚いた。
トーマは知らずのうちに命拾いしていた。それは確かに運がいいと言えるだろう。
しかし、兄と待ち合わせている間に研究室が襲撃され、友人数人を亡くし、テオも大怪我を負い。
トーマはそれを、どう感じただろうか。もちろん近しい人の死を悼む気持ちや、テオに対するなんらかの、同情のような感情もあっただろう。それ以上に、彼は自分の不甲斐なさだとか、罪悪感に打ちひしがれたのではないだろうか。
ムンベイはふと、テオに向かって尋ねてみることにした。
「あの、どうしてトーマがアカデミーを休学して、軍に入ったのか、知らない?」
「軍に?」
「おい、」
アーバインが咎めるような視線を投げるが、ムンベイはひかなかった。
「だっておかしいでしょ? 研究者だったのに、それをなげうって最前線に出てくるなんてさ。兵器開発専門で、ずっと帝都のラボにいるとか、そういうんならあたしだってわかるけど」
テオは顎に細い指を当てて少し考え込む。
「それは……僕にもよくわかりません。でも、確かにあの事件から一か月ほどで、あいつは軍に入りました。何か関係があるのは、事実だとは思いますが――」
「テオ、入るぞ」
そのとき、当の本人が玄関のドアを無遠慮に開けて入って来たらしい音が聞こえた。不自由なテオに余計な手間をかけさせたくないのだろう。
「トーマ、ここだ! 応接室! お二人もいるぞ!」
ああ、と快活な声でテオの呼びかけに答えたトーマがすぐに来ると思いきや、エルマの声がそれを遮る。
「あ、すみません大尉さん。手が離せなくて……すぐにお茶をお持ちしますね」
「いえ! お構いなく! 食事の支度でお忙しいでしょう? いやあとてもいい香りですね」
「え? ええ……」
エルマが慌てて出迎えたらしいが、トーマは鼻の下でも伸ばすのに一生懸命なのだろう。なにせあの男、惚れっぽいことにかけてはずば抜けている。
何やら不穏なものを感じてしまい、ムンベイは思わずテオに耳打ちしてしまった。
「妹さん、あぶないんじゃないの?」
「ああ、それなら大丈夫です。エルマは……」
テオがこっそりと教えてくれたことを聞いて、ムンベイもアーバインも驚きつつもトーマに同情せざるをえなかった。いや、別にトーマがエルマに対して明確な思慕の念を抱いているとは思わないのだが。
そうこうしているうちにトーマが応接室のドアを開けてずかずかと入ってくる。
「話は済んだのか?」
開口一番にそういうことを聞くので、テオは苦笑、ムンベイとアーバインはため息を吐くしかできなかった。
「済んだのかもなにもあんたも一緒じゃないとだめに決まってんでしょうが……」
「そうか、やはり俺がいないと駄目なようだな!」
違う、そうじゃない。
と、否定するのももはや面倒で、ムンベイとアーバインは聞こえよがしにため息をついた。
苦笑いしていたテオがきゅっと顔を引き締め、口を開く。
「実は、昨日の時点で盗賊団からの要求が来ています。内容は、冬を越せるだけの食糧と、金銭。明日までに用意できなければ村ごといただく」
「とんでもない要求してきたもんだね」
「ええ、その通りです。そんなもの、呑むわけにはいきません」
テオの力強い言葉は、さすがに村長だけあった。
「どのみち村の財産全部明け渡せって言ってるのと同じようなもんだろ。俺らが逃しちまえば、また別の村を襲うに違いねえ」
アーバインの推測にトーマも頷く。
「これ以上やつらの蛮行を許すわけにはいかん! いいか、絶対にここでやつらを一網打尽にするぞ!」
相変わらず仕切りたがるトーマをもう誰も止めはしなかった。
呆れつつも、さすがは軍人として一応の教育を受けただけあって、てきぱきと迎撃のための配置だとか村民の退避場所だとかを指示している。
知識もあるし、飛び級するくらいだから頭もいいのだろう。
ムンベイはトーマの、案外がっしりとした顎が檄を飛ばすのをぼんやり見ていた。
軍人になりたかったのだろうか?
だったらアカデミーに入学したりするだろうか?
ムンベイが考えたところで詮無いことだが、迎撃準備の話よりもそちらに意識が向いてしまうのを、止められなかった。
6
トーマがヴァシコヤード・アカデミーに入学すると、彼を取り巻くものは一変した。
飛び級だったものだから、周りは全員自分よりも年上。人見知りでもあったトーマは、周囲とはなじめずに孤立した。
けれど本人としては孤独なつもりはなかった。
別に、ともだちごっこをしたくて進学したのではないのだから、一人ぼっちでもかまわない。
そう言い聞かせるようにしていたので、自分から誰かに話しかけることもなかった。
寂しくなかったというと嘘になるかもしれない。
だけどつらくはなかった。
進学すればいいじゃないか。お前は頭がいいんだから。
兄がそう褒めてくれたのだ。
だから逃げ出すなんてことはできない。逃げ出したら、きっと兄さんは僕に失望する。
そういう思い込みがあったせいか、あったおかげというべきか。 とにかくトーマは一日も欠席せず、アカデミーに通い続けることができた。幸い教授陣からは目をかけられていたし、他の学生からネガティブな感情を向けられることもなかった。親しくつきあうことも皆無だったのと同じように。
それはともかく、入学から半年ほど経ったある日、トーマは本格的にとあるプログラミングに取り組み始めていた。
研究課題は「人工オーガノイド」について。
ゾイドと融合することでその性能を飛躍的に向上させるオーガノイドの確保は帝国、共和国の双方にとって死活問題であったこともあり、かつてはオーガノイドを巡って多数の犠牲者を出した事件も多くあった。
人工のオーガノイドがあれば、そんな悲しい事件は起こらなくてすむ。それに、量産が可能なシステムを構築できれば圧倒的な戦力を保持し、抑止力として使うことができる。
こうしてトーマは人工オーガノイドの研究を進めた。
これがあれば兄は自分を見直してくれるに違いない。
トーマは日夜を問わず開発に没頭していた。一人きり残されたコンピュータールームで、背後に人が立っても気づかないほどに。
研究を始めて一年ほどが経った。 共和国との戦争も終わり、オーガノイドを必要とするような状況ではなくなったが、トーマは相変わらず人工オーガノイドの実現に心血を注いでいた。
完成とは言えずとも、実用レベルまでもう少しでこぎつけられる。そんな折だった。
その日もトーマは深夜まで大学に残ってうんうん唸っていた。
どうしても、一か所だけ上手くいかないところがある。何をどう書き換えても動かないアルゴリズムを相手に、正直いらだってもいた。空腹や眠気も一因だったかもしれないが、キリの悪いところで中断したくはない。
だから遅くまで一人っきりで格闘していたのだが、凝り固まった考えのためか他の要因のためか、問題は一向に解決しない。
そのとき、背後から見知らぬ腕が伸ばされてくる。
「ここ、間違ってる」
節くれだった細い指先がキーボートを軽快に操作すると、あっという間にプログラムが走り始めた。エラーチェックの結果を示す完了音が鳴り、完成を知らせてくれる。トーマは今起こった出来事を認識できずにぽかんと口を開けるばかりだった。
「あ、ごめん、勝手に書き換えて」
「いえ……」
振り返った先に立っている、 突如現れた人影はトーマよりも少し年上の、優しげな面立ちの男だった。それがテオだ。
研究室で仮眠をとっていたテオは、コンピュータールームが未だに明るいことに気が付いて様子を見に来たらしい。
「そうしたら、君だ。トーマ・シュバルツ君? ……って呼んでいいのかな?」
「……はい」
兄よりは年下だけれど、自分よりは年上。今まで接したことのない年代の相手に、トーマは緊張していた。
「そんなに警戒しないでくれ」
苦笑するテオは、おそらく悪い人間ではないのだろう。それはわかるのだが、どういうふうに接していいのかトーマにはよくわからない。
「あの、ありがとうございました」
「ううん、それじゃ――」
そう言ってテオが立ち去ろうとすると、ぐうう、とトーマの腹が鳴る。
そういえば昼から何も食べていなかった。と、トーマが恥ずかしさに身を小さくさせるのを見て、テオは目を丸くしたあとに大きく噴出した。
「ちょっと待ってて、今お湯を沸かすから」
トーマはテオに連れられて、彼の所属する研究室に来ていた。
腹が鳴ったのは恥ずかしかったのだが、空腹なのは否定できなかった。
「あの、すみません……」
「気にしないで。こう言っちゃなんだけど、もうすぐ賞味期限が切れそうなのもあるから。食べてくれると正直助かる」
そう笑いながらテオが分け与えてくれた買い置きの食料品と、手ずから入れてくれたコーヒーをトーマはありがたく頂戴することにした。
「砂糖はとミルクはいい?」
「……大丈夫です」
「そう?」
強がってブラックで飲むのだが、テオはたっぷりの牛乳を自分のマグカップに注いでる。それを見ると、トーマは少しだけ後悔した。兄はいつもブラックで飲んでいるものだから、大人は皆そうなのだと思い込んでいたのだ。
テオは一息つくと、トーマの顔を見据える。興味津々な表情の中に、親しみやすさのようなものがあった。
「僕はテオ・ローベル。学年は一緒だと思う。あんまりこういう言い方、気に入らないと思うけどさ、君は話題だよね」
「はあ……」
何の話だかわからないが、テオはトーマに興味を持っているらしい。
「飛び級してきたのもそうだけど、人工のオーガノイドを作ろうとしてるって。みんな驚いてるよ」
「え、」
意外だった。てっきり飛び級してきたことをあれこれ言われるものと思っていたが、むしろテオが、あるいは周りが注目しているのはトーマの研究内容らしい。
認められたのだろうか。
かあ、と顔が熱くなるようで、トーマはコーヒーのマグカップを握りこむ。
「別に、そんなに大したことをしてるわけじゃないし、大体できるかどうかもまだわからない――」
「できるさ!」
力強い声に顔をあげると、テオは輝くような瞳でトーマを射抜くように見つめていた。
「例え人工でも、オーガノイドを使えばゾイドは動く。スリーパーなんかとは比較にならないほどの強さを備えたままで、だ。それが実現すれば人間は戦争に行かなくてすむ。死んでしまう人だって少なくて済むんだ」
テオは、誰かを亡くしたのだろうか。
「あ、す、すまない……つい興奮してしまって」
気圧されたトーマが二の句を告げずにいると、テオは照れ臭そうに口元を覆った。捲し立ててのどが渇いたのか、コーヒーを一息に岬ると、テオは再びトーマに向き直る。
「君の組んだプログラム、少し見ただけでもどれだけすごいものかわかったよ。ずるい申し出だとは承知しているけど、頼みがあるんだ。僕は無人兵器の研究をしているのだけど、プログラムを共同開発させてもらえないかな」
「それは……」
言い淀んでしまう。確かに、人工オーガノイドと無人兵器の制御システムには、設計思想という点で共通するものは多いと思う。二人で開発すれば負担も減るし、よりよいものができるかもしれない。
けれど、信用してもいいのだろうか。と、いう不安が一つ。
もう一つは、過大評価されているような居心地の悪さだった。
黙り込んだトーマに、テオはそっと微笑んだ。
「もちろん今すぐに返事が欲しいわけじゃない。いつでもいいから、もし一緒に研究してもらえるのなら、またここに来てくれ」
そして、カップを掲げ歯を見せて笑う。
「でも、コーヒーを飲みにくるだけでもいいけどね」
礼を述べて研究室を出たトーマは思い悩んでいた。
優秀な兄と比べられ、不出来な自分を恥じるばかりだった過去。そこから逃げるようにして入学を決めたヴァシコヤード・アカデミー。本当に自分は、人から評価されるような人間なのだろうか、そんな技量があるのだろうか。
やさしい兄は「お前はそういう才能があるのだから」と言ってくれる。けれどそれがやさしさゆえの嘘でないとどうして言い切れるだろう。
「……いやなやつだな」
家族まで疑ってしまいそうな自分が恨めしくなる。自分にも何か、自信を持てるようなことがあればいいのに。これまでに何度も繰り返した問答を、また頭の中で広げてしまう。
――マイナスの感情に引きずられるな。
兄の言葉を思い出した。
――おまえはこの僕の弟なんだから。
こんな僕でも、誰かに認められることがあるのでしょうか。
寮の自室に戻ったトーマは、机の上の小さな影に目をやった。
カラフルに色分けされた、ヘルキャットのおもちゃ。 ただの置物だったものを改造し、ぜんまいで歩行できるようにしたのは自分だ。
――これ、お前が作ったのか!?
今の自分よりも少し幼い兄が興奮したように目を丸くしている。
――すごいなトーマ!
ああ、あれが最初に褒められた作品だった気がする。
そっとヘルキャットに触れると、わずかにぜんまいが巻かれていたのか、二三歩進んで、すぐに止まった。トーマはなんとなくひっくり返して内部のチェックを始めてしまう。歯車のかみ合わせには問題ないが、摩耗が激しい。 今度、新しい部品を買ってきて交換しよう。
トーマは大きな口を開けてあくびをすると、ベッドの中にもぐりこんだ。眠りに落ちる前、そっと決意をしながら。
明日、テオの研究室へ行こう。
7
夜更けの村は寒さの厳しさのせいもあって、外は静かなものだった。テオから貸し出された防寒着をはおり、アーバインは村の外の小高い丘へと足を伸ばしている。散歩などではもちろんない。盗賊団が夜襲をかけるのではないかという懸念からの、見張りのようなものだ。
向こうはおそらく、アーバインたちが用心棒としてやってきたこと、すなわち、テオが彼らに屈するつもりがないことなどとっくに把握しているだろう。ならば力ずくで村を制圧する可能性は高いはずだ。
雪が降るほどではないが、冷たく澄んだ空には幾多の星が煌いている。星見を楽しむほど風雅ではないし、そういう場合でもない。
「さすがに、むやみに近寄ってくるほどバカじゃねえか」
物音の類は一切ない。 アーバインは眼帯のレンズを廻し、暗視モードをオンにする。
辺りに怪しい影はなかった。
夜間に襲撃されないのはありがたいが、明け方まで油断はできないだろう。
「なんだ、アンタまだ起きてたのか」
寝床を提供してくれているテオの家に戻ると、エルマが出迎えてくれた。もう日付も変わるだろうに、アーバインが呆れていると、彼女はこう言う。
「兄と大尉さんのお話につきあってたらこんな時間で。そろそろ休ませていただきます」
ムンベイはすでに二階の客室で寝息を立てているらしい。
「ああ」
「兄たちはまだ起きているみたいです。 あ、兄の部屋にお茶を用意していますので、よろしければ」
「ああ、わかった」
では、おやすみなさい。そう言って階段を上って行くエルマを見送ることなく、アーバインは暖を求めてテオの部屋へ向かった。ノックをすると、穏やかな声に応じられる。
「どうぞ」
暖炉の前で、テオはロッキングチェアに、トーマは厚い絨毯の上に座り込んでいた。テオは何も持っていないが、トーマは何か、小さなパーツの塊相手に格闘している。
「何してんだ?」
「修理だ。見てわからんか」
顔も上げずに呆れた返事をするトーマは、確かに小さなおもちゃの人形を修理しているらしかった。人形、といっても人型のではない。 ゴルドスだろうか。四足歩行のゾイドのぜんまい仕掛けのおもちゃだ。
「めずらしいもん持ってんだな」
こどもがよく持っている、かなり普及しているタイプのおもちゃだ。アーバインにも覚えがある。戦争中は軍のマーキングが入ったものがよく売れたが、今はどうなのだろう。
「村のこどものです。 壊れていたのを直してくれと頼まれていたのを忘れていまして」
「へえ」
アカデミーに通っていた村長で、年若く親しみやすければそういう要望もあるのだろう。直しているのはトーマだが。
「トーマの方がこういうのは得意ですから」
「褒めたって何もでないぞ」
「知ってるよ。あ、紅茶なら僕が、」
「いや、あんたは座っててくれ」
苦笑するテオとトーマは仲がいいように思えた。アーバインは無理に立ち上がろうとするテオを制し、保温ポットの中から紅茶をカップに注いだ。
「棚にブランデーがありますよ」
テオが示した飾り棚には確かに琥珀色の瓶がある。今夜は冷えることだし……と、アーバインは申し出をありがたく頂戴することにした。
「悪いな、もらう」
「どうぞ。……外は冷えたでしょう?」
「ああ。だが連中、まだ近くには来てねえらしいな」
「しかし明け方まで気は抜けん」
ねじ回しをきりきりと回しながら、トーマが重い調子で口にした。アーバインもテオも同じように、緊張をにじませた表情になる。
「だろうな……」
「すみません、お二人にはご負担をかけます」
「これが軍人としての仕事だからな」
何でもないように言って、トーマは工具を床に置いた。
「ほら、できたぞ」
テオの手に渡ったゴルドスのおもちゃは、ぎいぎいと小さな音を立てて四肢を前後に動かしている。 左の掌の上で数歩歩ませると、テオはにっこりと笑った。
「ああ、ありがとう。 やっぱりトーマに頼んでよかった」
「たかがこれくらい」
トーマは珍しく照れ隠しのように口をとがらせている。からかうようにテオは棚にもたれているアーバインのほうを振り返った。
「アカデミーにいたころ見せてもらったんですが、関節の一つも動かないようなただの置物を、トーマはぜんまいで動くおもちゃにしてたんです。それも、こんなに小さなころに」
こんな、と言いながら、テオは自分の胸のあたりに手をやって背丈の小ささを示そうとする。 昼間も誰かがそうやっていたような気がして、アーバインは奇妙な感覚だった。
「別に、そのくらい普通だ」
トーマは居心地が悪そうな顔で工具を箱にしまっている。案外丁寧な手つきなのは、やはりそちら方面のほうが性にあっているからだろうか。
テオは苦笑した。
「そんなことない。トーマ、君はもっと、自信を持つべきだと思うけど」
「俺は自分を誇りに思っている」
真面目くさった顔で言うのは家名のことだろう。そんなことはテオにだってアーバインにだってわかったし、トーマだってテオが何を言いたいのかわかっているのだろう。そうでなければ、ああも気まずそうな顔などしないに違いない。
「見張りに行ってくる」
「あ? ああ」
おもむろに立ち上がると、トーマは工具箱をテオの傍らのテーブルへ戻し、そのまま外へと出て行った。
まだ思春期の中にいるとでも言うのだろうか。 アーバインは少し鼻白んでしまいそうだった。
テオはやれやれと言いたげにため息を吐いた。
「アーバインさんもお休みになりますか」
もうすぐ日付が変わる。
「あー……いや、もう一杯飲んでいく。 アンタもどうだ」
「そうですね、今日は冷えますし」
アーバインがポットの紅茶を注いでやると、テオは恐縮しきった顔で頭を下げた。
「すみません、お客人に」
「構わねえよ。やれるやつがやりゃいいんだ」
適材適所ってやつだな、と、言って、何か違うような気がしないでもない。 テオは、そうですねと同意してくれたが。
「……この脚、冬は接続部が冷えてかなわないんです」
膝のあたりを撫でながら苦笑されて、アーバインはあいまいにうなずいた。
「だろうな」
感覚としてなんとなく想像はつくけれど、実際に脚の先に金属の何かをつけたことはないのであれこれ言う気にはなれなかった。
テオは少しだけ強い目をする。
「自分がこうなってみて初めて思うんですが、もう少しいい素材で作れそうなものじゃないかと。……トーマにこの話をしたら、そうかもしれんな、としか言ってくれませんでした。昔はあれこれ話し合っていたのに、もう工学に興味はないのかな……」
さびしそうな目をしているその理由はなんなのだろう。テオは友人の態度の変わりようを嘆いているのか。
まあ色々事情もあるに違いない、 と、 アーバインが柄にもなく励ましの言葉をかけようとしたそのとき、
「……何か聞こえなかったか」
「え?」
テオには聞こえなかったようだが、アーバインの耳にははっきりとその音が聞こえた。
まずい、と思った時にはすでに遅かった。
まず大きな振動、追いかけるようにして、風切りの音と近くに着弾したらしい轟音。
砲撃されている。
「アーバインさん!」
「村の外だ! 家には当てねえつもりだ!」
盗賊たちが狙っているのは村の財産であり、焼け野原ではない。今のはただの脅しだろう。 アーバインはカップや酒瓶をテーブルの上に置くとドアを開ける。駆けだす前にテオを振り返り声を荒げた。
「俺は出る、アンタは妹とムンベイと一緒に避難しろ!」
「わ、わかりました!」
アーバインがライトニングサイクスの元へとたどり着くと、ディバイソンからの通信を知らせるアラートがけたたましく鳴り響いていた。
「遅いぞ!」
案の定の怒鳴り声は無視してアーバインは状況を尋ねた。
「敵はどこだ」
「貴様の正面右手の林の中から砲撃している。中距離砲撃用の武装を付けているなんて聞いていないぞ!」
トーマの言葉の合間に、振動や砲撃音が聞こえてくる。どうやらすでに林の中で交戦しているらしいが、シュバルツの話にあった通り護衛に複数のヘルキャットがいるのならば、高火力とはいえ鈍重なディバイソンでは不利だろう
「俺に言うな」
おそらく主力は中距離砲撃武装を施したダークホーン、そしてそれを援護するヘルキャットが複数。光学迷彩をつかっているかもしれない。
「今から向かう。 雑魚は俺が引き受けるから、てめえは親玉をぶっ潰しちまいな」
懐に飛び込んで格闘戦に持ち込めばディバイソンに分があるだろう。軽量機体の高速ゾイドであるライトニングサイクスではダークホーンの重装甲に打ち負けかねない。
「だったら早くしろ!」
「へえへえ。……いくぞ、 サイクス」
軽やかな雄叫びを上げ、ライトニングサイクスは漆黒の体を闇夜へと走らせる。
断続的な砲撃にさらされ、トーマは焦燥を感じていた。地響きのような音と振動は、うっすらと覚えている、忌まわしいあの事件を思い出させる。 今まで忘れそうになっていたことなのにどうして突然思い出したのだろう。
8
テオの所属する研究室にトーマも入り浸るようになるのにさほどの時間はかからなかった。面倒見のいいテオのおかげもあってかトーマは研究室の面々に受け入れられ、可愛がられたし、互いの研究の成果を見せ合うのはとても楽しかった。
「なあ聞いたか、テロの話」
誰かがそう言いだしたとき、トーマは帰り支度を始めていた。
明日は久しぶりに兄が任地から帰宅する。 ならばとトーマも寮から家に戻ろうと伝えたところ、カールは「大学まで迎えに行ってやる」と言ってくれた。もうそろそろその時間だろうかというときに、なにやらきな臭い話題が出てトーマは少し嫌な気持ちになった。
「ああ、知ってる。帝都のそこかしこで爆破テロがあった話だろう?」
「そりゃそうなんだが、今や帝都の外でもテロや襲撃事件が相次いでるって話だ」
「何のために?」
確か先週逮捕された実行犯の一人は旧プロイツェン派の過激組織員だったと記憶している。まさか愉快犯だとか、何の考えもなしにテロ行為を行っているわけもあるまい。
おそらく帝都からその外へと警備の目を向けて、クーデターでも企図しているのではないか。
トーマが当て推量を口にすると、その場の面々は口々に「なるほど」と感嘆した。
「さすが、軍人家系だと違うなぁ」
褒めてくれているのだろうけど、「軍人」という言葉を、「家」という言葉を聞くと気持ちが暗くなる。ごまかすように笑ったトーマは、教授の女性秘書から呼びかけられた。トーマに電話があったらしい。
「お兄様からお電話だったんですけど、すみません、切れてしまったみたいです」
「兄さんが」
もう迎えに来てくれたのだろうか。約束よりも少し早い時間に首を傾げつつ、トーマはエントランスまで様子を見に行くことにした。
上着をはおって荷物を抱えると、研究室の仲間はにこやかに見送ってくれる。 楽しめよ、とか、久しぶりに兄貴に甘えてこいよ、なんてからかいもあったけれど。
いい友人にめぐまれた。トーマは口元が緩むのを堪えながら階段を下りて行く。途中で「食堂で腹ごしらえをしてきた」 テオとすれ違い二言三言交わした。
トーマは研究室のある棟のエントランスに出た。が、そこには誰もいない。正門からやや離れている上にそれなりに背の高い木々に囲われているため、そこからは人影は見えなかった。
もしかしたら遅れるという連絡だったのだろうか。さすがに軍用の連絡先は知らないのでこちらからかけ直すこともできない。外は寒いことだし研究室に戻ろうかと踵を返した、そのときだった。
「――⁉」
耳をつんざくような轟音と衝撃波でトーマはその場でよろめいた。 何が起こったのか、当然瞬時には理解できない。
しばらくして冷たい風が気味の悪い熱と焦げ臭さを運んでくる。まさかと思って見上げたその先には、黒煙が立ち上り赤い炎がちらちらと見えている。研究棟の三階付近は無残な有様だった。
「な……」
一体何が、と、口を開いたトーマの頭の中で、先ほどまでの会話が繰り返される。
――なあ聞いたか、テロの話
――ああ、知ってる。帝都のそこかしこで爆破テロがあった話だろう?
――そりゃそうなんだが、今や帝都の外でもテロや襲撃事件が相次いでるって話だ
考えられないことはないし、それになんの不思議もない。
単純な話だ。次にテロリストの標的になったのが、このヴァシコヤード・アカデミーだったというだけ。
頭では理解できているのに目の前の出来事を信じられない。
トーマはふらふらと歩き始め、エントランスを再びくぐろうとする。
「みんな、みんな無事で、いてくれ」
あんな爆発に巻き込まれていてはただで済むはずがない。テオの研究室は四階、爆発は三階。もしかしたらまだ間に合うかもしれない。
早く逃げろ、でないと――
そこで、トーマの記憶は途切れている。
§
目を覚ました時、母の顔があった。消毒液のにおいから察するに、病室なのだろう。
「今、何日ですか」
目元をわずかに赤くした母に尋ねると、あの事件から一日も経過していなかった。トーマは二度目の爆発で爆風に吹き飛ばされ、雑木林の近くで気を失っていたところを救助されたこともそのときに知った。
帝都へ戻るために近くを通っていた兄の部隊が救助部隊に先んじて行動していたことも知った。
テオが崩壊した建物の瓦礫に脚を挟まれ切断を余儀なくされたことも、彼以外の友人たちは四階で起こった二度目の爆発によって全員死亡したことも、トーマはその時に知った。
§
「感情で行動しているのではないか」
目も合わせずに兄は冷たくそう言った。
あれから二週間。アカデミーはようやく授業を再開し学生の姿も戻ってきた。そこにトーマの姿はない。 未だに生家の中で思いつめたような顔をしていると思ったら、突然「軍に入隊する」と言い出すのだ。
これが一時の気の迷いでなくてなんだと言うのだ。
カールは呆れ、何度も溜息とともに思いとどまるよう説得した。 父は一連の騒動で帝都の議場に詰めているし、母はトーマの頑固さに匙を投げたその結果カールが呼びつけられた。
「僕は冷静です」
それでもトーマは考えを曲げなかった。
「友人の仇を取ろうだとか、恨みを晴らしたいとか、そういう浅はかな考えで軍に入ろうとは思っていません」
そんな言葉が自ずから出てくる時点で、トーマはその考えを持っているのと同じだ。 シュバルツはため息を隠さない。
「では何故」
「二度と繰り返さないためです」
応接室の暖炉の中で薪がはぜる。トーマのくすんだグリーンの瞳は、恐ろしいほどにまっすぐだった。
「二度とあのような事件を起こしたくないのです」
カールは立ち上がり、飾り棚の前へ歩きながら淡々と述べた。
「お前一人が軍属になったとして、テロの類がなくなるわけがない。そこになんの因果関係も見出すことなどできない。お前はただ、自分ひとりが生き残ったことに対して自己満足の贖罪を果たしたいだけだ」
トーマが自責の念に駆られていることは火を見るよりも明らかだった。誰よりもやさしく思いやりがあるから、そんな不必要な感傷で馬鹿な思いつきをするのだ。
その愚かさにカールは苛立った。それでも弟よりはずっと冷静だったし、感情を隠すのは得意だった。
「違います! 俺は、」
遮るようにカールが差し出したのは、飾り棚に置かれていたヘルキャットのおもちゃだった。
「お前の手は何かを壊すためにあるんじゃない」
トーマが初めて作った機械仕掛けの人形を褒めてくれたのは他ならぬ兄だった。
お前には才能がある。こうやって人を喜ばせるものを作って、世の中の役に立てる。 それはとても素晴らしいことだ。もっと誇りをもっていいのだ。
忘れたはずがない。 アカデミーへ進学を決めたきっかけの言葉だったのだから。それを投げ捨てて軍へ入るのか。そう問われた気がして、軍は何もかもを破壊するのだと言われた気がして、トーマは悲しげに兄を睨んだ。
「……平和を築くために軍があるのだと教えてくれたのは、兄さんです」
人形のぜんまいを巻いていたカールは、その指を止めた。 冷たい指先が離れても、ヘルキャットはその脚を動かすことはなかった。
結局反対を押し切るようにしてトーマは帝国軍へとその所属を変えた。
折しもテロ事件を受けてか、ガーディアンフォースの設立が検討されている頃であり、トーマは一も二もなくそれに志願した。帝国軍よりも個人の裁量権が大きく、その上任地の定めもない。きな臭い情報があれば即時にそこへ向かって行動が可能なガーディアンフォースならば、遠くはなれたところで手も出せずにやきもきすることはおそらくないだろう。数か月後、辞令を受け取ったトーマはほっとしつつも焦燥を感じていた。それが何によるものかは、わからない。
「トーマ、アカデミーに通っていたあなたはとても楽しそうだった。やめてしまうなんてもったいないわ。 退学じゃなく、せめて休学にしてちょうだい」
母に拝み倒されてアカデミーは休学届を出したけれど、おそらく戻ることはないだろうと思う。
研究室のあった建物は解体され、別の場所に新築されると言う。 爆破事件のあった場所には、モニュメントが作られるとも。
それを見に行くことも、生涯ないのだろうなと、トーマはぼんやりと考えていた。
9
「大丈夫でしょうか……」
不安げな顔ではおったストールをかき寄せるエルマと、その肩を抱いてやるムンベイ。その近くに座るテオもまた、考え込むように眉を寄せている。 村人たちは全員ムンベイが曳いてきたシェルターに入っているが、いくら頑丈とはいえ赤色灯の下の表情はどれも暗いままだった。
「大丈夫よ。このシェルターはなんてったって帝国製なんだから。仮に被弾したってちょっとやそっとじゃ破られないわ」
「ムンベイさん」
エルマの手の震えを止めようと、ムンベイはできるだけ明るい声をだし、小さな手を握ってやる。
「それにアーバインもトーマも村には近づけさせないし、きっと林の中で敵は全部仕留めるに違いな――」
言い終わらないうちに轟音にさえぎられる。村からだいぶ離れているにも関わらず、これだ。先ほどアーバインから無線で知らされた「中距離射撃装備のダークホーン」の砲撃だろう。
着弾の振動から察するに、いくら帝国製のシェルターでも、直撃すれば無事では済まないかもしれない。危険だがグスタフでシェルターを曳いて遠くまで逃げるか――
「信じましょう」
テオはまっすぐにシェルターの壁を見つめていた。
「トーマはきっと、やってくれますよ」
あまりにも自信たっぷりなものだから、ムンベイは呆気にとられてしまった。なんだか肩の力が抜けてしまったようで、こんなことを口にしてしまう。
「あんたは、トーマが軍人に向いてるって思う?」
テオは少し考える素振りを見せたが、困ったように笑うだけだった。
§
アーバインは苛立っていた。
盗賊団がヘルキャットを使っているのならと昼間のうちにトーマがヘルキャットの音紋解析パターンを送信してくれていたのだが、今彼らに攻撃をしかけてくるヘルキャットのそれとまったく一致しないのだ。
「おいどういうことだ!」
光学迷彩で姿を消した敵からの砲撃に圧倒され、アーバインはトーマにがなる。 話が違うじゃないかと詰め寄られてもトーマは冷静だった。
「おそらく不正改造を施して正規のものから音紋を変更したんだろう。敵ながらあっぱれだ」
その声音に本心からの賞賛を感じとってしまい、アーバインは呆れてしまう
「感心してる場合かよ……!」
二体共に一方的に砲撃されるばかりでまったく突破できそうにない。 相変わらずダークホーンは村の方にむかって砲撃を行っている。装填に時間がかかるのか連続しての砲撃は行われないがその分威力が大きい。あれではいくらシェルターとはいえ直撃を食らえばただでは済まないだろう。
アーバインは舌打ちし、頭の中であれこれと考えをまとめ始めた。このままでは時間を浪費するばかりだ。
まずやめさせなければならないのはダークホーンの砲撃だ。重装甲のダークホーンを相手にするならディバイソンのほうが適役だが、そのためにはヘルキャットの護衛網を突破しなければならない。軽快なライトニングサイクスならばともかく、鈍重なディバイソンではただ突破することは難しいだろう。
うまくいかないものだ。
この際一か八か、サイクスでダークホーンに挑むか……かなり分は悪いだろうがここでぐずぐずしてはいられない。 アーバインがあれこれと考えをめぐらせていると、トーマが無線越しに提案してきた。
「おい、熱源カメラの感度を限界まで高めればあるいは判別できるかもしれん、やってみろ」
幸いビークのサポートがあればそれも容易だ。あくまでトーマのディバイソンであればの話だが。 アーバインのほうはビークのサポートなど言うに及ばず得られるはずもない。それに、
「さっきセンサーをやられた!」
狙ってやったのだとしたら大したものだが、サイクスのセンサーユニットは片方破壊されている。 全く使い物にならないことはないが、普段の半分ほどしか性能が発揮できていないようだった。
「何い? 貴様それでも――」
トーマがくどくどと言い始めるので、アーバインは逃げ出すようにサイクスを走らせた。
「ぐだぐだ言うんならてめえで相手しろ! 親玉は俺がやる」
「あっ! こらアーバイン、勝手な行動は――」
闇夜の中、サイクスは雑木林の奥へと駆けて行った。さすがの機体性能とパイロットの腕と言うべきか、まばらに生えた木々にはぶつかりもしない。
しかしその背後をヘルキャットは当然追いかけるに違いない。砲撃の火花を認めるや否や、トーマは声を荒げた。
「そうはさせん! ビーク! 熱源センサー感度最大!」
きゅいん、という反応音の後、トーマのヘッドマウントディスプレイ内に赤い影がいくつか投影された。林の奥へ追撃をかけるヘルキャットだ。
「これで貴様らも丸裸と言うわけだ!」
トーマがトリガーを引くと、三連衝撃砲が的確にヘルキャット二体を撃破する。残りは三体。センサーはしっかりとその影を捉えていた。
「ミニマム・ファイヤー!!」
§
林を駆け抜けたアーバインのライトニングサイクスは、しばらくして開けた場所に出てきた。どうやら林を抜けてしまったらしい。あたりには隠れられるような障害物の類はなく、ただ茫漠たる荒野が広がるばかり。当然ダークホーンどころか他のゾイドも、人影すらも見当たらなかった。
「畜生……どっから狙ってやがる」
センサーさえ生きていれば発見できただろうが、今となってはそんなことを言ってもしょうがない。ちょうど目の前になだらかな丘陵地が見える。そこからスコープと目視で確認するしかなかろうと、アーバインは歩をすすめた。
もしかしたら丘の上から砲撃しているのかもしれない。 アーバインは慎重に歩を進めた。 サイクスの上体をギリギリまで低くして、最後の数歩を一気に駆け上がる。
「いねえな……ッ!?」
丘の頂上に着地する寸前、ちょうどサイクスの喉笛のあたりを砲撃された。至近距離、しかも跳躍した途中で身動きもとれず、アーバインはそのまま丘の斜面に叩きつけられた。
「クソッ!!」
ダークホーンは丘陵地の頂上に穴を掘り、その中に身をひそめていた。登ってくる相手からは完全な死角だった。センサーが生きていれば感知できただろうが今となっては何もかもが遅い。
「システムフリーズだと……⁉」
甲高い電子音が響くコックピット内で、文字通り身動きできないアーバインは握りこぶしをコンソールパネルに叩きつけた。
「おいどうした!」
無線にトーマの声が入る。眼下を見れば、ディバイソンがその巨体を揺らし林の中から躍り出てくるところだった。 ヘルキャットはすべて片付けたのだろう。残すところはあのダークホーンのみ。
しかし。
「すまねえ! こっちはフリーズしちまった! 丘の真上にダークホーンが――」
言い終わらないうちにミサイルポッドの発射音がした。 火を吹き上げながら、十を超えるミサイルが丘の下めがけて降下していく。 が、 照準合わせのためにミサイル群が一旦真上まで上昇したのをトーマは見逃さなかった。
「ビーク!」
十七連突撃砲の砲身それぞれがミサイルをとらえて角度を調整する。間に合うのか、と、アーバインが固唾をのんで見守るが、杞憂だった。
「ファイヤー!」
正確無比の一言に尽きる。 一発の撃ち漏らしもなくミサイルを叩き落とし、迎撃に充てられなかった弾はそのままダークホーンの真上に降り注いだ。
高火力のディバイソンから容赦のない砲撃を受け、これではいくら重装甲を誇るダークホーンといえども堪え切れるものではない。
「すげえな……あ……?」
そしてそれは、ダークホーンの間近に横たわるライトニングサイクス――アーバインも見逃さない。
「てめえええええ!!」
上からはミサイルの残骸やら火の粉やらが降りかかり、その一方で撃破されたダークホーンだったものが飛んでくるわ、あろうことかディバイソンの砲弾すら近くに着弾した。
生きた心地がしないとはこういうことだろう。
ほんの数十秒ではあったが、アーバインは煉獄の中で息をひそめているような気分だった。
「殺す気か!!」
「何を言う。ちゃんと照準からは外しておいたぞ」
あっけらかんと真顔でそう言うものだから、アーバインは二の句も告げなかった。土煙の向こうから重い足音のディバイソンが近寄ってくる。
「手痛くやられたようだな」
面目次第もない。トーマに言われるのもそうだが、ムンベイに何を言われるかと思うと気が重かった。
「まあともかくこれで任務完了というわけだ」
「そうだな……」
トーマもアーバインも一仕事終えた安堵感からキャノピーを開放する。冬の夜の寒さは厳しいが、それすら胸がすっとすくように感じられた。
「村の被害はどうだ」
アーバインが尋ねると、トーマはコンソールパネルを操作する。おそらく、シェルターのムンベイと通信しているのだろう。
「幸い軽微なようだ」
ややあっての返答を聞いて、ようやく心の底から安堵できた気がした。
「そりゃよかった――」
と、視界の端で何かが動く。 丘陵地の地面がわずかに盛り上がり、動いていた。その動きには見覚えがある、どころの話ではなかった。あれはゾイドが地中を動き回るときのそれだ。
「まずい――」
とっさに二人ともコックピットに腰を下ろしてキャノピーを閉じようとする。が、 ヘルディガンナーがうなり声とともに躍り出で、その銃口を向けるほうが早かった。
10
どこまでも白が続いている。
足元には何か、やわらかいものが敷き詰められていた。
雪だろうか。
トーマは一歩踏み出そうとして、やめる。
どちらへ、どこへ向かえばいいのかわからなかったからだ。
ここがどこかもわからないのに、むやみやたらと動くのは得策ではない。そう結論付けてしばらく待つことにした。
何を?
ここにこうして立っていれば誰かがなんとかしてくれるのだろうか。そう思い込んでいるのか。
自問したところで答えなど見つかるはずもない。トーマはそのまま立ち尽くす。寒さは感じない。ただ、不安と焦燥だけは膨れ上がっていった。
どのくらいそうしていただろう。
かしゃかしゃと何かが触れ合う音がする。金属だろうか、冷たく、けれど軽い音。歯車と歯車がかみ合ってスムーズに動いている音。好きな音、心地いい音。
足元を、無数の白い四足の人形が横切っていた。それらはトーマの背後からやってきて、彼の立つその脇を規則正しく進んでいく。見たことがある。あれは、自分が作ったものたち。
この手から生まれ、この手を離れていったものたち。先頭が見えなくなるほどに遠ざかっても、背後から怒涛のごとく押し寄せる。それらはだんだんと大きくなっていき、押しつぶされそうな恐怖感すらもたらした。
自分の作ったものに、つぶされるのか。
背後で、ごうと風が巻き起こる。見上げた先、自分の頭の真上を、ひときわ大きな人形が跳躍していた。
あっと声を上げて、両腕で頭を覆いそうになる。 その刹那、トーマは確かに捉えた。
――大きくなったら、何になりたい?
少年が見ている。
何も知らないまなざしで、微笑みながらトーマを見ている。
11
ばりばりとショートする音が聞こえる。 アーバインが恐る恐るに目を開けると、そこにはヘルディガンナーの残骸が転がっていた。砲撃された跡が腹部のあたりに見え隠れしている。
一体どうして。
自分もトーマも砲撃どころかヘルディガンナーの攻撃をかわす余裕すらなかった。一体誰が。
「無事か、トーマ!」
スピーカー越しの声が聞こえる。声の主を探しアーバインがあたりを見回していると、土煙の向こうから四足歩行のゾイドが駆けてきた。
赤と黒のセイバータイガー。 ガトリングを装備した特徴的な機体はシュバルツの愛機だ。
「トーマ!」
ディバイソンに駆け寄ると、シュバルツはコックピットから身を乗り出して弟の安否を確認しようとする。何の余裕もない、切羽つまった表情だった。そこには軍人として、という体面の問題は一切ない。ただ兄として弟の無事を案じる顔だった。
「兄さん」
トーマはコックピットの中で呆然としたままだった。
「無事か⁉ 怪我はないな⁉」
あれやこれやと心配して語りかける兄を気遣うでもなく、変わらずトーマは呆けたようにコックピットに立ち尽くしている。
頭でも打ったのだろうか。それにしては顔つきはしっかりしているように見えるが……アーバインもまた怪訝な顔で兄弟のやりとりを見ていたが、トーマはようやく口を開くと、
「俺はアカデミーに戻ろうと思います」
なんの脈絡もないことを言い出した。
藪から棒に何をと眉をひそめるアーバインとは対照的に、シュバルツは弟の申し出にしばらく目を丸くはしたものの、ふっと気が抜けたように笑った。
「――そうか」
何がなんだかわからないのはどうやらアーバインだけらしい。夜明けが近づいた丘陵地へ向かって、シュバルツが率いてきたのだろう一個師団がぞろぞろとやってくる。どうやら隊長はいてもたってもいられず、真っ先に駆け付けたらしい。
ふっと笑ったアーバインの鼻先を、白い雪が掠めて行った。
§
雪が溶けるのは早かった。
久しぶりの休暇を生家の庭で過ごすシュバルツは、長い間庭師と家人に任せきりだった植物の世話に精を出している。あれもこれもと手当たり次第だったわけではないが、振り返ってみれば相当数の鉢や花壇を作って来たらしい。
「兄さんはこういうことを仕事にしたいと思ったことはないんですか」
背後で庭仕事を手伝っていたトーマが尋ねる。土で汚れた手袋で顔を掻いたのだろうか、子供のように泥がついていた。
「ない」
きっぱりとした返事に、トーマは不思議そうな顔をした。
「私は多分、趣味を仕事にするのは向いていないだろうからな。そうしてしまうと、息抜きの手段がなくなる」
一時期はコックピットにすら鉢植えの黒百合を持ち込んでいたと聞いたことがあるので、トーマはなんとなしに理解できるような気がした。
「お前はきっとうまくやれるさ」
おそらく笑っているのだろう。背中の方からは何もうかがえないが、今まで何度も聞いてきた兄の言葉がとても軽く聞こえてしまった。やっと、自分は自分の思うままにしていいそうするべきなのだと思えた気がする。
「子供のころ、僕は自分も兄さんのようにならなければならないと思っていました。家のせいにするつもりはありませんが、そういうものだと思っていたのは、事実です」
つぼみをつけたコデマリが風に揺れた。
「私もお前にそういうことを一度言ったような気がする。もうずいぶんと昔だと思うが」
それを言ったのはまさしくこのあたりだったような気がする。
兄にそう言われて、トーマは首を傾げた。
「そうですか? あまり覚えが……」
記憶にないらしいトーマを見て、脱力してしまった。
こっちはいらぬことを言ってしまったものだと、言うべきではないことを言ってトーマの道を狭めてしまったと思い込んでいたというのに。だからこそヴァシコヤードへの進学にあたっては背中を押したし、軍人になると言い出したときも止めたのだ。だというのに、トーマは兄の言葉など知らぬという。
「……いや、それならいい」
結局やきもきしていたのは自分だけで、トーマはトーマなりに自分だけで悩みぬいてここまで歩んできたわけだ。
まるで子離れのできない親になっていたような気分だった。
あるいは、信頼していなかったのかもしれない。
「テオ・ローベルも復学するそうだな」
シュバルツが話を変えると、トーマは複雑そうな顔になった。
あの事件の直後、復学するのだと息巻くトーマに「実は自分も春から復学する」とテオは笑った。ナデルバルトの長だというのに、いいのかと聞くと、
「妹が婿をもらう。彼が次の村長さ」
そのときのトーマの顔は見ものだったとムンベイはしばらく笑っていた。
「妹御の心配もなければ安心して研究に向き合えるだろうな」
「そうですね……」
今頃エルマは、幼馴染の青年と結婚式でも挙げているのだろうか。
「トーマ、」
「えっ、あ、いや!」
呆れたような兄の苦笑に、トーマは一つ咳払いをし、すうと息を吸い込んだ。
「このトーマ・リヒャルト・シュバルツ、当然親友の妹君の幸せを願っております! 臣民の幸福は帝国の繁栄に直結し、ひいては――」
シュバルツは腰に手を当てて笑う。
「トーマ、いい加減そういう口調はやめてはどうだ。お前はもう軍人じゃないんだから」
屈託なく笑う顔は、少年のころのようだった。
「そう、ですね」
軍人ではない。
事実上の退役が、その手続きが惜しくなかったというと嘘になる。 ガーディアンフォースの仕事はやりがいがあったし、もう少しでビークの射撃命中率は九十九パーセントに達するところだったのに。
けれど、今のトーマは胸を張って先へ歩いていける。
「しかし短い間でも軍人をやれたのは、いい経験でした」
そう言った後に、いつかどこかで聞いた言葉をなぞったような気がして奇妙な気持ちになった。果て、どこで誰が言ったことだったか。思い出せないが、まあいい。
それを聞いたシュバルツが満足そうに笑い頷くと、東屋から母が二人を呼んだ。 せっかく父もいるのだからお茶にしよう、と。
道具を置き、手袋を外しながら兄弟は庭を後にする。
「トーマ、お前顔に泥がついているぞ」
「そういう兄さんだって髪についてますよ」
「何? なんで早く言わないんだ」
「そんなことを言われても……まだ手入れは終わらないじゃないですか」
その足音の後では花々が色とりどりに咲き乱れている。