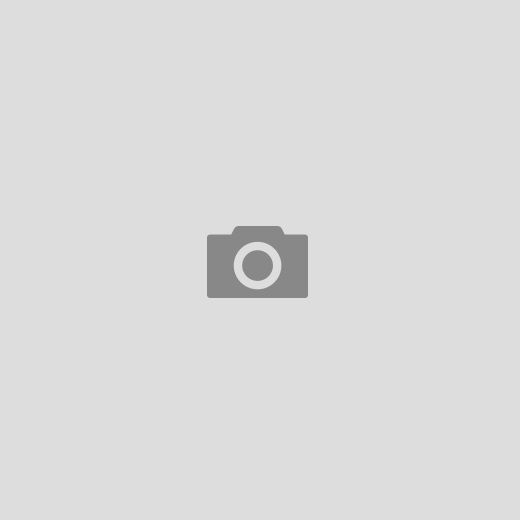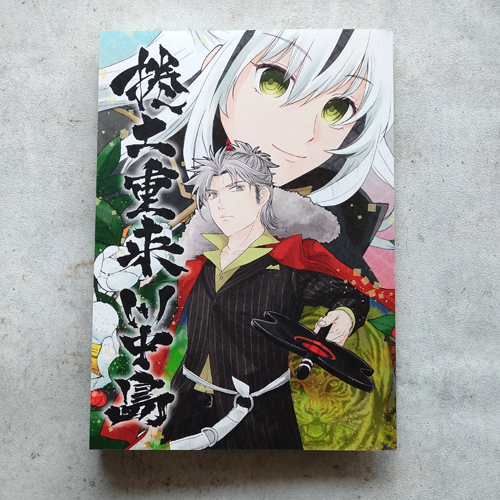「それはある日の夕方のことだった……人気のない放課後の校舎をその生徒は歩いていた……クラスメイトはもちろん、教師たちもほとんどが帰宅しているような時間……廊下も壁も血のように赤い夕陽でべったりと染め上げれている……不気味すぎる光景に、生徒は早くその場から逃げ出したくなった、どうして忘れ物なんてしたのだろうと後悔してもどうしようもない……そしてそいつが廊下を曲がった瞬間! ……“ソレ”は姿を現した……ズル、ズルズル……そんな音をたてながら、下半身だけで移動する世にもおぞましい怪異が!今!そこに~~~!!」
――というのが、上杉の語った怪談だった。いや……よくよく思い出せば、あれは怪談とはとても言えない。なにしろ本人の性格と語り口のせいでまったく恐ろしくない上に、あまつさえ途中で噛んでいて、その場にいた桐島に至っては薄く微笑みながらも懸命に笑いをこらえていた。ちなみに上杉には桐島の努力はまったく伝わっていないようだった。もっとも、たとえ桐島が噴き出していたとしても、それはそれで“オイシイ”のだろう。
ともかくそんな、一週間もすれば忘れてしまいそうなことを思い出したのには一応の理由がある。俺の目の前にある光景はその怪談モドキにある意味酷似しており、ある意味ではそれよりもずっと不可解だったからだ。
「……⁉」
時刻は正午を少し回ったところ。開け放たれたままの教室の窓からは湿気を含んだぬるい風とセミの鳴き声が入ってくる。三階の教室の外には視界を遮るものはほとんどなく、夏の午後らしい真っ白な雲がそびえているのがよく見えた。教室の引き戸を開けて中に入ろうとした俺がそれらの次に見たものは、這いつくばったような体勢の、人間の下半身だった。
もちろん、ぶった切られた人体の一部とか、人形の類ではない。よくよく見れば上半身は無事に(?)つながっているし、単に並んだ机の影に隠れて一瞬見えなかっただけだとわかる。上杉の怪談モドキのせいで一瞬声を上げそうになった自分が少し情けなかった。
だが、目の前の異常が人間だとはわかっても、その人物が――いや、あの暑苦しいルーズソックスは綾瀬だとすぐにわかるのだが――何をしているのかというのは結局わからない。何か目的があって床に這いつくばっているのは間違いないだろうが、その理由にはまったく見当がつかなかった。大体、俺の知る綾瀬優香という女子はああいう奇行に走るタイプではない。しかし、俺は綾瀬と特別親しいわけでもないので、俺が知らないだけで綾瀬には妙な習慣があるのかもしれない。……いや、ないだろう。親しくはないとしても去年から同じクラスの顔なじみなので、そのくらいは判断がつく。
ともあれ俺も教室の入り口でただ突っ立っているわけにもいかない。よりによって窓側の自分の机から鞄を回収しなければ俺は帰れないのだから。しかしこの状況、何も言わずに入っていっていいものか、それとも「何をしているんだ」と声をかけてみるべきか。どう振舞ったものかわからないまま、なぜか「ドアを開けた時点で気づけよ」という八つ当たりめいた非難まで浮かびそうになる。
「あれ? 城戸?」
が、突如として体を起こした綾瀬がこちらに気づいたので、俺の混乱はその瞬間に無駄なものとなり果てた。
「え~? いたなら言ってよびっくりすんじゃーん、てか城戸、アヤセのピアス見なかった? さっき落としちゃったことに気づいてさあ、もうマジ最悪なんですけど~教室になかったら廊下まで探すべきだと思う?」
おまけに聞いてもいないのに状況説明入りの、これはなんだろうか、愚痴なのか質問なのか……まで聞かされる。だがおかげで事態の把握はできた。綾瀬が床に這いつくばっていたのは、落としたピアスを探すためだったわけだ。
「ピアスっていうのは、いつもしてる銀色のやつか?」
見覚えのある特徴を述べると、綾瀬は何故か驚いたような顔をする。
「そうだけど、城戸、意外に見てるんだね」
俺は怪訝な顔をするしかなかった。さっきは「アヤセのピアス見なかった?」と、まるで知り合い全員が自分の持ち物を把握していることを前提にしたような問いかけをしたというのに。いや、それはともかくとして、俺は少しだけ気まずさを感じた。「意外に見ている」というのはどういう意味だろうか。
「なんか、あんま他人に興味ないと思ってた」
綾瀬は立ち上がり、両手を叩きながら「ふは、」と笑った。よくわからない感情の動きとしか思えないが、どうも俺が気持ち悪がられているわけではないらしい。
「……ピアスは見てねえな」
「そっかー……だよね、アヤセもめっちゃ探したし……」
綾瀬は誰かの机の上に腰かけてパタパタと手のひらで顔を仰いでいる。俺はといえば、どうしたものかとしばし悩んだ。用事でもあればそれを口実にこの場を後にできたのだが、どうにも俺という人間は方便であっても知り合いに嘘を言うのが苦手らしい。それに、あれだけ懸命に探そうとしているのを見た後に踵を返すのはためらわれた。
「ピアスなんて小せえもの、そう簡単には見つからねえだろ……お前、教室以外にどこに行ったんだ?」
時間はあるし、後味が悪いし、そういう消極的な理由からの発言だったが、綾瀬は俺が見たことのないような顔をした。感激と驚きと興奮が入り混じった、なんとも言い表しづらい表情だった。
「え……えー⁉ なに⁉ いっしょに探してくれるの⁉ ウッソ城戸やさし~~! 知ってたけどね!」
知ってたってなんだ。というかうるさい。俺も知ってたし再確認にすぎないが、この女は本当に四六時中うるさい。一瞬、協力を申し出た後悔に見舞われたが、撤回するのはさすがにサマにならない。
「で、教室以外に行った場所は?」
幾分うんざりしながら問いただすと、綾瀬はなぜか指折り数えつつ行動を思い返し始めた。
「今日はぁ……えーとまず朝教室に入って、それから体育館。あ、校長先生の話聞きながらピアス触ったの覚えてるから、そんときまではなくしてなかった! そのあとトイレ行ってぇ、教室戻ろうかと思ったけど暑かったから図書室でちょっと休んで……そんで教室戻ってHRっしょ? で、帰ろうとしたらピアスないじゃん! って気づいた」
「……そうか」
あまり期待はしていなかったのでそこまで落胆もしなかったが、綾瀬の発言からは落とした場所を全く絞り込めないことしかわからない。もう一度教室の中にピアスが落ちていないことを確認して、俺たちは教室を出た。まずは綾瀬の行動順をなぞるように体育館へと向かう。その道すがらも綾瀬の口は閉じることを知らんとばかりにまくし立てるばかりだった。いくら登校日とは言っても夏休み真っ只中なのだから、今まで残っている生徒はほとんどいない。いるとしても運動場か体育館か、それぞれの部室くらいなものだろう。人気のない午後の廊下に綾瀬の声はよく響いた。何をそんなに話すことがあるのかと呆れるほどだったが、あれは沈黙で間がもたないのを避けるためだったのだろうか……いや、そういう気の回し方は、上杉はやっても綾瀬はしないだろうとは思うが――
「――あ」
唐突に綾瀬の足が止まる。つられて俺も立ち止まる。ピアスを見つけたわけでもなければ、何かを思い出したわけでもなさそうだった。綾瀬は廊下の窓の外を向いている。尖った小さな顎は、ようやく話すことをやめていた。
視線の先は中庭だった。春秋の過ごしやすい季節にはここで談笑したり昼食をとる生徒も少なくないが、さすがに真夏の今は人影もない――いや、いた。女子二人と、彼女らに挟まれるようにして男子が一人、合計三人が中庭を横切って歩いている。いずれもよく見知った顔だった。もちろん綾瀬も知っている……どころか、親しい三人に違いない。だが、俺がそうであるように綾瀬もまた、あの三人に声をかけようとは到底思いつかないようだった。
三人は傍から見れば仲睦まじげだった。それぞれ両手に本を何冊も抱えているから、どこかに運んでいる途中だろう。どういう状況なのかよくわからないが、三人のうち一人はよく図書室に出入りしているので、大方司書に用事を頼まれたのを残り二人が手伝っている……といったところか。まあ、あの三人はいわゆる三角関係なので俺の思いもよらない思惑も含まれているかもしれないが。
三角関係、そういうわけでおいそれと声をかける気にもなれず、俺は三人が中庭を横切っていくのを黙って眺めていた。なんとなく気づかれたくない気がして、窓枠の外側に身を隠してしまう。綾瀬のほうは、何故か――眉間に皺を寄せていた。そこには嫌悪とか、怒りとか、そういう感情は見てとれない。ただどういうわけか、ひたすらに悲しそうな顔をしていた。
悲しい? なぜ部外者の綾瀬がそんな顔を……?
はっと気が付いてしまった。
「……お前まさか、お前まで……?」
ややこしい関係の当事者が三人から四人に? となるとそれは四角関係というのになるのか? いや、というか、綾瀬が? 本当に?
どういう言葉をかけていいのかわからないまま、ただ綾瀬が苦しそうな顔をしている原因が”そう”なのかを確かめようとした。したのだが。
「は? ――あ! 違うし! アヤセにはちょーかっこいい彼氏がいーまーすー! あん中に混じる気とかないし!」
綾瀬は意味不明と言いたげな顔でこちらを向いて数秒、俺の言いたいことを理解すると、途端に泡を食って否定した。そういえば、他校に彼氏がいるというのはわりと最近、どこかで耳にしたような記憶があった。なので、綾瀬があの三人の中にそういう意図をもって割って入ることはない、それは間違いなさそうだった。
では、なぜ綾瀬は自分のことのように悲しそうな顔をするのだろうか。だったらなんでそんな顔してんだと、聞いていいものか判断のつかない俺が口を開くより先に綾瀬は感情を垂れ流した。
「マジでそーいうんじゃなくて! そうじゃないんだけど……だって、今は三人ともあーやって笑ってるけど、いつかは、園村か桐島か……じゃなかったら二人ともか、泣かないといけないわけじゃん? それってさ、つらいよね……もしどっちか一人だけが失恋ってことになったらさあ……うわ、それ考えたくない……大体アヤセ、そーなったらどんな顔して会えばいいワケ? って感じじゃん?」
窓枠から身を乗り出して腕を外に垂らし、背中を丸めてぼそぼそとそんなことを言っている。
中庭の三人はすでに姿を消していた。
どうやら綾瀬は三人の行く末を案じてつらそうな顔をしていたらしい。ついでのように自分の立ち回りも案じているようだが、俺にはそれは、照れ隠しのように聞こえた。
綾瀬の言うことには一理ある。あの三人が今の関係をずっと先の未来まで続けていくというのは、到底現実味がない。いつかはあの三人の関係も変わるし、それは決して後味のいいものでもないのかもしれない。
しかし綾瀬優香という人間が他人のことでここまで思い悩む人間だったのかと思うと、少し意外だった。いや、意外というのも失礼なのかもしれない。綾瀬だって人並みに悩みもするだろう。それを表に出さないだけで。
「今のまま、三人もあのまま、そんでみんなで遊んだりして、めっちゃ楽しいじゃん? そしたらさ、なんかずっと、このままでもいいんじゃないかなって……あ! やだ~! こんなメソメソしてたら百合子のこと言えた義理ないじゃんね!! ……って思ったらアヤセのプリチーな顔が曇っちゃったのよ」
百合子という名前には聞き覚えがない。俺の知らない綾瀬の友人か、それとも芸能人か何かか。
結局綾瀬が話しかけているのは俺なのか夏の空なのかわからんほどに、その発言は独り言めいていた。実際俺はただの一度も口を挟むことはなかったので、その場においては壁のようなものに過ぎなかっただろう。特に返事も相槌も求められなかったのは、俺にとっては幸いだった。
綾瀬は大きく長い溜息を吐いた後、勝手に回復した。
「ま、アヤセも高3の夏だし? ちょっとセンチメンタルジャーニーなワケ」
照れ隠しのように額に指をやっている。とりあえず言いたいことはすべて吐き出したようで、表情はいつものような飄々としたものに戻っていた。
センチメンタルなんとかはさっぱりだが、感傷に浸りたくなる気持ちはわからないでもなかった。あと1年も残っていない高校生活のことや、卒業後の進路を見据えてそれぞれに努力しているクラスメイトを見ていると俺だって焦燥感に駆られる。現に、先ほど進路指導室まで呼び出されていた俺もまた、このまま高校生活が続けばいいのに……という逃避を思い浮かべたのだから。
いつまでも、このまま――甘ったるい感傷だ。
ここ(エルミン)に転入してきたころは、こういう感情を自分が持つとは想像もしていなかったし、今も自分で「ウソだろう?」と言いたくなるときもある。一年前の自分が今の俺を知ったら「悪夢のようだ」と頭を抱えるかもしれないし、もっと遠い未来の俺があの頃を俺を「悪夢のようだ」と懐かしむ日も来るかもしれな、
「城戸ってさ~モテるでしょ?」
つくづく、綾瀬優香という女は、本当に何もかもが唐突だった。
「……は?」
いきなりなんだと軽く睨んでも意に介さず、結んだ髪の毛先を指にくるくると巻き付けている。
「だってやさしいし? あと余計な事言わないし? 今のだってさ、例えば南条だったら絶対おせっきょーだし、稲葉は見当はずれの励ましとかしそうじゃん? 上杉? あいつ笑いとろうってのがミエミエ。よけーなこと言わずにそばにいてくれるのっていい男って思わない?」
「男の俺に聞くのか、それを」
綾瀬は、それもそうかと笑い飛ばした。
ともかく、どうやらそれが綾瀬の男性観らしいが、
「まあ城戸はアヤセの好みじゃないけど」
俺は対象外のようだった。なんとなくほっとした。顔に出ていたのか、綾瀬は意地悪く目を細める。
「ほら、そこで「おまえだって俺の好みじゃネーヨ」とか言わないっしょ?」
綾瀬はまた笑った。笑顔に紛れて「好みじゃないけど何考えてるかくらいはわかるよー」と、言われたような気がした。
「あ、そういう意味じゃモテモテのあいつと似てるよね。黙って話聞くの得意そう」
それが誰を指しているのか、敢えて口に出す必要もなかった。
「アイツか……」
いや、似ていないと思う。もちろん綾瀬が今言っているのは、「余計なことを言わずに黙って話を聞く」という一点でのみ、俺とアイツが似ているというだけというのは理解している。だとしても、俺としては自分がアイツと似ているとは思えなかった。なにしろ根本的なところが違う。俺は何を言うべきなのかわからずに黙っているだけだが、アイツはそのときどう振舞うべきかわかった上で黙っていることのできる男だと思う。それは決定的な違いだと思うのだが、
「ふーん? でも女の方からしたら、黙って話聞いてもらってるってことには変わんないじゃん?」
結果が同じであれば、そこまでの経緯はどうでもいいらしい。つくづくよくわからない生き物だと思った。そのよくわからない生き物と、どうして俺はここにいるのだろう……と、見失っていた目的を思いだそうとしたとき、また別の見知った顔が階段の方から現れた。
「ここにいたのか綾瀬……ん? 城戸? 珍しい組み合わせだな」
珍しい組み合わせという評価は同意するが、俺としては南条が綾瀬を探していたという事実の方が珍しい。
「げ、南条」
別に綾瀬は南条を嫌っているわけではないと思う。綾瀬が顔をしかめた理由は、さっきの「南条だったら絶対おせっきょー云々」を言った矢先に本人が現れた気まずさのようなものだろうか。
一方の南条はいつものように尊大な顔で呆れたように溜息を吐き、中指で眼鏡の位置を正している。見る人によっては傲岸不遜な人物と捉えられるだろうが、どうやら俺たちは「南条はそういうヤツだし」と流せる程度には慣れてしまったようだった。
「“げ”、とはなんだ、聞き捨てならんな、そういうことを言うのならこれはよ……元の場所に戻しても構わんが?」
南条が開いた手のひらには、銀色の小さいものが見える。
「え? あー!アヤセのピアス!」
「うるさっ……」
「……貴様は自分の声量を客観視できんのか」
この日一番の大声だったので、俺も南条ものけぞり気味に眉間に皺を寄せてしまった。よっぽど大事なものだったのか、綾瀬はキャーキャーとはしゃいだような声で、どこに落ちていたのかと南条に詰め寄っている。その答えは妙に歯切れが悪かったが、気になったのは俺だけらしい。やはり綾瀬はピアスが戻って来たという結果に満足するばかりで、南条がそれをどうやって見つけたのかという経緯はどうでもいいようだった。
ともかく一件落着。俺は教室に鞄を取りに戻ろうとしたのだが、何故か綾瀬にシャツの袖を引っ張られる。
「なんだ」
「アヤセがお礼にアイスおごっちゃる!」
なぜか綾瀬は誇らしげだった。表情はどうでもいいとして、その申し出は面倒だ、というのが正直な感想だ。
「見つけたのは南条だろ」
半ば押し付けるようなことを言うと、視界の端で南条が迷惑そうな顔をしたのが見えた。綾瀬は意に介さない。
「そうだけど探すの手伝ってくれたのには変わりないじゃん? ねー渡り廊下の自販機に新しいの入ったってたまきが言ってたから行こ~!」
よく見たら南条も袖を捉えられていた。綾瀬は上機嫌も上機嫌なのだろう、見つけた南条はともかく、何もしていない俺にも礼をしてくれるらしい。多分、礼。綾瀬自身がアイスを食べたいという欲求はまったく隠せていないが。
「いや別にいらん。俺は帰る」
心底面倒そうな顔の南条の気持ちもわからんでもない。アイスを食べている間、綾瀬はあの甲高い声で、俺たちにとってはどうでもいいことをしゃべり続けるに違いないのだから。それはまあ、面倒には間違いないのだが、無下にするのも綾瀬に悪いというものだろう。
それに、面倒だと思うことと、嫌だと思うことはまったく別だ。
「南条、そう言わずに、付き合えよ」
南条は――よっぽど驚いたのだろう、珍しく口をあんぐりと空けていた。しかし御曹司に似つかわしくない表情はそう長くは続かず、何か唸るような声(?)を出した後、黙ってうなずいた。
「よーし! じゃ行こ! 何味にしよっかな~」
スキップしそうな足取りで綾瀬は階段へと向かっていく。その後ろを、俺と南条はやや緩慢な歩みで追いかけた。
「どこで拾ったんだ?」
綾瀬に聞こえないように声を落として尋ねると、南条は「む」と一瞬眉を寄せる。何か言えない事情でもあるのかと思えば、そうではないらしい。
「敏いな……いや、実は俺が拾ったのではない。横内が拾ったらしいが、届けてくれと頼まれた」
「ああ……」
さすがに、理解した。横内は大人しい性格でさほど目立つこともなく、俺も話したことすらないのだが、綾瀬に想いを寄せているにも関わらずその綾瀬から気の毒なほど毛嫌いされているということだけは知っている。託された南条も一旦は「お前が届けるべきなのでは」と促したものの「僕が返しても、綾瀬さんは嫌だろうから……というかさすがに何度も罵られたくはないし……」と、横内は遠い目をしたという。恋は盲目という言葉があるが、そろそろ横内も光を取り戻しつつあるのかもしれない。
「どこがいいのか俺にはさっぱりわからんが……ままならんものなのだろうな」
南条の言葉は辛辣でもあり、同時に他人の感情は尊重すべきだという意志を感じさせた。
「何を笑う、城戸」
南条に軽く睨まれる。どうやら顔に出ていたらしい。
「いや、一年くらい前のお前なら、「綾瀬のどこがいいのかさっぱりわからん」で切り捨てるだけだっただろうに、変わったな、と思っただけだ」
南条は一瞬悔しそうな顔で言葉に詰まった。別に言い負かそうというつもりでもなかったが、南条は宣戦布告とでも受け止めたのか、なぜか俺に反撃してくる。
「変わったというならお前のほうがよっぽどだな。一年前のお前なら綾瀬の提案など蹴っているだろうに」
自覚していなかったわけではない。ただ、南条から見てもそうなのかと思うと、なんとなく気恥ずかしいような気がしただけだ。
「……そうかもな」
言いたいことはわかる。俺だって珍しいと思う。アイスが食べたかったわけではないし、断って綾瀬の機嫌を損ねてしまっては……なんてことも考えてはいなかった。
ただ、そんな日もあっていいような気がしただけだった。
「ちょっと二人ともおーそーいー!」
階下から綾瀬が叫んでいる。相変わらずやかましい。これ以上やかましくなられても困るので、俺たちは歩みを速めた。
多分――残り少ない夏の日に、なんということもない思い出を残したかったのかもしれない。17歳の俺は、いつかどこかの遠い未来で「あれはなんだったんだろうな」と笑える記憶が、一つ増えることをよしとしたのだろう。
腕組みした綾瀬と、1時には帰るからなと宣言する南条。よくわからない組み合わせで、綾瀬が選んだよくわからない味のアイスを食べて、中身のない話を続ける。一つだけ収穫があるとすれば、百合子の正体だけだったが、きっと百合子という名前を俺はすぐに忘れてしまうだろう。
反面、渡り廊下の木陰から見た空の色は忘れられないほどに鮮やかだった。甘ったるいアイスの赤が、よく映える夏だった。