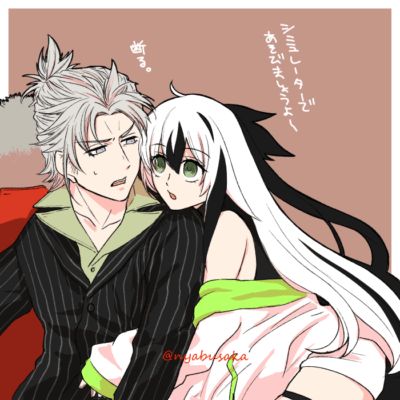救いはあるか
ナオミが死んだことを知ったとき、正直に言うと半分くらいは諦めがついていたから取り乱すこともなかった。
そうは言うもののもう半分は「それでも、もしかしたら」なんて期待を持ったままだったから、あたしは冷静なように見えて内心かなり動揺していたんだと思う。
「オイ、」
業魔殿――ビーシンフル号から見る芝浜の夜景は悪くない。眠らぬ街という言葉がよく似合う繁華街が、さっきから滲んで見えるのは自分が一番よくわかっている。
外の景色を見るためだけに作られた広い展望室には、背の低いテーブルと揃いのソファが何組か配置されている。すわり心地もよければ趣味もいいので、貸切状態なのをいいことについつい長居してしまっているが、ここでぼんやりしている理由はそれだけではない。
悲しみを消化するのは、一人きりがよかった。
粗暴な足音が聞こえてきても、背後から声をかけられても、相手が誰だか知っていながらあたしは振り向かなかった。こんな顔、見られたくないし。今だけ一人にさせてほしい。
「聞こえねえのか、レイ――」
キョウジ……スケロクは無理やりソファに、あたしの隣に腰を下ろして、それから意外なことに絶句しているようだった。
この男は泣いている女を前にしても、面倒臭ぇと悪態を吐きこそすれ、気を遣ったりましてハンカチを差し出したりなんてことは絶対にない。だから、すぐに立ち去るだろうと思っていた。大体、彼でなくともいい歳した大人が靴を脱ぎ散らかしてソファの上で足を抱えて泣いているなんて、係わり合いになりたくないに決まっている。
けれどあたしの予想に反して、スケロクはそこから動こうとしなかった。かといって何を言うでもない。さすがに気まずくなって、「なんでここにいんのよ」と、鼻をぐすぐすさせながら問うと(自分でもこんなに情けない声になっているとは思わなかった)、
「ここはおまえの部屋じゃねえだろ」
文句あんのか。と、妙に懐かしいへらず口が返ってくる。
昔に戻ったようだった。それがなぜか、嬉しかった。黙っていると喜んでいるのがばれそうな気がして、とっさに口を開いてしまう。
「あんたの部屋でもないじゃない」
「まぁな……」
スケロクは上着のポケットから煙草を取り出し、さも当然のような顔で一本咥えた。
「あ、ちょっと、ここ禁煙なのに」
「誰もいねえからいいだろ」
「あたしがいるでしょうが!」
静止もどこ吹く風、結局ジッポライターで火をつけてしまった。憎たらしい笑みを浮かべておいしそうに煙を吐きながら、スケロクはちらとこっちを見た。
「おまえはノーカウントだよ」
馴染みの薄い顔が、よく知った風に口元を歪めている。
「失礼な男ね……あんたってほんと変わらない」
外見――物理的な身体が変わっても、彼の魂は何も変わらないのだろう。煙草の銘柄も、火をつけるときに首をかしげる癖も。
何にも、変わらない。
世界の全部が変わらないままだったらよかったのに。甘い考えはスケロクの声でかき消される。
「親友だったって?」
ナオミのことを言っているのはすぐにわかった。彼女が死んだのを知らせてくれたのはマダム銀子なのだから、スケロクだってすでに聞き及んでいてもおかしくはない。
「うん。師匠同士が仲良くて、一緒に暮らしたこともあったわ」
「ふぅん」
興味なさそうな返事に、なんとなくほっとした。同情されたいわけではない。突き放されたほうが吹っ切れるかもしれない。そう思うと、勝手に口が開いていた。
「……あたしもよく知らないけどね、彼女の兄弟子がこっちに殺されて、それであたしのこと恨んでたみたい」
「くだらねえ」
嗤うわけでもない。スケロクの声には淡々とした響きだけがあった。
「こんな因果な商売やってりゃ、そんなことザラだろ。いちいち仇だ復讐だなんて言ってたらお互い命がいくつあったって足りやしねえ」
「……?」
ひどいことを言われているような気もするけど、これはもしかして慰められているのだろうか?
いや、そんなまさか。キョウジだったころの彼は他人を蹴倒し踏み潰し、通った後にはぺんぺん草も生えないような男だったのだから。あたしを慰めるくらいなら喜んで悪魔の一ダースくらいは「掃除」するだろう。
一拍遅れて「そうね」と肯定すると、スケロクはため息のように紫煙を吐き出した。呆れているに違いない。
「それでおまえは、自分のことを殺したいほど憎んでるやつが死んだってのに、律儀にメソメソしてんのか?」
言われてみれば嘆く義理もないのかもしれない。でも、幼いころの思い出をすべて否定するのはつらい。
「……まぁ、ね。いくら恨まれてるってわかってても、やっぱり親友よ。死なれちゃったらもう終わりだもの。会って話せばもしかしたら、とか、考えてた……し。あはは……甘いよね」
こうやって割り切れない感情が残っている自分に、ほっとしているのは甘さだ。自分でもわかっているし、彼にだって見透かされている。
「そうだな」
「なによ、即答?」
「それ以外に言い様がねえんだよ」
へっ、と笑ってスケロクは煙草をもみ消した。手のひらには銀色の携帯灰皿が乗っている。歩き煙草とポイ捨ての常習犯だったくせに、改心したんだろうか。いや、それはないだろう。
ないだろう、と確信しながら、でも彼だって少し変わった気がした。あたしの話に、ほんのちょっとでも付き合ってくれる程度には。
結局これは彼なりに励まそうとか慰めようとかそういうつもりだったのかもしれない。そう思い当たるとなんだか無性に恥ずかしいような気がして、わざとらしい声を出した。
「ほんっと、やさしくないよね。キョウジ君はあんなにやさしいのに」
「……おまえはほんっとに口がへらねえな」
「あら、ありがと」
スケロクは二本目の煙草を咥えたまま、怪訝な目であたしを見ていた。謝辞の意味に気づくほどマメな男じゃないのはよく知っている。でも一生気づかないほど馬鹿でもないからそのうちわかるかもしれない。
次に会うときはまた別の顔をしているんだろうか。そう考えると、なんだか焦りのような悲しさが湧いてくるようだった。
「キョウジ、」
姿形と一緒に、魂も変わっていくのだろう。もっと人に優しくできる葛葉キョウジ。うん、薄ら寒い。
「あたしが死んでも泣かないでね」
明るすぎる夜景のせいで、お互いの顔が窓ガラスに映りこまなくてよかったと思った。
「泣くか、馬鹿」
彼がどんな顔をしてそう言ったのか、知らないほうがきっといい。
(了)
笹舟の行き着く先
俺はときどき、何かが無性にこわくなります。
なぜ青年がそんなことを言ったのかわからないし、「何か」というのが何であるかなど麗にはわからなかった。
せせらぎのように流れ落ちる水の筋が、八月の日差しを受けてきらめいている。じっと見つめていると落ちているのか上っていくのかわからなくなりそうだ。
麗と、キョウジと名乗る青年は、揃って庭を眺めていた。別に面白いものがあるわけでもない。そうしろと命じられているわけでもない。他人の家に上がりこんでいる手前、膝は崩さずにじっとしている。
一週間前、この家の主は死んだ。
特に親しかったわけでもなければ知己でもなかった。生前の、「人間だったころの」姿すら写真でしか見たことがない。
人には言えぬ生業ゆえに、二人はここに座っている。立派な、という形容が似つかわしい邸宅は、豪奢でありながらどこかむなしさのようなものを感じさせた。人の手がどこまでも加えられた人工の庭を、単純に美しいとは言えないのと似たようなものだろう。
風鈴がゆれ、冷たい音を奏でている。その音に、キョウジはわずかに肩を震わせた。きっと何かに呼ばれたような気がしたのだろう。麗にもそれがわかる気がした。
一週間前、この家の主をキョウジは殺した。
正確には、「主だった異形のもの」を消し去った。
あまりに急な依頼だったもので、なぜ主がそのようなことになったのかなど二人は知らない。しかし、知らぬでは許されない。第二第三の異形のものが現れてはかなわぬ。それは己らの手間や億劫さのためもあろうが、見知らぬ誰かの平穏を徒に乱させたくはないという、ある種の義憤や使命感でもあった。
麗はししおどしが傾くのを見るでもなく見ている。
主はどのように生きていたのだろうか。何を生業とし、何を好み、何に心を動かしたのだろうか。もはや語る口も持たぬ上、魂すら消滅した彼に尋ねることもできぬ。
酷ではあろうが、残された細君に知る限りのことを聞き出すしかない。二人にできることはそれだけで、二人がやらねばならぬ最低限のこともそれだった。
彼女は何を知っているのだろうか。何も知らないのではないだろうか。
そのほうがいいと思った。
(ああ、だめね。気持ちがつられそう)
膝の上で握り締めた拳に力をこめる。情にほだされて甘い考えなど起こすなど自分らしくもない。かつてのキョウジにならば気取られていたに違いないだろう。
横目で見た現相棒は、むっつりと口を結んでいるかと思いきや、妙に穏やかな顔で庭の木々が風に揺れるのを、否、その先の何かをじっと見ていた。夏の蒼穹は濃く、息が詰まりそうになる。あんな青の先には、一体何が沈んでいるのだろうか。
ちりん、ちりんと風鈴が騒ぐ。
俺はときどき、何かが無性にこわくなります。
自分にも恐ろしいものはある。
麗は今、おそらく何も知らぬだろう細君を疑わざるを得ない自分の立場がわずらわしく、恐ろしい。この隙間から魔が侵食していったとしたら、と考える弱さが恐ろしい。自分が何を好み、何に心を動かし、果たして真実生きているのか断言できぬ心もとなさが恐ろしい。
それでも、かろうじて顔にも気配にも出さぬよう気を張っていることはできる。長年の修行は肉体だけでなく精神をも十分に鍛え上げた、その結果だ。
しかしキョウジは、ほんのつい最近まで何も知らぬ善良な市民だった彼は――
俺はときどき、何かが無性にこわくなります。
なぜ平然としていられるのだろう。
一度死に、他人の肉体を得、彼はそれでも確固たるものを持っているのだろうか。
すうっと細められた目はおそらく、麗とは別のものを見ている。それは暑い夏の光景だろうか。それとも冷たい異界の魔窟だろうか。
麗は今、葛葉キョウジが恐ろしい。
(了)
抜き身
――御前、そのようであっては、いつか己が身に災いをもたらすだろうねえ。
覚えている最初の記憶などないに等しい。子供の頃は塵溜めを漁り残飯を食らい、今は自分が死体の山という塵溜めを作っているようなものだ。
葛葉狂死にとっては、彼自身を取り巻く世界は「自分」と「自分以外」の二分にしかできず、自分以外のものには等しく価値など見出せない。見出せないどころか価値などないに決まっている、そうとしか思えない。そう思わなければ、自分を捨てたものを切り捨てなければ――
――まぁ、かわいそうに。あんさん、いつも惑い児みたいな目ぇして
哀れまれることが嫌いだ。同情に寄り添われることが嫌いだ。
かつて、女悪魔がその赤い目を細めてそう言ったことがあった。同情しているフリをして、こちらをとり殺そうとしているのならば、まだマシだった。本心から気の毒だと思っている、それがどうにも耐えがたかった。屈辱? 動揺? えもいわれぬ不快な衝動が胎からこみ上げて吐きそうになる。
腹が立ったので狂死はその悪魔を焼き殺した。断末魔を上げることもせず、炎につつまれたその存在が、最期に残したまなざしの色など見もしなかった。
――人間のくせに人間が嫌いなのね。だったらアナタも、こっちにくればいいじゃない?
お断りだ。
どこかに属することなどこれまでもこれからもありえない。無価値な愚物どもと十把一絡げにされることを思うと胸糞悪くなる。
なぜこのように腹立たしいことばかりなのだろうか。自分は何に対してこの刃を振り上げているのだろうか。悪魔を斬ったところで胸のつかえがなくなるわけでもない。人間を斬っても同じだ。当然だろう。すべて等しく、価値はない。零はいくら重ねても零のままだ。
――坊、そないなところでどうしたんや?
初めて触れられた悪魔は、角と獣の耳を生やし、やさしい女の声をしていた。
ひどい雨の夜だった。泥だらけで長屋の裏手に座り込んでいたら、ぼうっと目の前が淡く光っている。その中心にそれはいた。二本の足で立ち、美しい着物を着ていたが、それは明らかに人間ではなかった。けれど、今後あのように美しいモノにお目にかかることはないだろうと確信させる凄み――のようなものが、あった。
――坊?
まだ数えで五つにもなっていなかったので警戒することも思いつかなかった。捨てられた子供に、甘い乳のにおいを拒めと言うのは酷だっただろう。母親の顔など知らない。それでも母性を嗅ぎ取った童は、たおやかな指先に導かれるまま、その胸に抱かれた。
――ああ、坊は悪魔をよう使える、その血がそうさせる、うちにはわかる。坊、一緒に来んか?
一緒に。甘美な響き、魅力的すぎる誘惑。そして破滅へと結びつくもの。
どこかうっとりとしたように目を細めたそれの頬に手を伸ばそうとした。かかさま、と呼んでみたかった。開きかけた口に雨の雫が流れ込む。何を言おうとしたのか、それの口元が緩んだそのとき、ガラス戸をひっかくような甲高い悲鳴を上げてそれは霧散した。
何が起こったのか理解できなかった。寸の間のあと、陸軍の兵たちがぞろぞろとやってくる。
調伏しそこねた悪魔がどうとか、何某少尉がお手柄だとか、よくわからない言葉ばかりが頭の上を滑っていく。
狂死の手は空を掴み損ね、だらんと垂れた。
理解できたのは、女悪魔を討伐した陸軍兵たちもまた、悪魔を使っていたということだけだった。
――抜き身の刃のようだねえ。
正確に何年経ったかなど定かではない。
おそらく二十歳前後になった彼は「狂死」の名を名乗ることにした。
別段、意味はない。狂い死にさせたい相手がいるわけでもないし自分がそうなりたいなどと捨て鉢になっているわけでもない。
名前を名乗ると相手が鼻白んだような顔をする。それだけは見ていておもしろかった。自分が狂っていないとでも思っているからだろう。そんなことを証明する手段などないというのに。
しかし葛葉の者だという、眼前の人物だけは面白そうに笑うばかりだった。銀細工の煙管を旨そうにふかし、狂死を「抜き身の刃」と評している。
――そうもさらけ出して、こわいものなどないと言いたいのかい?
言いたいも何も、恐れるものなど別にありはしない。
答えるのも億劫で、睨み返すことでそれに代える。年齢も性別も不祥の人物は、相変わらず狂死をじっと見ていた。まるで見世物小屋の中をのぞいているかのようにも思えたし、贔屓の役者でも見ているようにも思えた。
――御前、そのようであっては、いつか己が身に災いをもたらすだろうねえ。
脅しならもっとマシな言い方にしろ。
それだけ言い残して狂死はその場を後にした。
災い。
それが何を意味するのかなど狂死には関係のないことだった。
それは彼にとって価値のないものであり、仮に降りかかった災いが死を招いたとしても、それすらもはやどうでもいいと思えた。
雨が降っている。いやな気分になる。
その理由も、狂死はもう覚えていない。
(了)
廻
多聞天、というのは仏教における武神の一柱であって、寺社の名前ではない。本来ならばこの場所を表す名が別にあるのだが、彼にとっては些末事だったのだろうか、相棒の帰りを待つのはいつも「多聞天」の境内だった。
晴れていれば日がな一日、燦燦と降り注ぐ陽光を浴びながら毛繕いをする。
気が向けば人間の女子供にその毛並みを触らせてやるのもやぶさかでない。
業斗童子(ゴウトドウジ)という名の黒い猫は、そうして代わり映えのしない毎日を穏やかに過ごしていた。
この街は、明るくて暗く、穏やかでかしましい。
彼がまだ人間の姿を得ていたころは、あちらこちらに影を落とす高い建物はなかった。今や帝都のいたるところに、高層のビルヂングが生えている。一体何が楽しくてそのようなものを造るのか理解もできないが、それがこの街の選んだ在り方であり、人々の願った結果に違いない。
で、あれば――帝都守護の任を受けこの地に滞在するデビルサマナー……の、相棒にしてお目付け役であるゴウトは、たとえ気に入らないとしても、その在り方を曲げるなどとは思うべくもなかった。
世の流れにはあらがわず、人の営みは見守るのみ。
子供たちが蝶を追いかけている。甲高い声は決して好ましいものではないのだが、ゴウトはただ緑色の目を細め、そっぽを向くように寝姿の頭を動かすのみだった。
この街では大きな争いはない。些細な喧嘩は日常茶飯事で、稀にそれが大事になって死傷者が出ることもありはする。だが、この街に動乱はない。死を振りまく疫病もなく、政変の兆しも見られない。
こんな平穏がかつてなかったわけではない。過去にも、そしていかなる場所にも、穏やかなひと時が訪れないことはなかった。しかし人々がいくら願っても、不変というものは存在しえない。
逆説的に言えば、だからこそ帝都守護などという任が存在する――そう認識してもいいのかもしれない。
「ゴウト」
耳慣れた声が、ゴウトの意識を揺り戻す。鼻先をかすめる退魔の香。外套姿でその場にしゃがみこむのは彼の相棒、十四代目葛葉ライドウだった。
「うん? 早かったな」
正確な刻限はわかりかねるが、通常よりも一刻ほど早いように思う。ゴウトの問いに、ライドウの名を継ぐ少年はその理由をなにやらと述べていたが、特段興味もわかなかったのですぐに忘れてしまった。
一人と一匹は、まだ日の高い帝都の街を往く。時折ライドウと顔見知りの人々が声をかけてきたり、女学生風の何人かが熱烈な視線だけを投げかけてきたりする。目的地は下宿先兼勤務先の銀楼閣・鳴海探偵社。所長の男はどうせ、マッチ棒の楼閣づくりに精を出しているのだろう。
毎日は、穏やかに過ぎる。
悪魔がらみの事件は起こるが、過去に起こった大きなものと比べれば大した脅威ではなかった。
ライドウは青年へとたくましく成長し、鳴海は頭に白いものが目立ち始めた。
ただゴウトだけは、いつまでも変わらない。
§
それからほどなくして、帝都は変わった。帝都だけではなかった。
国と国との争いが、否応なしにあらゆるものを飲み込み、推し流し、根こそぎ焼き払った。
帝都守護。
常人ならぬ存在とはいえ、もはや一個人になしえるようなお題目ではなくなっていた。
潮時かもしれない。
目尻に年齢が刻まれつつあるデビルサマナーがそう感じたのかはわからない。しかし戦争が終わり、何度目かの復興に沸き立つ帝都から、一人の男が姿を消したのは事実だった。
人は変わる。街も変わる。
目まぐるしい時の流れは、かつて身をもって味わったことがある。人間の成したことを/成すだろうことを突きつける冷たい回廊で。
人は変わらない。そう簡単には、変われない。そう希っていても、人は時として流されていく。
だが葛葉ライドウは違う。ゴウトはそれを知っている。
襲名のときに定めた己の在り方は、変えられることなど赦されていない。それは行動を定義し、魂を縛り付ける、閉ざされたものだった。それに何かを感じたことなどない。生き物が呼吸をするのと同じに、彼にとっては思考の埒外にあるような「当然」のことなのだから。
そしてそれは、ゴウトも同じ。彼は自分と同じ在り方を選んだ男を何人も知っている。この先どのように世界の仕組みが変わろうと、彼らはその隙間で――たとえひっそりとではあっても――その営みを続けていくことを知っている。
花が咲き、夕べに散る。
星が瞬き、天を巡る。
雨は地を濡らし、芽吹きを呼ぶ。
季節は何度も流れ、また繰り返す。
§
「そう拗ねないでください。こうしないと電車には乗れないんですから」
白銀のような長い髪を揺らし、その人物は片手に持つ大荷物の中に声をかけた。携帯電話での通話は終わったらしい。
大荷物――ケージは人間が入るようなサイズなどでは断じてない。張りのある布地でできたそれの大きさはせいぜい五十センチ四方で、一面は黒いメッシュの生地が貼られている。中には同じ黒の毛並みを持つ猫が、鳴き声も上げずに丸くなっていた。
最近では電車に飼い猫を乗せるにも様々な規定がある。決められた大きさのキャリーケースに入れておかなければならないし、その分の追加料金だって予め取り決められている。
黒猫は不本意だったが、納得するしかなかった。
しかし不本意とは言ったものの、思い返せばそもそも電車――初期は蒸気で動いていたので電車ではないが――というものが走り始めたころも、飼い猫やら犬やらと同乗する人間はそう多くはなかった。そう、そうだ。黒猫をつれてどこへでも行く相棒は物珍しい目で見られていたものだった。療養中の当代からすれば「考えられない」ことだろう。
電子音のベルが鳴り、空気のような音を立ててドアがひとりでに閉まると、小さなケージを乗せた大きな鉄の箱は動き始めた。ややノイズまじりの車掌の肉声アナウンスを追いかける、録音された無機質な案内。時速八十キロを超える快速の車内は様々な年代の乗客でほぼ満席だった。黒猫はメッシュの檻越しに周囲を一瞥する。幼児を連れた女性、談笑する老人たち、鞄を抱えて転寝する背広姿の男性、ドア近くに立っている詰襟の集団は、高校生というやつだろうか。かつて師範学校に通っていた相棒の姿を思い出し、隣に座っている人物と見比べる。
よくもまあ変わったものだ。
口に出さなかったのは、彼なりに当世に馴染み、場をわきまえてのことだった。電車の中で猫が鳴けば、暫定飼い主殿は困惑するだろう。
電車はゆるやかなカーブに差し掛かる。県境を越えれば、まもなく目的の街へと至るだろう。
§
そこは初めて訪れるはずなのに、どこか懐かしさが感じられる場所だった。
「……葛葉探偵事務所?」
黒猫は目を眇めた。重い扉をくぐり、ケージから出た先はなんとも豪奢な内装の建物である。よく手入れのされた床には自分の姿が反射しているし、調度品も高価なものばかりだった。
「おい」
ステップフロアの上から視線が向けられている。恰幅のいい初老の男が、その体格に似合わないほど細かい皺を眉間に寄せて一人と一匹を眺めていた。
「なんでまた俺のとこなんだ」
不機嫌というよりは不可解な口ぶりで男が尋ねる。黒猫は、その声に聞き覚えはない。が、彼の纏っている奇妙な雰囲気には何かしら感じるものがあった。
「理由は特にありませんけど、強いて言えば様子見も兼ねて。それに、私はあなたにはいろいろと貸しがありますから」
こちらはなにやら上機嫌だった。彩られた唇は本心からの笑顔を作っているが、そこには何か、愉快さによってそうなっているような――いわば人の悪さが滲んでいるようにも思えた。
それでようやく、理解が追い付いた。
葛葉を名乗る得体の知れない男、目付け役の態度、常人とは一線を画した雰囲気。
(やれやれ……)
黒猫は呆れた。わざわざこんな場所まで自分を預けるために足を運ぶとは酔狂にもほどがある。呆れの理由はそれが一つと、もう一つは自分の勘が鈍ったのではないかという自嘲だった。
二人はその後も、「他所をあたれ」だの「文句が言える立場ですか」だの、言い合いからは程遠い応酬をしばらく続けていたが、結局傍から見ても力関係は歴然で、口ひげを蓄えた男が言い負かされる結果に落ち着いた。そんなことをしなくても最初から分かり切っていた結末ではあったが。
「きっと引き受けてくれると思っていました。ではよろしくお願いしますね。
――仲良くするんですよ」
まるで母親か何かのような口ぶり……というのは、残された一人と一匹に共通の感想だった。
まあこの男についてそう振舞うのも仕方あるまい。何せ目付け役と問題児なのだから――と、黒猫は納得する。
まあそう言いたくなるのも妥当か。何せかつてはこの猫と共に過ごしていたと聞くし、懐かしさからそう口走るのもむべなるかな――と、探偵事務所所長は合点し、革張りの椅子にその身をどっしりと落ち付かせる。
「で? どこ行くんだよ、あいつは」
男の口ぶりは見た目よりも若い。人の出払っている事務所の中で何を取り繕うでもないのだろう。
猫は正直に行き先を告げた。サマナーであれば彼の言葉は人語として認識できる。男も例にもれず、黒猫の返答に「そうか」とだけ返した。何度も肉体を取り換えているわりにその実力は衰えていないらしい。
(まあ、四天王の一角なのだ。そう簡単に耄碌されても困る)
いや、結局今は別の男がその立場なのか? 黒猫は自問したが、出窓から降り注ぐ午後の陽光に思考を妨げられる。午睡の誘惑はいつであっても耐え難い。かつての多聞天を瞼の裏に描きながら、彼はゆっくりと体を丸めた。
人は変わる。街も変わる。そして自分だけは、取り残されてここにいる。
それは孤独と呼んでもいいものかもしれないが、苦しいと感じた覚えはあまりない。この男も同じだろう。
瞼を開けてみたくなるが、黒猫はそれをしなかった。なにやら興味深そうな視線が向けられている気配を感じていたので、素知らぬふりを決め込むことにした。
しかし――
(……フフ)
黒猫は、幾分上機嫌だった。結果論とはいえ、お互い似たような身の上に落ち着いてしまっている。しかし年季はこちらが上。断じて名誉なことではないが、同じ境遇の存在にヤツが関心を持っているというのは実に面白いし、得体の知れぬ優越感すらこみあげるのだった。たとえ相手が、さしたる面識のない間柄であったとしても。
(葛葉、か)
強いて言うならば、彼の在り方は初代の男と少し似ている。その事実が僅かばかり溜飲を下げさせるのかもしれない。
果て、自分はこんなにも人の悪い考えをしていただろうか――などと益体のない思考をめぐらせながら、黒猫は眠りに落ちていく。
時刻は午後三時を少しばかり回ったところ。商店街の只中にありながら、重い扉は一切の喧騒を遮っている。まるで静謐だけがそこにあり、魂だけの男たちなど忘れ去られたかのようだった。
葛葉探偵事務所の午後は、ただ静かに流れていく。
これまでと同じように、これからも変わらずに。
(了)